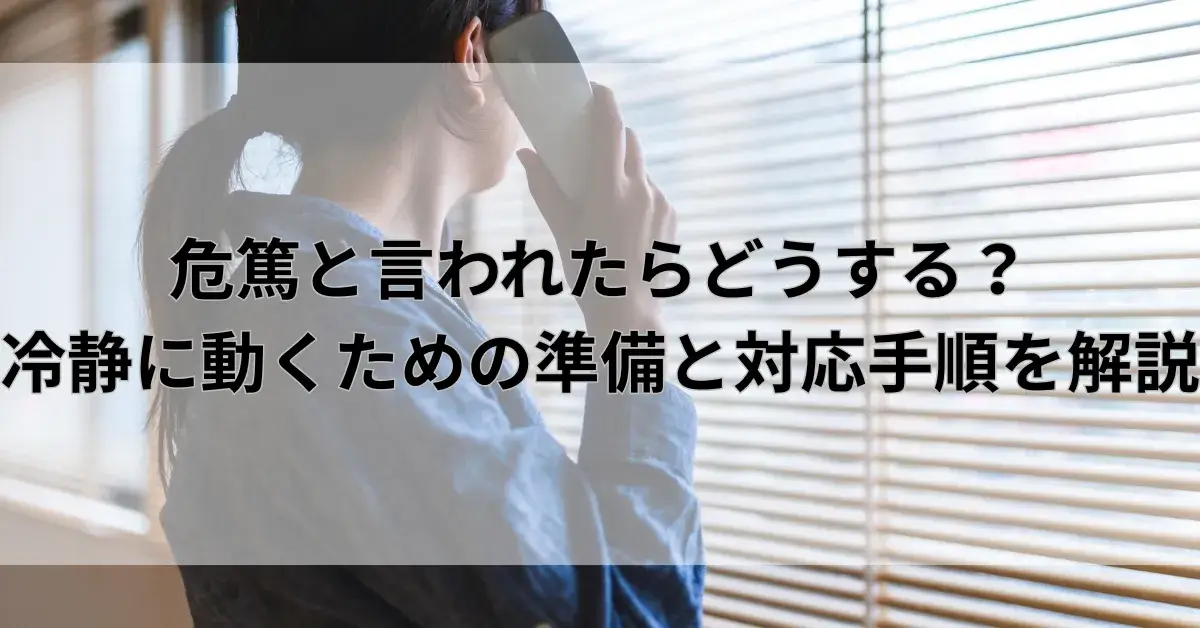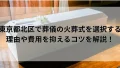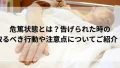突然「危篤です」と告げられると、多くの人は何からすべきか分からず混乱します。
しかし、事前に対応の流れを知っておくことで、冷静に最善の判断ができます。
この記事では、危篤と言われた際に行うべき行動、準備する持ち物、そして心の整理までを段階的に解説。
読後には「今何をすべきか」「どんな心構えで臨むべきか」が明確になり、慌てず大切な時間を過ごせるようになります。
危篤と言われたら最初にすべき行動とは
危篤と言われた時の最初にすべき行動として、医師に現在の状態を詳しく聞き取ることや病院に向かうための準備を行う、家族や親族に連絡することです。
- 医師から危篤を告げられた直後の確認事項
- 病院へ向かう際に準備しておくべき持ち物
- 家族や親族へ連絡する順番と伝え方
医師から危篤を告げられた直後の確認事項
愛する家族が危篤状態であると突然知らされたとき、誰でも動揺し、冷静さを失いがちです。
しかし、このような緊急の事態こそ、まずは深呼吸をして心を落ち着かせ、必要な情報を正確に把握することが肝心です。
病院へ急行する前に、担当の医師や連絡をくれた人から、現在の容体(意識の状態や呼吸の様子など)を詳しく聞き取りましょう。
また、病院の正確な名称や所在地、病棟、病室の番号といった、駆けつけるために不可欠な情報、さらには面会に関して時間や人数の制限があるかどうかについても確認しておくべきです。
可能であれば、後の情報共有のために、これらをメモに控えておくと安心です。
病院へ向かう際に準備しておくべき持ち物
一刻も早く病院に駆けつけたい気持ちは山々ですが、危篤状態が数日間続く可能性もあるため、宿泊に備えた準備をしておくと後で困りません。
特に、数日分の着替えや洗面用具、常備薬などは用意しておきたい品です。また、親族や関係者への連絡手段としてスマートフォンと充電器は必須の持ち物です。
病院までの交通費や滞在中の飲食費、万が一の際の支払いを見越して、ある程度の現金やキャッシュカードを財布に入れておくことも重要です。
もし遠方から向かう場合は、後で自宅に戻る時間がないことも想定し、喪服を一式持参すると良いでしょう。
移動の際は、気が動転している状態での車の運転は避け、安全を最優先にタクシーなどの公共交通機関を利用することが推奨されます。
家族や親族へ連絡する順番と伝え方
病院へ向かう準備と並行して、危篤の事実を大切な人々に伝える必要があります。
連絡の順番は、まずは同居の家族、次に危篤者から見て三親等までの近親者へ速やかに知らせるのが一般的です。
連絡は緊急性が高いため、時間帯を問わず電話で行うのが基本です。早朝や深夜にかける場合は「夜分遅くに申し訳ありません」といった配慮の言葉を忘れずに添えましょう。
伝えるべき内容は、自身の氏名と危篤者との関係、現在の病状、そして入院先の病院名や住所、病室番号といった必須情報を、落ち着いた口調で簡潔に伝えることが大切です。
また、病院に来てほしいのか、それとも連絡のみに留めるのかといった意向も合わせて伝えましょう。
危篤と言われたら意識しておく心の準備や病院内での対応について
危篤と告げられた時のどう過ごせばいいのか、医師か看護師とのコミュニケーションの取り方、冷静さを保つための心構えと支え方についてご紹介。
- 最期の時間をどう過ごすかの考え方
- 医師・看護師とのコミュニケーションの取り方
- 冷静さを保つための心構えと支え方
最期の時間をどう過ごすかの考え方
医師から危篤を告げられたら、回復の見込みがほとんどない厳しい状態であると理解し、悔いのないように最期の時を過ごす心構えが求められます。
何よりも大切なのは、できる限りそばに寄り添い、本人の存在を支えることです。
危篤状態でも聴覚は最後まで残っている可能性が高いとされているため、意識がないように見えても、感謝の気持ちや愛情、楽しかった思い出などを穏やかに語りかけましょう。
また、手を握ったり、体をそっとさすったりするスキンシップは、本人に安らぎを与えることにつながります。
ただし、本人の近くで亡くなった後の手続きや葬儀に関する具体的な話をするのは、本人や周囲の家族への配慮に欠けるため控えてください。
医師・看護師とのコミュニケーションの取り方
危篤の状況下では、治療の継続や延命措置の是非など、重要な医療上の判断を迫られることがあります。
そのため、医療スタッフと密に連携を取り、状況を正確に把握することが不可欠です。
現在の容体や今後の見通しについて遠慮なく質問し、分からない医療用語があればその場で確認しましょう。
もし延命治療などについて生前に本人の意思が確認できていれば、その希望を伝えることが、家族が判断を下す上での大きな助けとなります。
また、看取り後には退院手続きや入院費の精算が必要になりますが、その流れや支払い方法についても、医療スタッフに確認しておくとスムーズです。
退院時には、入院中お世話になった医師や看護師、病院スタッフへ、感謝の意を伝えることも忘れてはいけません。
冷静さを保つための心構えと支え方
大切な家族の危篤という事態に直面すれば、誰もが強い不安や動揺を感じるものです。
まずは深呼吸を意識的に行い、呼吸を整えることで、心の混乱を鎮める努力をしましょう。
危篤状態からすぐに亡くなるわけではないこと、小康状態に移行したり、まれに回復したりする可能性もあることを理解しておくと、落ち着きを取り戻しやすくなります。
この時期は、看病する側の精神的、肉体的な負担も非常に大きくなるため、「自分がしっかりしなければ」と一人で全てを抱え込もうとしないことが大切です。
家族や親族間で交代で付き添う体制を整えたり、友人や専門家(葬儀社など)に不安を相談したりするなど、周囲の協力を積極的に求めましょう。
危篤と言われたら葬儀準備も同時進行で考える
危篤と言われた時は万が一のことも考え葬儀社に相談をしておくことをおすすめします。
葬儀社に事前相談をするメリット、葬儀の形式で話し合うポイント、事前確認すべき書類などについても解説していきます。
- 葬儀社に早めに相談するメリット
- 葬儀の形式や費用を家族で話し合うポイント
- 事前に確認しておきたい書類や証明書一覧
葬儀社に早めに相談するメリット
危篤状態にある時に葬儀のことを考えるのは不謹慎だと感じるかもしれませんが、万が一の事態に備えて行動することは、後に残される家族の負担を軽減し、後悔を防ぐことにつながります。
危篤の連絡後、ご逝去となれば、ご遺体は病院の霊安室に長くは安置できません。
そのため、すぐに搬送と安置の手配が必要になりますが、事前に葬儀社の目星をつけておくことで、この流れを迅速かつ円滑に進めることができます。
また、複数の葬儀社から見積もりを取り、サービスや費用を比較検討する余裕が生まれるため、後で「費用に納得できなかった」「希望と違った」といった後悔を避けることができます。
信頼できる葬儀社は、その後の煩雑な手続きや葬儀の準備について、専門的なアドバイスとサポートを提供してくれるため、家族は精神的なゆとりを持って故人との時間に集中できるでしょう。
葬儀の形式や費用を家族で話し合うポイント
危篤の段階でご家族が集まっている時間は、葬儀の方針について話し合う貴重な機会です。
もしご本人がエンディングノートなどで葬儀の希望を残していれば、それを最大限尊重しつつ、家族間で喪主は誰が務めるか、葬儀の形式(家族葬、一日葬、一般葬など)をどうするか、参列者の範囲をどこまでにするかといった主要な事項を決定しておきましょう。
また、菩提寺の有無を確認し、万が一の際には僧侶に連絡をしてお務めを依頼できるかどうかも、事前に確認しておくべき重要なポイントです。
費用面についても、希望する葬儀の形式に基づいた大まかな予算を決め、複数の葬儀社の料金プランやサービス内容を見積もりで比較検討することが大切です。
事前に確認しておきたい書類や証明書一覧
ご逝去後は、入院費の精算や葬儀費用の支払いなど、すぐにまとまった現金が必要になる場面が多く発生します。
特に、宗教者へのお布施は葬儀当日に現金で渡すことが多いです。
さらに、故人の銀行口座は死亡の事実が確認されると凍結され、原則として引き出しができなくなるため、医療費や葬儀費用に充てるための現金を、危篤状態の間に準備しておくことが推奨されます。
また、亡くなった後に医師から発行される死亡診断書(死亡届と一体)は、役所への提出が必要な重要な書類です。
生命保険の請求などで必要になる場合があるため、提出前に必ずコピーを取っておきましょう。
その他、生前に本人が希望していた延命治療や臓器提供に関する意思も、医師とのコミュニケーションのために再確認しておくべきです。
危篤と言われたら起こりやすいトラブルと注意点
危篤と言われた時の起こりやすい親族間の意見の食い違いや病院や葬儀社との連絡ミスを防ぐ方法、精神的負担を軽減するサポートについてご紹介。
- 親族間の意見の食い違いへの対処法
- 病院や葬儀社との連絡ミスを防ぐ方法
- 精神的負担を軽減するサポート窓口
親族間の意見の食い違いへの対処法
危篤や臨終前後は、家族全員が精神的に不安定な状態にあるため、医療方針や葬儀の進め方、看病の分担などで親族間で意見が衝突しやすい時期です。
特に、延命治療の選択など重要な決断は、生前の本人の意向を最優先に考え、医療スタッフを交えて冷静に話し合いましょう。
また、看病や葬儀の準備は一人が抱え込まず、親族間で役割を分担して責任の所在を明確にすることが、軋轢を防ぐことにつながります。
金銭面では、危篤者の口座から費用を引き出した場合、その使途と金額を明確に記録し、親族間で共有することで、将来の相続トラブルを未然に回避することができます。
病院や葬儀社との連絡ミスを防ぐ方法
緊急時に冷静さを失うと、連絡すべき情報の抜け漏れや誤った伝達が発生しやすくなります。
病院から危篤の連絡を受けた際は、病状、病院の所在地、面会情報といった重要な点をその場で必ずメモに取るようにしましょう。
親族や関係者に連絡をするときは、自身の氏名や危篤者の容体、病院情報を簡潔かつ正確に伝えるリストを事前に用意しておくと、混乱を避けられます。
職場への報告についても、感情的にならず、必要な休暇期間や業務の調整事項など、必要最低限の情報を冷静な口調で報告することを心がけましょう。
また、電話が繋がらない相手には、メールなどで一報を入れた後、時間を改めて必ず電話で再確認を取ることが、連絡ミスを防ぐ確実な方法です。
精神的負担を軽減するサポート窓口
大切な人の命の危機に直面し、精神的な苦痛を抱えるのは当然のことです。
このような状況で無理をして体調を崩してしまっては、最期の看取りにも影響が出かねません。
不安や焦燥感を感じたときには、深呼吸をするなどして、まずは自分の心をコントロールするよう努めましょう。
そして、看病や葬儀の手続きに関する重い責任を一人で背負おうとせず、家族や親族、親しい友人に率直に気持ちを話し、協力を求めることが重要です。
また、葬儀社は単に葬儀を行うだけでなく、ご逝去後の煩雑な手続き全般について相談に乗ってくれる専門家です。
葬儀社を早めに検討し、不安な点を相談することで、精神的な負担を大きく軽減することができます。
危篤と言われた際のよくある質問
危篤と言われた際のよくある質問についていくつかご紹介していきます。
危篤の連絡を受けたらすぐに行くべき?
危篤の連絡は、文字通り「命の危険が差し迫っている」状態を意味しており、一刻も早く病院へ駆けつけることが最も優先されるべき行動です。
危篤状態は、数時間で急変する可能性も十分にあり得るため、大切な方との最期の時間をともに過ごす機会を逃さないよう、後悔を残さない行動が求められます。
深夜や早朝であっても、病院からの呼び出しや近親者への連絡は遠慮する必要はありません。
ただし、焦るあまり運転で事故を起こすことがないよう、冷静になり、安全を確保した上で移動しましょう。
病院へ向かう際の服装は、お見舞いマナーとして喪服を避けた地味な平服が望ましいです。
危篤から亡くなるまでどのくらいの期間が多い?
危篤から臨終までの期間は、その人の病状、体力、年齢、受けている医療措置などによって大きく異なり、医師であっても正確に予測することはできません。
一般的には、危篤状態を告げられてから数時間から半日、長くても二、三日以内に亡くなるケースが多いとされています。
しかし、中には患者の生命力や医療的なサポートにより、数週間や数ヶ月にわたって危篤状態が続くこともあります。
また、一時的に容体が安定する「小康状態」に転じることもありますが、根本的に回復の見込みは低いため、油断はできません。
いずれにせよ、最期の時が近いという現実を受け止め、心の準備をしながら本人に寄り添うことが大切です。
危篤時に葬儀社へ連絡しても問題ない?
身内が危篤の段階で葬儀社に連絡することは、全く問題ありませんし、むしろ強く推奨されます。
ご逝去後は、ご遺体の搬送や安置場所の確保を短時間で行う必要があり、冷静に判断する時間的・精神的な余裕がほとんどありません。
事前に葬儀社に相談し、費用や葬儀の形式について検討しておくことで、万が一の事態にも慌てず対応でき、後悔のないお別れを実現するための土台が作れます。
また、葬儀社はご遺族の不安や疑問に対し、専門的な知見から具体的なサポートを提供してくれるため、心の負担を軽減する効果もあります。
記事全体のまとめ
家族が危篤状態にあると告げられたら、それは回復が極めて困難で、大切な人との別れの時が差し迫っていることを意味します。
まずは深呼吸をして心を落ち着かせ、病院の場所や面会制限などの情報を正確に把握し、宿泊の準備を整えて迅速に病院へ向かうことが最優先です。
親族や関係者へは、時間帯を問わず電話で速やかに連絡し、情報を正確に伝えるよう努めましょう。
危篤から臨終までの時間は予測不可能ですが、最期の瞬間には、本人のそばに寄り添い、「ありがとう」といった感謝や愛情の言葉を伝えることを何よりも大切にしてください。
また、臨終後の慌ただしさに備え、危篤の段階から葬儀社を検討し、葬儀の形式や費用の相談、そして入院費や葬儀費用のための現金を準備しておくことが、後悔を避けるための賢明な対処法となります。
この困難な時期を乗り越えるために、すべての重荷を一人で背負おうとせず、周囲の協力や専門家の支援を頼ることが、心の平穏を保つ鍵となるでしょう。