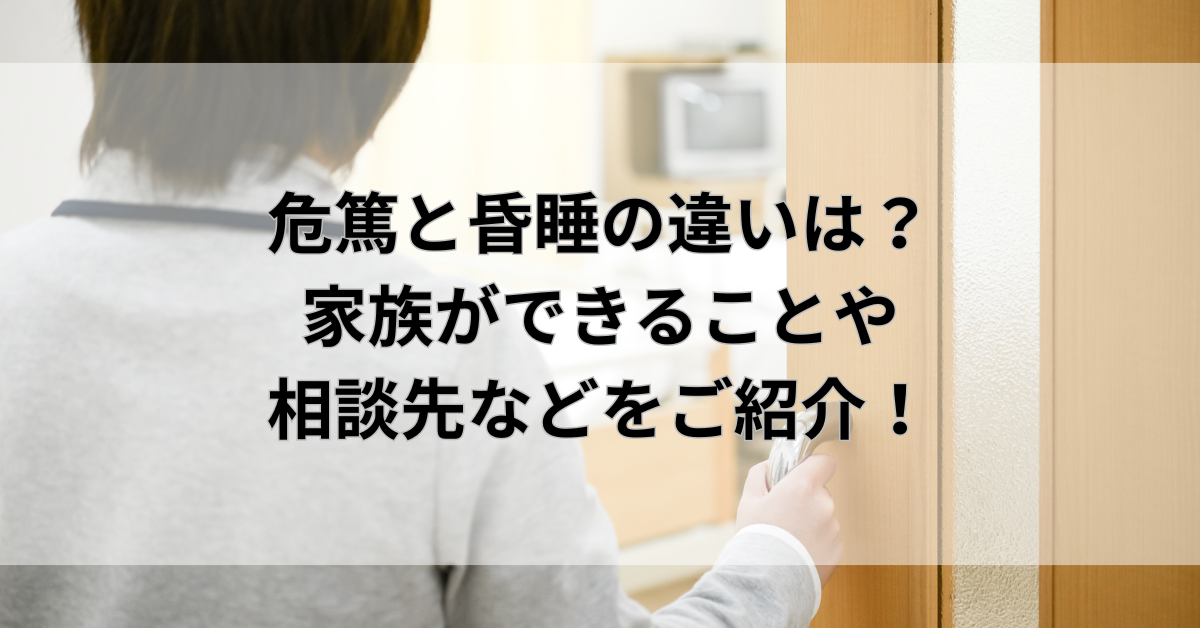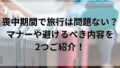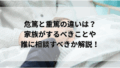「危篤」と「昏睡」は、どちらも命にかかわる状態ですが、どう違うのかは意外と知られていません。
家族がそのような状態になったとき、混乱せずに正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、危篤と昏睡の違いや見分け方、そしていざというときに家族がどこに相談すればよいのかを、わかりやすく解説します。
不安な気持ちに寄り添いながら、今できることを考えるきっかけにしてください。
危篤と昏睡はどう違うの?
危篤は生命の危機に焦点が当てられていますが、昏睡は必ずしも生命の危機が差し迫っていることではない点が違う所です。
言葉の意味や使われ方の違い
「危篤(きとく)」と「昏睡(こんすい)」は、どちらも命の危険が迫っている状況で使われる言葉ですが、その意味合いには重要な違いがあります。
まず危篤とは、病気や怪我の症状が非常に重く、回復の見込みがほとんどなく、いつ命を落としてもおかしくない、危険な状態を指します。
この言葉の「篤」という漢字には「病気が重い」という意味が含まれています。
一方「昏睡」は、意識が完全に失われ、強い刺激を与えても目覚めない状態を指す言葉です。
この二つの言葉の最も重要な違いは「意識」にあります。
「昏睡」は意識が完全にない状態を表しますが、「危篤」は意識がある場合とない場合の両方が含まれます。
また、「危篤」は生命の危機に焦点が当てられていますが、「昏睡」は必ずしも生命の危機が差し迫っている状態だけを指すわけではありません。
危篤や昏睡の違いだけでなく家族ができることや心の準備
危篤や昏睡の違いだけでなく家族ができる事として、病院へ向かう準備や慌てずに冷静になり万が一のことも考えること、親しい方や職場に連絡することも忘れないようにしましょう。
危篤のときにまずするべきこと
ご家族が危篤状態であると連絡を受けた際、まずは慌てずに落ち着くことが何よりも大切です。
気が動転して冷静な判断が難しくなるのは自然なことですが、深呼吸をするなどして気持ちを落ち着かせましょう。
落ち着いたら、すぐに病院へ向かう準備をします。宿泊になる可能性も考えて、以下のものを用意しておくと安心です。
- 携帯電話と充電器
- お財布
- 親戚や友人の連絡先がわかるもの
- 着替えや下着などの宿泊セット
- 常用している薬
また、万が一の事態に備えて、心の準備をしておくことも重要です。
すぐに亡くなるとは限りませんが、覚悟を持つことで、より冷静に対応できるでしょう。
病院に到着し、ご本人の状態を確認したら、次に親しい方々へ連絡を行います。
一般的には三親等までの親族に連絡するのが目安ですが、故人との関係性を重視し、特に親交の深かった友人などにも優先して知らせるべきです。
ご本人が意識のあるうちに、誰に会いたいか、誰に知らせてほしいかを確認しておくのが理想的です。
連絡は電話が最も確実な方法とされており、緊急を要するため深夜や早朝でも失礼にはあたりませんが、その際は一言お詫びを添えましょう。
また、数日間の休暇が必要になる可能性があるので、早めに上司に状況を伝え、業務の引き継ぎについて相談しましょう。
さらに、菩提寺や所属している宗教団体があれば、そちらにも連絡を入れておくと良いでしょう。
特にキリスト教などでは、危篤時に行われる儀式があるため、事前に神父や牧師に来てもらう必要があります。
昏睡のときに気をつけたい接し方
昏睡状態にある方への接し方で重要なのは、聴覚が人間の五感の中で最後まで残る可能性があるということです。
たとえ意識がないように見えても、ご本人の耳には周りの声が届いている可能性があるため、積極的に話しかけましょう.
話しかける際には、以下のような言葉を選ぶと良いでしょう。
適切な言葉
前向きで安心感のある言葉や楽しかった思い出を振り返る言葉、これまでの感謝を伝える言葉が適切です。
- 前向きで安心感のある言葉
- 楽しかった思い出を振り返る言葉
- これまでの感謝を伝える言葉
前向きで安心感のある言葉
死を連想させる表現は避け、愛と希望を感じさせる言葉を選びましょう。
楽しかった思い出を振り返る言葉
ご本人との思い出話をして、穏やかな気持ちになってもらいましょう。
これまでの感謝を伝える言葉
後悔のないよう、心からの感謝の気持ちを伝える最後の機会となるかもしれません。
不適切な言葉
一方で、避けるべき言葉や行動もあります。
- 死を連想させる言葉
- ネガティブな言葉
- 無理に励ます言葉
- 容態を詳しく尋ねる言葉
死を連想させる言葉
「ご愁傷様です」など、まだ亡くなっていない人に使うべきではない言葉や、忌み言葉(「枯れる」「散る」など)は避けましょう。
ご本人の前で、死後の手続きや葬儀に関する話題を出すのも控えましょう。
ネガティブな言葉
「もうダメかもしれない」といった否定的な言葉や、感情的に取り乱すことは避け、穏やかに接することが大切です。
無理に励ます言葉
「頑張って」「しっかりして」といった言葉は、ご本人や付き添っているご家族を追い詰める可能性があるため、避けましょう。
容態を詳しく尋ねる言葉
付き添っているご家族に、ご本人の容態を詳しく尋ねるのはマナー違反です。相手からの説明を待ちましょう。
また、ご本人が快適に過ごせるよう、周囲の環境を整え、身体を清潔に保つことも大切です。好きな音楽を流すなど、リラックスできるような工夫も良いでしょう。
今後のことを考えるときのポイント
ご本人が意識の疎通ができるうちに、今後のことについて話し合っておくことが非常に重要です。
これは、ご本人の意思を尊重し、後でご家族が後悔しないためにも役立ちます。
具体的には、延命治療の意思確認、遺言状の準備、葬儀の希望などの点について検討すると良いでしょう。
- 延命治療の意思確認
- 遺言状の準備
- 葬儀の希望
延命治療の意思確認
人工呼吸器や人工栄養、人工透析など、延命治療に関するご本人の希望を事前に確認し、「事前指示書」などの文書に残しておくことが望ましいです。
遺言状の準備
遺産の分配や生命保険の受取人などについて遺言書を作成しておくことで、ご家族間のトラブルを防ぎ、手続きをスムーズに進められます。
葬儀の希望
どのような形式(家族葬、一般葬など)、規模、参列者の範囲など、ご本人の希望を聞いておくことで、いざという時に慌てずに済み、ご本人の意向に沿った葬儀を行えます。
遺影やBGM、メモリアルコーナーなど、細かな要望も事前に相談できるでしょう。
また、危篤状態になると、今後の医療費や葬儀費用など、まとまったお金が必要になる可能性があります。
ご本人の銀行口座は、亡くなった後に凍結されて引き出しができなくなるため、事前に必要な現金を確保しておくことをおすすめします。
危篤や昏睡の場合はどこに相談すればいいのか
危篤や昏睡の場合の相談先として、病院以外の選択肢として葬儀社があります。
病院以外にも相談できる場所はあるの?
ご家族が危篤状態になった際、まずは病院の医師や看護師の指示に従うことが基本ですが、状況によっては病院以外にも相談できる場所があります。
自宅で危篤状態になった場合、最初に連絡すべきはかかりつけの主治医です。
主治医が不在の場合は、救急車を呼んで病院へ搬送することも考えられますが、事前に危篤時の対応について主治医と相談しておくことが推奨されます。
もし、健康な方が自宅で突然亡くなり、死因が不明な場合は、警察に連絡する必要があります。
この際、現場検証が行われるため、ご遺体を動かさないように注意しましょう。
葬儀の準備に関しては、葬儀社が専門的なサポートを提供しています。
なぜ葬儀社に依頼や相談をしておくと安心なのか
危篤の段階で葬儀社に相談しておくことは、精神的負担の軽減、迅速な対応、希望に沿った葬儀の実現、費用の比較検討、各種手続きのサポートなどができるため、安心です。
- 精神的負担の軽減
- 迅速な対応
- 希望に沿った葬儀の実現
- 費用の比較検討
- 各種手続きのサポート
精神的負担の軽減
大切な方を亡くした悲しみの中で、葬儀の手配を急いで行うのは非常に大きな負担となります。
事前に相談しておくことで、心と時間に余裕が生まれ、冷静に準備を進めることができます。
迅速な対応
病院の霊安室にご遺体を安置できる時間は限られているため、速やかに搬送先を決める必要があります。
事前に葬儀社を決めておけば、亡くなった際にすぐに搬送を依頼できます。
希望に沿った葬儀の実現
事前に打ち合わせをすることで、ご本人の希望やご家族の意向を反映した葬儀を計画しやすくなります。
費用の比較検討
複数の葬儀社から見積もりを取る「相見積もり」が可能になり、費用を抑えつつ、納得のいくサービスを選ぶことができます.病院から紹介される葬儀社は割高になる傾向があるため、注意が必要です。
各種手続きのサポート
死亡診断書の提出やその他作業など、死後に必要となる様々な手続きについても、葬儀社が代行してくれる場合が多く、ご家族の負担を軽減できます。
相談しておくと何が準備できるのか
葬儀社に事前に相談しておくことで、葬儀の形式や規模、ご遺体の搬送と安置場所の確保、詳細は葬儀内容の検討、費用面の準備などの具体的な準備を進めることができます。
- 葬儀の形式や規模の決定
- ご遺体の搬送と安置場所の確保
- 詳細な葬儀内容の検討
- 費用面の準備
葬儀の形式や規模の決定
家族葬、一日葬、火葬式など、希望する葬儀の形式や、参列者の人数に応じた規模を事前に決めておけます。
ご遺体の搬送と安置場所の確保
亡くなった後のご遺体を病院から自宅、または葬儀社の安置施設へ搬送する手配、および安置場所の確保について相談できます。搬送のみを依頼することも可能です。
詳細な葬儀内容の検討
遺影の写真、BGM、メモリアルコーナーの設置など、葬儀をよりパーソナルなものにするための細かな要望を事前に伝えておくことができます。
費用面の準備
葬儀にかかる費用の概算を知ることができ、それに備えて現金を確保する計画を立てられます。
危篤や昏睡に関するよくある不安や疑問
危篤や昏睡に関するよくある不安や疑問についてご紹介。
危篤でも元に戻ることはあるの?
危篤状態と告げられたからといって、必ずしもすぐに亡くなるわけではありません。
特に、脳梗塞などの急病や交通事故による怪我が原因の場合、集中的な治療によって回復する可能性があるとされています。
しかし、病気による衰弱や寿命が原因の危篤は、持ち直すことが難しい場合がほとんどです。
また、一時的に容態が回復したように見える「中治り現象」というものもありますが、これは死期が迫っているサインの一つであり、根本的な回復ではないことに注意が必要です。
昏睡ってどれくらい続くの?
昏睡状態の期間は、原因や個人の状態によって大きく異なります。
数時間で意識が戻ることもあれば、数週間、数ヶ月、あるいはそれ以上続くこともあります。
先生の話をどう聞けばいいの?
医師から危篤やそれに近い状態について説明を受ける際は、精神的に動揺してしまいがちですが、できる限り冷静に話を聞くことが重要です。
医師は、回復の見込みがないと判断した総合的な身体の状態を説明します。
延命治療に関する説明など、ご家族が重要な決断を迫られる場合もありますので、質問があれば遠慮せずに尋ね、理解を深めるようにしましょう。
また、ご本人が亡くなった際には、医師から「死亡診断書」が発行されます。
これはその後の各種手続きに必要となる非常に大切な書類なので、確実に受け取り、大切に保管してください。
記事全体のまとめ
「危篤」とは、病気や怪我で回復の見込みがほとんどなく、いつ命を落としてもおかしくない状態を指し、意識の有無は問いません。
一方、「昏睡」は意識が完全に失われ、外部からの刺激に反応しない状態を意味しますが、必ずしも生命の危機が差し迫っているわけではありません。
ご家族が危篤や昏睡状態になった場合、まずはご自身の気持ちを落ち着かせ、ご本人と過ごせる貴重な時間を大切にしましょう。
意識がなくても聴覚は残っている可能性があるため、感謝や思い出話など、前向きで安心感を与える言葉を優しく語りかけることが大切です。
危篤状態からの回復はまれなケースではありますが、可能性はゼロではありません。
医師の説明を冷静に聞き、疑問があれば尋ねるようにしましょう。
感謝のお葬式は危篤時のご相談や葬儀だけでなく遺品整理や相続、終活を安心の明朗会計で熟練スタッフが24時間365日対応しておりますので、ご相談お待ちしております。