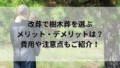改葬をする際に必ず納骨式が必要なことをご存知ですか?
改葬をする前の今現在のお墓に納骨をする際に納骨式を行ったと思いますが、改葬をする際には一度納骨を取り出しますので、納骨堂などに新たに埋葬をする際は納骨式が必要です。
改装後に海洋散骨などの納骨自体をしない場合は不要ですが、新たな納骨堂や樹木葬の個別型などにする予定の方は忘れずに菩提寺に依頼すべきです。
また、依頼をする際にはどのような事前準備が必要なのかも把握しておくと、必要な物を事前に準備することができミスを防止することができます。
そのため、本記事では改葬で納骨式をスムーズに行うためにどのような書類や事前準備が必要なのかご紹介しておきますので、ぜひ最後までご覧ください。
また、改葬や納骨式などに関する質問や相談についてはぜひ感謝のお葬式にお任せください!
些細なお悩みでも解決することができますので、ご連絡お待ちしております。
改葬で納骨式までに必要な書類と事前準備について
改葬で納骨堂までに必要な書類と事前準備について解説していきます。
改葬に必要な書類や事前準備について
改葬をする際には必要な書類がいくつかあり、忘れてしまうと改葬自体ができませんのでご注意ください。
必要な添付書類
改葬をする際には以下書類が必要です。
- 受入証明書
- 埋葬許可証
- 改葬許可証
受入証明書
受入証明証は「遺骨の受け入れることができます」という証明をすることができる書類です。
受け入れ先の墓地などの改葬先にお問い合わせをして発行してもらいましょう。
埋葬許可証
埋葬許可証は遺骨を埋葬するために必要な書類です。
現在埋葬されている墓地や霊園などにお問い合わせをして申請を行い、発行してもらいます。
改葬許可証
改葬許可証は改葬に必要な書類で、自治体に申請をして発行してもらいます。
改葬許可証の発行に「受入証明証」「埋葬許可証」がないと申請することができませんので、まずは2つを発行してもらい、その後改葬許可証の申請を行う流れです。
改葬や納骨式までに準備や手配すべき内容
書類以外にも以下のような物を事前に準備・手配しておきましょう。
- 閉眼供養の依頼
- 布施や供物な
- 必要であれば親族への連絡
- 改葬後の会食手配など
納骨式は遺骨を新たに埋葬をする際の儀式ですが、その前に現在のお墓などに埋葬されている遺骨を取り出す必要があり、その際には閉眼供養という納骨式とは別の儀式が必要です。
閉眼供養も僧侶に依頼をする必要がありますので、必ず事前に確認をして日程調節を行い、当日にはお布施を必ず忘れずに持参しておきましょう。
また、墓じまい・閉眼供養・納骨式などは依頼者だけでなく親族も参加することがありますので、日程は事前に共有しておくことをおすすめします。
改装後には会食をする場合がありますので、会食の人数の確認後事前に予約しておきましょう。
僧侶の方が会食を辞退した場合は御膳代としてお布施とは別に会食の代わりとして渡しますので、万が一のことも考え用意しておくと急遽不参加になった場合も安心です。
改葬と納骨式とは?意味と一般的な流れを解説
改葬と納骨式がそれぞれどのような意味なのか、混同しまうこともありますので意味を解説していきます。
改葬と納骨式の関係とは?
改葬とは、すでに埋葬されている遺骨を別の場所に移すことです。
納骨式は改葬後に新たな場所で遺骨を納める際の儀式です。
宗派や地域によって流れに違いはあるものの、どちらも故人を敬う大切な行事です。
改葬だけでなく納骨式も行うことで、移転先の墓所への敬意と感謝を伝えられます。
そのため、改葬はするけど納骨式はしない、ということは基本的にありませんので、改葬をする際は納骨式も行う前提で進めていきましょう。
納骨式はどんな場面で行われる?
納骨式は主に遺骨を新たに納める際に行われますので、改葬や新規の納骨の際はもちろん、永代供養の移行時にも行う場合があります。
僧侶による読経を依頼することが一般的で、家族や親族が立ち会います。
無宗教であっても簡単なセレモニーを通じて故人をしのぶ場になります。
改葬における納骨式のタイミング
改葬の手続きが完了したあと、移転先で納骨式を行います。
多くの場合、納骨堂や霊園の利用開始日に合わせて日程を組みます。
法要とあわせて納骨式を行うケースも多く、僧侶のスケジュール調整が必要ですので、タイミングを事前に相談しておくと準備がスムーズになります。
改葬で納骨式を滞りなく進めるための当日の流れ
改葬を行う際にいつ頃納骨式があるのか、どのぐらい時間がかかるのかを事前に把握しておくとスケジュールが立てやすいため、それぞれ解説していきます。
納骨式当日の所要時間とスケジュール
納骨式はおおよそ30分から1時間ほどで終了するケースが多いですが、準備や打ち合わせを行いますので集合時間の15分前には現地に到着しておきましょう。
読経、焼香、納骨という流れのあと、僧侶や親族にお礼の挨拶をして解散します。
会食を予定している場合は、移動時間や開始時間も含めてスケジュールを調整する必要があります。
終了後の流れとお礼の伝え方
納骨式終了後は、参列者に感謝の気持ちを伝えることが大切です。
特に遠方から来た親族や僧侶には、口頭だけでなく手紙やメールでも感謝を伝えると印象が良くなります。
お布施やお車代を渡すタイミングは読経終了後が基本です。
僧侶には「本日はありがとうございました」と一礼して手渡します。
改葬と納骨式でかかる費用と相場を知っておこう
改葬を行う場合は納骨式も必須のため、どちらの費用も把握しておくべきです。
お布施・読経料の一般的な相場
僧侶に読経を依頼する場合、納骨式にかかるお布施は3万〜5万円程度が一般的です。
加えて、お車代として5,000円〜1万円を別途用意するのがマナーです。
お布施は「御布施」と表書きし、無地の白封筒または仏事用ののし袋に入れます。
また、会食をしない場合は御膳代として渡しますので、辞退した場合は併せて忘れずに準備しておきましょう。
墓じまいや改葬の費用
改葬をする際に、まず現在のお墓から遺骨を取り出すための作業と費用が発生、その後改葬として費用が新たに発生します。
改葬元の費用だけでもおおよそ50万~100万、改葬先の費用としても50万以上費用が発生することが多く、合計すると安くても100万円以上の場合がほとんどです。
親族の交通費・会食費などの実費も考慮
納骨式には家族や親族の参加が見込まれます。
その際の交通費や会食費は施主が負担することが多いため、事前に予算を立てておきましょう。
参加人数によっては合計数万円〜10万円以上になるケースもあります。
式後の会食を行う場合は、予約時に人数と料理内容を決めておくとスムーズです。
改葬で納骨式における服装マナーと親族対応の注意点
改葬で納骨式における服装のマナーや親族などの対応の注意点について解説していきます。
喪服か平服か?服装選びの基本
納骨式における服装は、遺族であれば喪服が基本とされていますが、改葬の納骨式では、平服での参加を希望する家族も増えています。
案内状や事前連絡で「平服でお越しください」と記載されている場合は、地味な色味のスーツなどでも問題ありません。
迷った際は黒・紺・グレーなど控えめな色を選び、アクセサリーも光沢を避けると良いでしょう。
親族への案内や挨拶のマナー
納骨式への参加をお願いする場合は、早めに案内の連絡を入れることが望ましいです。
電話や手紙で日時・場所・服装の案内を丁寧に伝えましょう。
また、当日は施主として親族一人ひとりに挨拶することが大切です。
「本日はお忙しいところ、ありがとうございます」といった感謝の言葉を忘れないようにしましょう。
納骨式に招く範囲と伝え方
納骨式に招く範囲は、故人と関係の深い親族が中心になります。
改葬の場合は、現在の墓地にゆかりのある親族にも声をかけると丁寧です。
遠方からの参加となる場合、交通費の配慮も検討しましょう。
案内状には日時・場所・アクセス・連絡先を明記し、返事の期日も添えるとスムーズです。
記事全体のまとめ
本記事では改葬で納骨式をスムーズに行うためにどのような書類や事前準備が必要なのか、マナーや注意点についても解説していきました。
特にはじめての改葬では細かな不安などがあると思いますので、ぜひ改葬や納骨式について少しでもお悩みがありましたら、感謝のお葬式にお任せください。