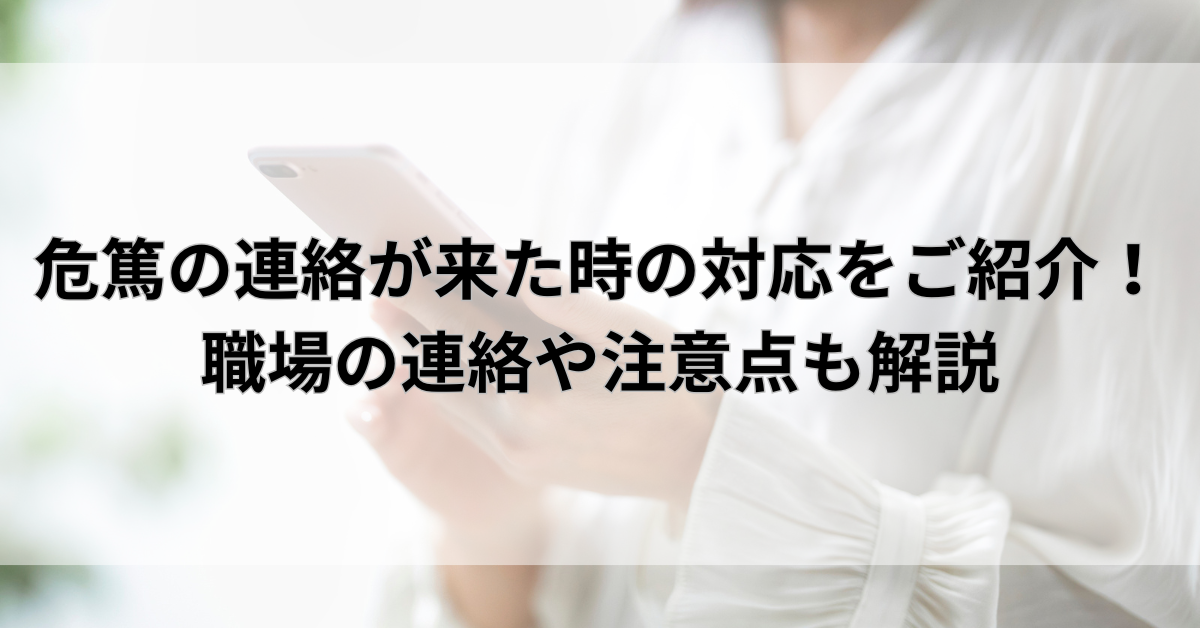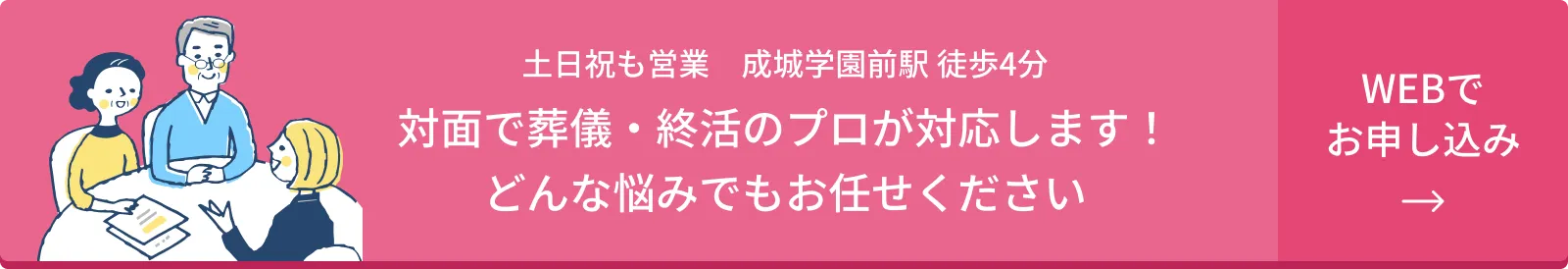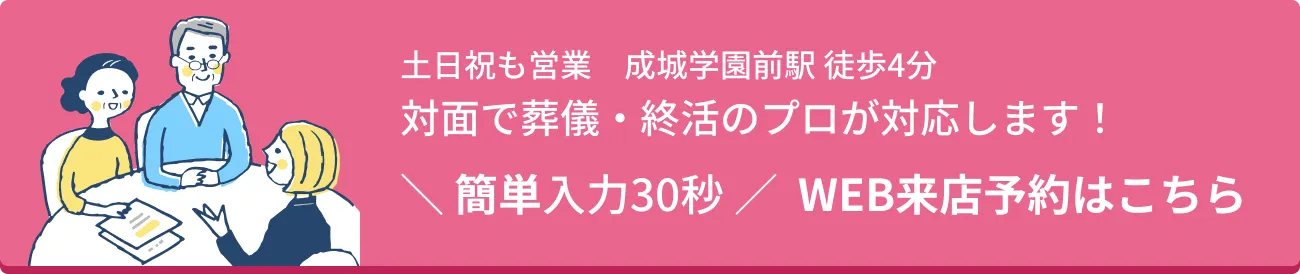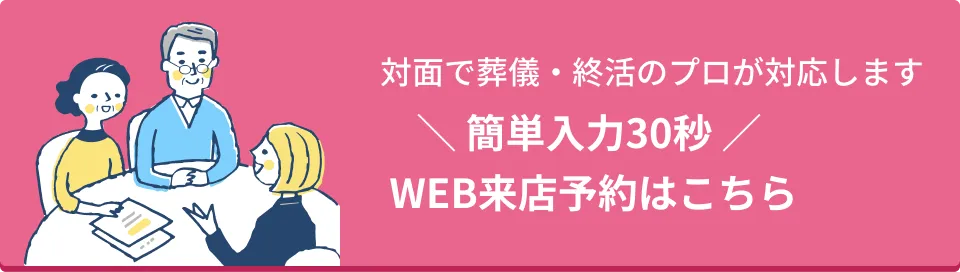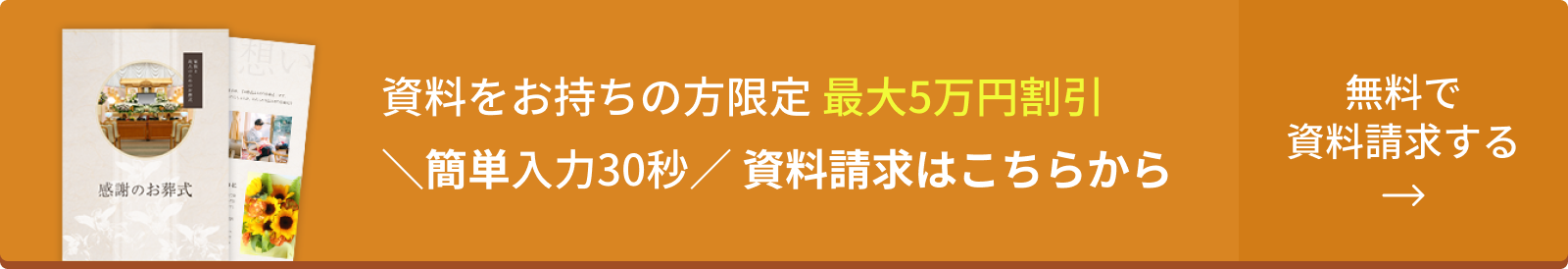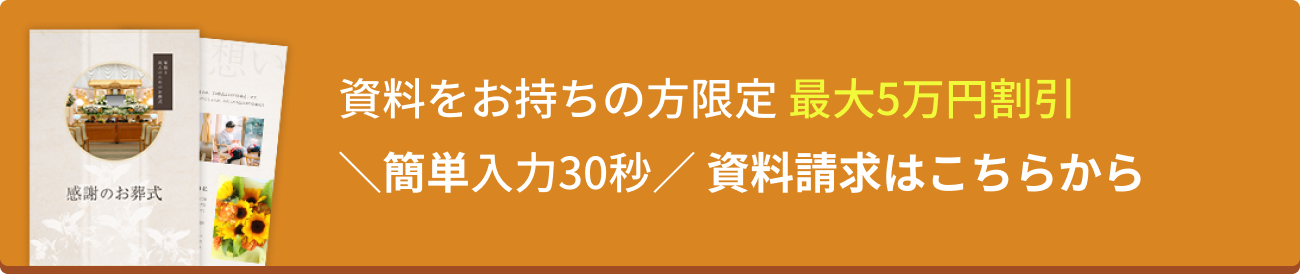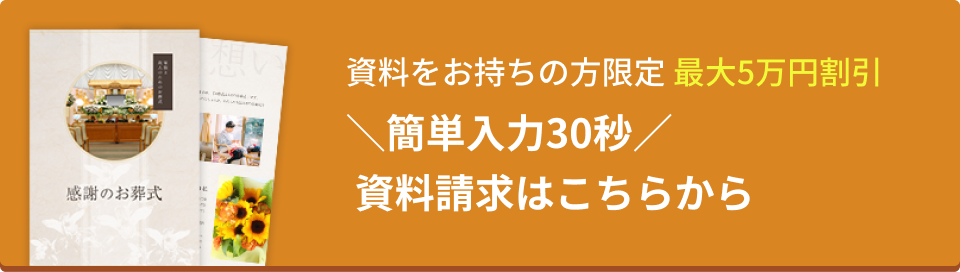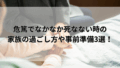ある日突然、病院から「危篤です」と連絡が入ると頭が真っ白になり、何をすべきか分からず戸惑う方が多いのではないでしょうか。
仕事や家族、親族、そして今後の準備。
冷静な対応が求められる一方で、精神的な動揺も避けられません。
本記事では、そんな非常事態に直面したときの「最初の行動」から、「職場や親族への連絡方法」、さらに「葬儀社への事前相談」まで、具体的な流れと文例を交えて分かりやすく解説します。
これらの対応をあらかじめ知っておくことで、慌てず正しく行動できるだけでなく、周囲からの信頼も保つことができます。
特に、時間帯別の対応やよくある疑問へのQ&Aもカバーしており、実用的な場面で活かせる情報を網羅しています。
この記事を読むことで、危篤の連絡を受けた際に「自分が何をすべきか」を明確に理解でき、心構えとともに具体的な準備が整えられるようになります。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。
危篤の連絡を受けた時の対応について
危篤の連絡を受けた時の対応については、まず緊急事態ではありますが冷静さを保ち、病院に向かう準備と親しい方への連絡をする必要があります。
また、危篤とは実際にどのような状況であるか、移動をする際のポイントについてもご紹介。
まず確認や対応すべき3つのこと
家族が危篤状態になったという連絡を受けた際、まずは冷静さを保つことが最も重要です。
気が動転していると、冷静な判断ができず、必要な準備を忘れたり、思わぬミスやトラブルにつながる可能性があります。
深呼吸をするなどして、一度心を落ち着かせましょう。
次に、病院へ向かう準備を速やかに行います。
場合によっては病院に泊まり込む可能性も考慮し、宿泊に必要な物品を準備しておくと安心です。
具体的には、着替え、普段飲んでいる薬、スマホや充電器、財布、親族や友人の連絡先を記載したメモなどを用意すると良いでしょう。
最後に、親しい方々へ連絡を開始します。
直接来院してほしい方には、病院名や病室の情報、自身の連絡先を正確に伝えます。混乱を避けるため、落ち着いた口調で連絡するよう心がけましょう。
- 深呼吸を行い冷静さを保つ
- 病院に向かう準備
- 親しい方々へ連絡
危篤とはどのような状況か
「危篤(きとく)」とは、医師による治療が行われても回復の見込みが極めて低く、生命の維持が非常に危険な状態を指します。
これは、主に病気や外傷によって意識が戻らず、呼吸や心拍などの生命活動が著しく低下している状態です。
類似した言葉に「重篤(じゅうとく)」がありますが、これは病状が非常に重いものの、直ちに命を落とす可能性が危篤ほど高くはない状態を意味します。
危篤の方がより差し迫った命の危険がある状態であると言えます。
危篤状態では、意識の喪失、浅く不規則な呼吸、顔色や唇の血色の悪さ、手足の冷たさなどが身体に現れることがあります。
また、呼びかけや刺激への反応が鈍くなることが一般的で、脈拍が弱まり血圧も徐々に低下します。
医師から「今夜が峠」といった説明がある場合は、最期が近いことを示唆していることが多く、迅速な行動が求められます。
ただし、危篤と診断されても必ずしもそのまま命を落とすとは限りません。
一時的に容体が安定して「小康状態」に転じたり、中には回復して通常の生活に戻るケースも存在します。
しかし、回復の可能性は低いと認識し、残された時間を大切に過ごす心構えが重要です。
移動・交通手段の確保のポイント
危篤の連絡を受けたら、速やかに病院へ向かうことが求められます。
夜間や急な呼び出しがあった場合に備えて、ご自身では運転は避けてタクシーなどの交通手段を事前に確認しておくと安心です。
移動中は焦らず、安全を最優先に行動することが大切です。
危篤の連絡を受けた時に葬儀社へ相談すべき理由
危篤の連絡を受けた時には、葬儀社に連絡をして置くと万が一の事態に備えて、残された家族の精神的・物理的負担を大きく軽減しますので相談することをおすすめします。
その他相談すべき内容とメリットについてご紹介。
- 危篤段階でも事前に葬儀社へ連絡すべきか?
- 相談しておくべき3つのこと(流れ・希望・費用)
- 事前相談のメリットと注意点
危篤段階でも事前に葬儀社へ連絡すべきか?
危篤段階であっても事前に葬儀社へ連絡し、相談しておくことは非常に賢明であり、決して不謹慎な行為ではありません。
多くの人が病院で亡くなる現代において、万が一の事態に備えて、事前に葬儀に関する準備をしておくことは、残された家族の精神的・物理的負担を大きく軽減します。
故人が病院で息を引き取った場合、ご遺体は病院の霊安室に一時的に安置されますが、その利用時間は通常限られており、速やかな搬送が求められます。
このため、冷静な判断が難しい状況の中で、急いで葬儀社を選び、搬送先を決めなければならない事態に陥ることが多々あります。
事前に葬儀社を選定し、相談しておくことで、このような混乱を避け、後悔のないお見送りのための準備を進めることができます。
回復を願う気持ちと同時に、「もしも」に備える心構えが大切です。
相談しておくべき3つのこと(流れ・希望・費用)
危篤段階で葬儀社に相談する際に、特に確認しておくべき重要な点は以下の3つです。
葬儀後の全体的な流れ
逝去後の手続きは多岐にわたり、限られた時間の中で多くのことをこなす必要があります。
葬儀社に相談することで、医師による死亡確認、死亡診断書の受け取り、役所への死亡届提出、火葬許可申請といった一連の流れや必要な手続きについて、具体的な説明を受けることができます。
これにより、万が一の際にも慌てずに対応できるでしょう。
希望する葬儀の形式と内容
葬儀の形式は、家族葬、一日葬、一般葬など多様です。
故人の意向や家族の希望に沿った葬儀を執り行うためには、事前にどのような形式で、どのくらいの規模で、どのような内容にしたいか(参列者の範囲、香典の有無、遺体の安置場所、故人の宗派など)を葬儀社と具体的に話し合っておくことが重要です。
葬儀にかかる費用
葬儀費用は葬儀の形式や規模によって大きく異なり、葬儀社が提示する料金プランも様々です。
事前に複数の葬儀社から見積もりを依頼し、費用相場を把握した上で比較検討することで、予算に合った適切なサービスを選べます。
また、葬儀費用の中には、宗教者へのお布施など、葬儀当日に現金で支払う必要があるものもあります。
故人が亡くなると、銀行口座は一時的に凍結され、そこからの引き出しができなくなるため、まとまった現金をあらかじめ手元に用意しておくことも大切です。
事前相談のメリットと注意点
事前相談のメリットと注意点についてご紹介。
メリット
事前相談の主なメリットは心理的負担の軽減、スムーズな手続き、費用面の明確化、後悔のない選択をすることができます。
心理的負担の軽減
不測の事態に直面しても、事前に情報を得て準備をしておくことで、精神的な動揺を抑え、冷静に対応できます。
スムーズな手続き
死亡後の複雑な手続きや搬送の手配を、葬儀社のサポートのもと、滞りなく進めることができます。
後悔のない選択
時間に追われることなく、複数の葬儀社を比較し、故人や家族の意向に最も合致する葬儀プランをじっくり選ぶことが可能になります。
費用面の明確化
事前に見積もりを取ることで、費用の総額や内訳を把握し、不明瞭な請求を避けることができます。
多くの葬儀社は24時間365日体制で無料相談を受け付けています。
注意点
注意点としては、費用だけでなく、スタッフの対応や相談のしやすさなど、人柄も含めて信頼できる葬儀社を選ぶと良いでしょう。
危篤の連絡を職場にする時の正しい伝え方
危篤の連絡を職場にする際には緊急性が高いため可能な限りは電話を利用しますが、早朝や深夜であればまずはメールをしましょう。
急な休みを取得する際のマナーやについてもご紹介。
上司・部下への伝え方(電話やメールなど)
家族が危篤状態になった場合、所属している職場への連絡も不可欠です。
迅速な連絡によって、上司や同僚が業務の引き継ぎや人員調整を速やかに行えるため、自分が安心して危篤者のもとへ駆けつけることができます。
連絡の基本は電話で直属の上司に直接伝えることです。
緊急性が高いため、可能な限り電話を利用しましょう。
ただし、早朝や深夜など、電話をかけるには失礼にあたる時間帯であれば、まずはメールで簡潔に状況を伝え、後ほど改めて電話で詳細を報告するのがマナーです。
メールやSNSは緊急時の連絡手段としては確実性が低いため、あくまで補助的な手段として使用し、必ず電話でのフォローアップを行いましょう。
もし勤務中に危篤の連絡を受けた場合は、電話ではなく、できる限り口頭で直接上司に伝えることが推奨されます。
その際は、まず病院へ駆けつけることを優先し、仕事の引き継ぎなどは後から電話で相談しても問題ありません。
急な休み取得のマナー
会社に危篤の連絡をする際は、必要最低限の内容を簡潔に伝えることが求められます。
具体的には、家族が危篤状態である旨と、それに伴いまとまった休暇が必要となる旨を伝えましょう。
病名や具体的な病状といった個人的な内容を細かく伝える必要はありません。
「最期の瞬間はそばにいたい」という思いを適宜表現することで、上司や同僚の理解を得やすくなるでしょう。
また、仕事の引き継ぎや不在期間中の対応については、初期連絡では軽く触れる程度にし、後ほど改めて詳細を相談するのが適切です。
家族が危篤状態になったことを理由に会社を休む場合、一般的には忌引き休暇は適用されません。
忌引き休暇は、家族が亡くなった後の葬儀の手配や参列のために利用されるものです。
そのため、危篤による休暇は、有給休暇として処理されるのが一般的です。有給休暇がない場合は、通常の欠勤扱いとなる可能性があります。
休暇が必要となる可能性がある場合は、身内が危篤になる前から上司や所属部署に状況を伝えておくことが、円滑な休暇取得につながります。
また、休暇が長引く場合は、できるだけ早く会社に連絡を入れ、上司と業務の進捗や今後のスケジュールについて相談することが大切です。
職場復帰の際には、休暇中に自分の業務をフォローしてくれた上司や同僚に対し、感謝の気持ちを伝えることが重要です。
可能であれば、菓子折りなどを持参すると、より誠意が伝わり、良好な人間関係を維持するのに役立ちます。
危篤の連絡を親族へ伝える際の注意点
危篤の連絡を親族へ伝える際には誰にどの順番で連絡すべきなのか、トラブルを防ぐための言葉遣いやタイミングなどの注意点があります。
- 誰にどの順番で連絡すべきか
- トラブルを防ぐ言葉遣いとタイミング
誰にどの順番で連絡すべきか
家族が危篤になった場合、最優先として同居している家族に連絡をしましょう。
その後、三親等までの親戚に連絡するのが一般的です。
三親等には、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹、祖父母、叔父・叔母、甥、姪、孫、曾祖父などが含まれます。
三親等以内の親戚であっても、普段から親交が少ない場合は、危篤の本人と特に親交が深かった友人を優先して連絡しても問題ありません。
血縁関係だけでなく、故人との日頃の交流頻度を考慮して判断することが推奨されます。
ただし病室に呼ぶ人数は最低限に抑えることをおすすめします。
トラブルを防ぐ言葉遣いとタイミング
危篤の連絡は緊急性が高いため、電話で直接伝えるのが基本です。
早朝や深夜であっても、緊急を要する連絡であるため失礼にはあたりません。
ただし、相手を気遣う一言を添えることが大切です。
例えば、「朝早くからすみません」「夜遅くの連絡で恐れ入ります」といった前置きをすることで、配慮が伝わります。
電話ではなるべく落ち着いた口調で、心を落ち着けて冷静に話すよう意識しましょう。
気が動転したまま連絡すると、相手をさらに驚かせる可能性があるためです。
伝える内容は、まず自身の氏名を名乗り、本人との関係性を説明した上で、危篤であることを明確に伝えます。
病院に来てほしい人には、入院先の病院名、病院の住所、病室の情報、そして自身の携帯番号を正確に伝えます。
電話がつながらない際はメールにて危篤を先に連絡しておきましょう。
ただし、メールは相手がすぐに気づかない可能性もあるため、時間をあけて電話することをおすすめします。
危篤状態の本人と接する際は、泣き叫ぶなど取り乱した態度を取らないよう気をつけましょう。
また、たとえ反応がなくても耳は聞こえている可能性があるため、本人の近くで亡くなった後の話をするのは避けるべきです。
後ろ向きな言葉ではなく、安心して最期を迎えられるような配慮が必要です。
危篤の連絡を受けたのが深夜や勤務中だった場合の対応
危篤の連絡を受けた際の時間帯に応じて適切な対応をする必要があります。
- 時間帯別の対応(早朝・深夜・日中)
- 夜間の連絡で気をつけるべき点
時間帯別の対応(早朝・深夜・日中)
危篤の連絡は、いつ、どのタイミングで届くか分かりません。時間帯に応じた適切な対応が求められます。
日中(勤務中)
勤務中に危篤の知らせを受けた場合、速やかに直属の上司に口頭で伝えるのが最も適切です。
急を要するため、まずは病院へ向かうことを優先し、仕事の引き継ぎなどは後ほど電話で相談しても構いません。
状況が落ち着き次第、改めて具体的な休暇日数や業務分担について連絡を入れましょう。
早朝・深夜
早朝や深夜に危篤の連絡を受けた場合、電話をかけるには相手に迷惑がかかる時間帯であるため、まずはメールで簡潔に状況を伝えるのが無難です。
メールの件名には「緊急」や「家族危篤」といった分かりやすい言葉を入れ、本文では状況と、翌朝改めて電話で連絡する旨を明記しましょう。
電話が繋がらない場合の補助的な手段としてもメールは有効です。
家族や親しい友人への連絡については、危篤という緊急事態であるため、早朝や深夜といった時間帯を気にせず電話で伝えるべきとされています。
ただし、冒頭で「夜遅くに申し訳ありません」など、時間帯への配慮を示す一言を添えることが重要です。
夜間の連絡で気をつけるべき点
夜間に会社へメールで連絡する際は、件名で緊急性を伝え、本文は簡潔にまとめることが重要です。
具体的な病状など個人的な詳細は省き、休暇の必要性と今後の連絡についてだけを伝えます。
また、翌朝改めて電話で詳細を伝えることを忘れずに記載しましょう。
これは、メールだけでは相手がすぐに確認できない可能性があるため、確実に情報を伝えるためのマナーです。
危篤の連絡に関するよくある質問
危篤の連絡に関するよくある質問をご紹介。
メールだけでの連絡はマナー違反?
危篤の連絡において、電話での直接連絡が最も基本的な方法であり、推奨されます。
これは、危篤が緊急性の高い状況であり、確実に情報を伝える必要があるためです。
ただし、深夜や早朝など、電話をかけるのが難しい時間帯や、相手が電話に出られない場合には、メールを一次的な連絡手段として利用することは許容されます。
その場合でも、必ず後で電話をかけて詳細を伝えたり、状況を確認したりするフォローアップがマナーです。
メールやSNSだけでの連絡は、相手がメッセージに気づかない、または緊急性が伝わりにくい可能性があるため、避けるべきだとされています。
特にSNSのグループチャットでの連絡は、失礼と感じる人もいるため、個別にメッセージを送る方が安心です。
どこまでの親族に知らせるべき?
危篤の連絡は、まず同居の家族に伝えるのが最優先です。
その後、三親等までの親族に連絡するのが一般的とされています。
三親等には、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹、祖父母、叔父・叔母、甥、姪、孫、曾祖父などが該当します。
しかし、血縁関係だけでなく、危篤の本人と特に親交が深かった友人や知人にも連絡するべきです。
たとえ三親等内の親戚であっても、普段から交流が少ない場合は、親しい友人を優先して連絡しても問題ありません。
病院の都合や他の患者への配慮から、一度に大人数が病室に集まらないよう、連絡する人数を最低限に抑えることも考慮が必要です。
疎遠な親戚については、後日死亡の連絡で十分な場合もありますが、連絡すべきか迷う場合は、後悔を残さないためにも一報を入れておく方が良いでしょう。
駆けつけられない場合はどうすべき?
危篤の連絡を受けたものの、遠方に住んでいる、仕事の都合がつけにくい、あるいは現在の状況(感染症対策など)によりすぐに駆けつけられない場合もあります。
もし自分がすぐに駆けつけられない立場であれば、まずは連絡をしてくれた相手に対し、心境を気遣う言葉を簡潔に伝えましょう。
相手も動揺している可能性が高いため、「大変な中でご連絡いただき、心から感謝しています」「どうかご自身もご自愛ください」といった気遣いの言葉が適切です。
仕事関係者からの連絡であれば、「こちらのことは心配しないでください。ご家族との大切な時間を過ごしてください」と、仕事のフォローを申し出る姿勢を見せることも重要です。
病院によっては、面会に関する制限がある場合もありますので、訪問前に確認することが推奨されます。
遠方の親族に対しては、必ずしも来院を促すのではなく、状況の報告として一報を入れるだけでも良いとされています。
無理に面会を強要せず、相手の状況と気持ちを尊重することが大切です。
記事全体のまとめ
家族が危篤状態になったという連絡は、誰にとっても大きな衝撃と動揺をもたらすものです。
しかし、このような緊急時こそ、冷静さを保ち、適切な対応を迅速に行うことが不可欠です。
危篤という状況は一人で乗り越えるには困難が伴います。
周囲の人々や専門業者と協力し、情報共有と役割分担を適切に行うことで、冷静に対応し、大切な人との最期の時間を心穏やかに過ごすことができるでしょう。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。