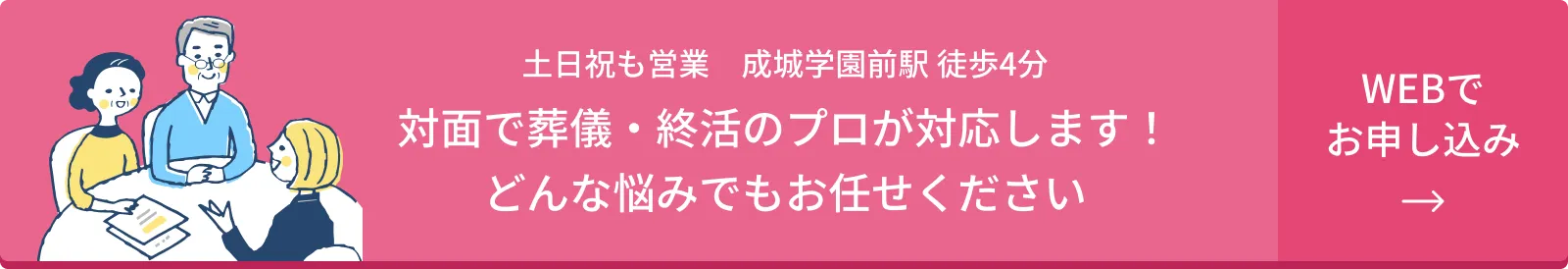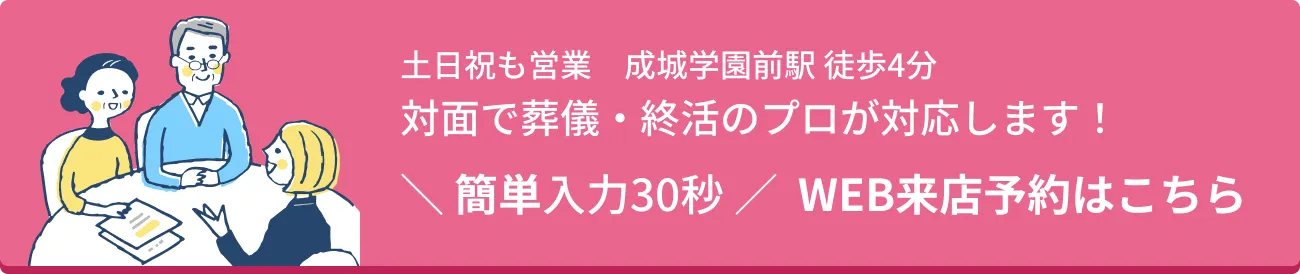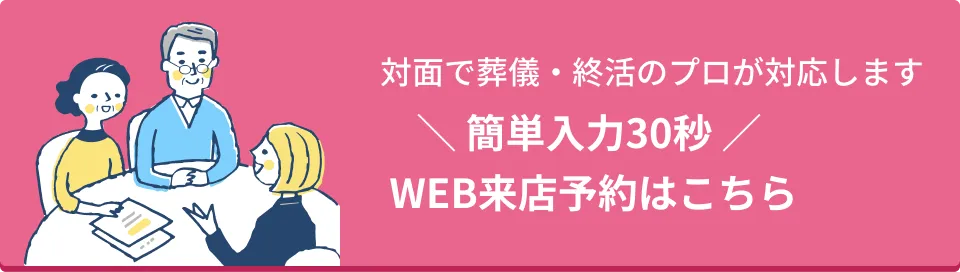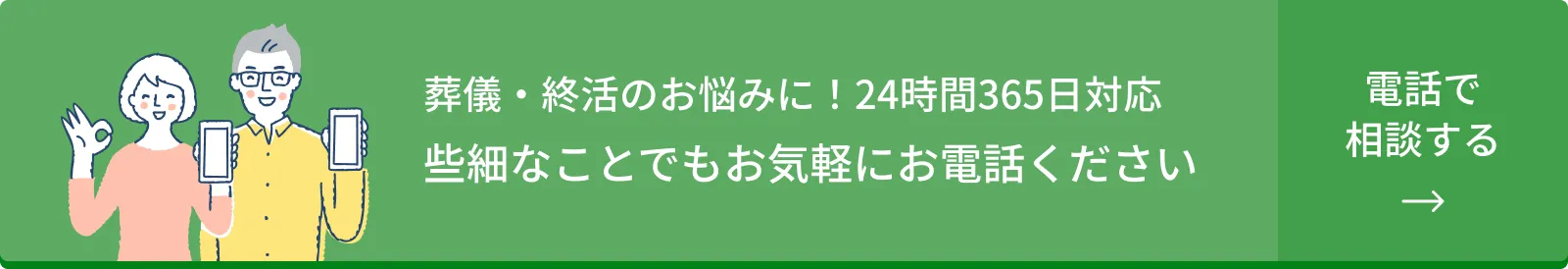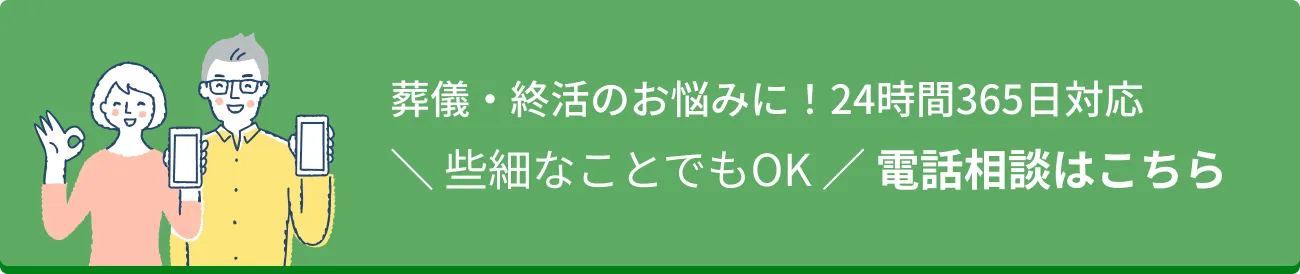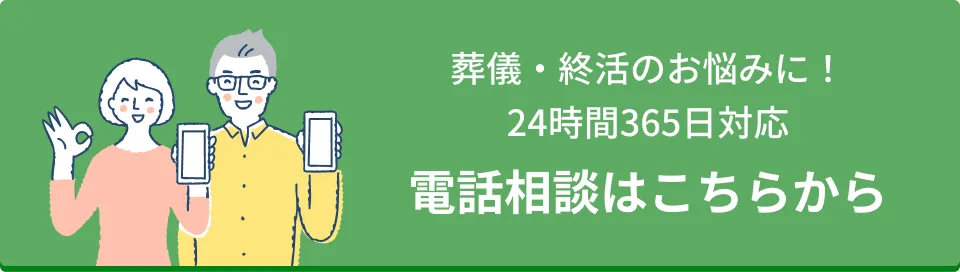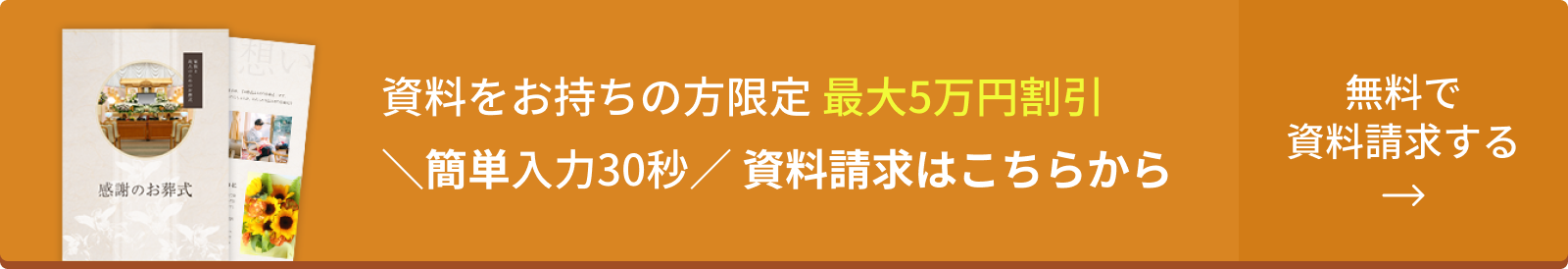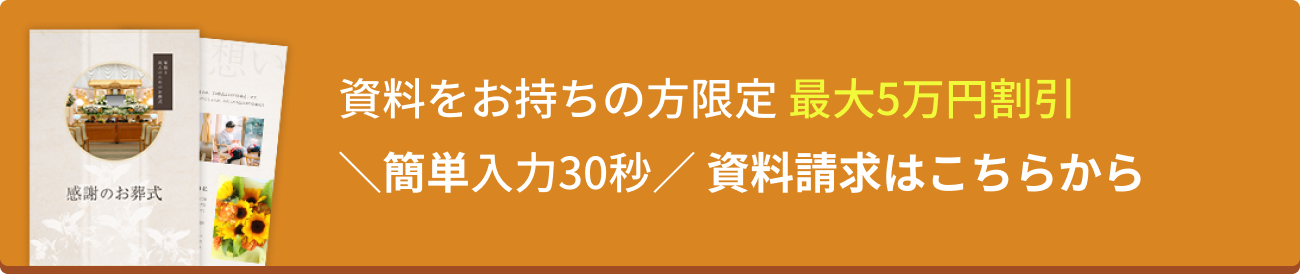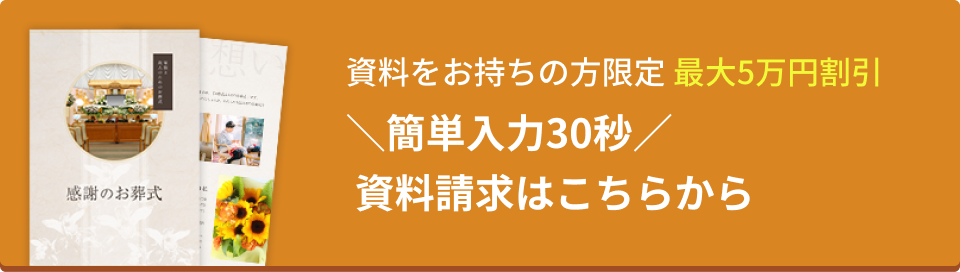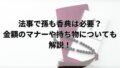・大学生の場合は喪服を着用して、小学生・中学生・高校生の場合は学校指定の制服があれば制服で問題ない。
・持ち物のマナーとして、ハンカチ・マスク・スマホについて解説
・葬儀では私語を慎み、不要な持ち物は持たないようにする
学生が葬儀に出席する際に、服装は社会人と同じ喪服ではなくてもいいのか不安になりませんか?
学生の場合、学校指定の制服があれば通常は制服を着用して登校するため、喪服などを持っていないことが多いと思います。
また、はじめて葬儀に出席する方も多いため、どのような持ち物が適切なのかも気になるかと思います。
そのため、下記のような葬儀の際に着用する服装や葬儀に参加する際に必要な持ち物などに気になっている方必見。
・どのような持ち物を準備すればいいか知りたい
本記事では、葬儀に学生はどのような服装が適切か、持ち物や注意事項も解説します。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。
葬儀に学生はどのような服装がいいのか
葬儀の場では、故人を偲び、ご遺族への配慮を示すため、参列者は礼儀にかなった服装を心がけることが大切です。
学生の場合も同様に、場にふさわしい装いが求められます。
大学生
大学生は制服がないため、原則として大人と同じ喪服を着用することが基本的なマナーとされています。
もし急な訃報で喪服が手元にない場合は、リクルートスーツやビジネススーツで代用することも許容されることがありますが、これはあくまで略式と理解し、濃い色の無地のものを選びましょう。
ストライプ柄や明るい色のスーツは避けるべきです。
男性の場合
男性の場合、喪服は光沢のない黒のブラックスーツが適しており、ワイシャツは白無地のレギュラーカラーを選びます。
ネクタイは光沢のない黒無地で、ディンプル(くぼみ)は作らないのがマナーです。
ベルトと靴下は黒無地、靴も黒の革靴で、エナメルや派手なデザインは避けます。
女性の場合
女性の場合、喪服は光沢のない生地のブラックスーツ、ワンピース、またはアンサンブルが基本です。
肌の露出は控えめにし、トップスの袖は五分袖から長袖、スカート丈は膝からふくらはぎ程度が適切とされます。
アクセサリーは真珠の一連ネックレスが一般的ですが、学生は無理に着用する必要はありません。
ストッキングは薄手の黒(30デニール以下)を選び、厚手や柄物は避けます。
靴は装飾のない黒のパンプスで、ヒールは5cm以下が望ましいです。
髪型は清潔感を保ち、長い髪は顔にかからないよう低い位置で一つにまとめるのがマナーです。
明るい髪色や派手なヘアアレンジは避け、必要であれば一時的に黒く染めるスプレーなどを使用することを検討しましょう。
メイクをする場合は、ツヤや色味を抑えた控えめな「片化粧」が適切です。
小学生・中学生・高校生
小学生、中学生、高校生は、学校の制服があれば、それが正式な礼装とみなされますので、制服を着用して参列して問題ありません。
制服の色が黒でなくても、またリボンやネクタイの色が明るめでも、それが学校指定のものであればマナー違反にはなりません。
制服を着用する際は、着崩さずに校則通りの正しい着こなしを心がけましょう。
制服がない場合は、黒、濃紺、濃いグレーなどのダークカラーを基調とした、シンプルで控えめな服装を選びます。
服装以外のマナー
靴は、男女ともに黒色のシンプルな革靴やローファーが望ましいですが、汚れのないシンプルなスニーカーも許容範囲とされています。
エナメルなど光沢のある素材や、派手なデザインの靴は避けてください。
靴下は、黒、白、濃紺、または濃いグレーの無地を選び、くるぶし丈やニーハイソックスはマナー違反とされます。
髪型は、清潔感があり、長い髪は低い位置で一つにまとめるなど、顔にかからないように整えます。
派手なヘアアクセサリーは避け、黒や茶色のシンプルなヘアゴムやヘアピンを使用しましょう。
また、中学生・高校生はメイクをする必要はありません。
季節に応じて、寒い時期には黒、濃紺、ダークグレーのコートやマフラーを着用できますが、ファー素材は避けて会場に入る前に脱ぎましょう。
夏場でもジャケットを着用するのが基本ですが、暑い場合は半袖シャツも許容されますが、できるだけ露出を控えるように配慮しましょう。
葬儀に学生が行く際の必要な持ち物
葬儀に学生が参列する際に、大人と同じく持参することが望ましい小物があります。
ハンカチ
ハンカチは、弔事専用の黒または白の無地のものが適切です。色物や柄物、華美なデザインのハンカチは避けるようにしましょう。
スマホ・携帯電話
スマートフォンは、葬儀の場では電源を切るか、マナーモード(音や振動もオフ)に設定することが非常に重要です。
時計代わりに使うこともマナー違反とされているため、あくまで緊急連絡用や、式中に触れないものとして持参し、バッグにしまっておくのが最も安心です。
葬儀に学生が行く際の不要な持ち物
葬儀は厳粛な場であるため、持参しない方がいい物も多くあります。
派手なアクセサリーや装飾品
結婚指輪や一連の真珠ネックレス以外は基本的に外し、学生はアクセサリー自体を身につける必要はありません。光る素材、大きいもの、連なっているものは避けます。
殺生を連想させる素材のアイテム
毛皮、フェイクファー、動物柄(クロコダイル、ヘビ柄など)の服や小物(バッグ、靴、コート、マフラー、ストール)はNGです。
カジュアルな素材の服
綿、麻、ニット、スウェット、デニム、ナイロンなど、カジュアルな印象を与える素材は避けるべきです。
明るい色や目立つ柄の服・小物
赤、黄色、オレンジなどの派手な色や、キャラクター柄、大きなフリルやスパンコールなどの装飾が施された服や小物は不適切です。
カジュアルな靴
サンダル、ミュール、過度に高いヒール、エナメル素材(光沢があるため)、ブーツ(大雪時を除く)、ローラー付きの靴、音の鳴る靴、蛍光色のスニーカーなどは避けましょう。
大きすぎるバッグや派手なバッグ
A4サイズのリクルートバッグ(女性)、大きなロゴや装飾、光沢のあるバッグは避けます。学生は基本的に、必要な最小限のものをポケットに入れるか、親が管理するなどの対応が望ましいとされます。
派手な髪飾り
リボンや大きなヘアピンなど、華美な印象を与える髪飾りは控えます。
濃いメイクやネイル
濃い色のアイシャドウ、口紅、ネイルは避け、ナチュラルな印象に留めます。
中高生はメイクをしない方がよいでしょう。
ネイルが落とせない場合は、ネイルシールを貼るか、黒い手袋を着用する方法もあります(焼香時は外す)。
くるぶし丈やニーハイソックス
靴下は足首が隠れる丈を選び、短い丈やニーハイソックスはマナー違反とされます。
ネクタイピン
男性はネクタイピンを付けません。
香水
きつい香りの香水は控えましょう。
葬儀に学生が行く際の注意点
葬儀に参列する学生は、服装だけでなく、振る舞いにも配慮が必要です。
- 私語は慎み適切な態度をとる
- スマホ・携帯電話をマナーモードにする
- 不用意な物をあまり持って行かない
私語は慎み適切な態度をとる
葬儀は故人とのお別れの場であり、静粛性が重んじられます。
式中は私語を慎み、静かに過ごすことが大切です。友人や親戚に会っても、会話は式が終わってから会場の外で行うようにしましょう。
焼香の作法は前の人に倣えば問題ありません。もし間違えても、真面目に取り組んでいれば失礼にはあたりません。
スマホ・携帯電話をマナーモードにする
携帯電話は、電源を切るか、音や振動が鳴らないよう完全にマナーモードに設定することが必須です。
着信音や通知音が式の静けさを乱すことは避けなければなりません。
一番安心なのは、電源をオフにしてバッグにしまうことです。
不用意な物をあまり持って行かない
葬儀の場では、必要最小限の持ち物にとどめるのが賢明です。
子どもがおもちゃやお菓子などを持参する場合も、音の出ないものを選び、他の参列者の迷惑にならないように配慮が必要です。
また、私物をなくしたり置き忘れたりしないよう、親が管理するか、ポケットに収まる程度のものにしましょう。
まとめ
葬儀に学生が参列する際は、故人を偲び、ご遺族に寄り添う気持ちを服装や態度で示すことが最も重要です。
制服がある学生は、それが正装として認められていますが、着崩さず清潔感を保つことが大切です。
大学生は大人と同様に喪服を着用するのが基本であり、急な場合のリクルートスーツ代用時も、それに合わせた小物や身だしなみへの配慮が必要です。
服装は、黒や濃紺、ダークグレーといった落ち着いた色味の無地のものが望ましく、光沢のある素材や派手な装飾、キャラクター柄、肌の露出が多いデザインは避けるべきです。
靴や靴下、髪型、バッグなどの小物についても、シンプルで地味なものを選び、清潔感を意識しましょう。
葬儀は長丁場になることがあり、特に小さなお子様の場合は、無理をさせないよう、体調管理を優先し、出入り口に近い席に座るなどの配慮も忘れてはなりません。
また、式中の私語や携帯電話の使用は厳禁であり、静かに故人を悼む姿勢が求められます。
喪服は普段着る機会が少ないため、いざという時に困らないよう、事前に準備しておくことも安心につながります。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。