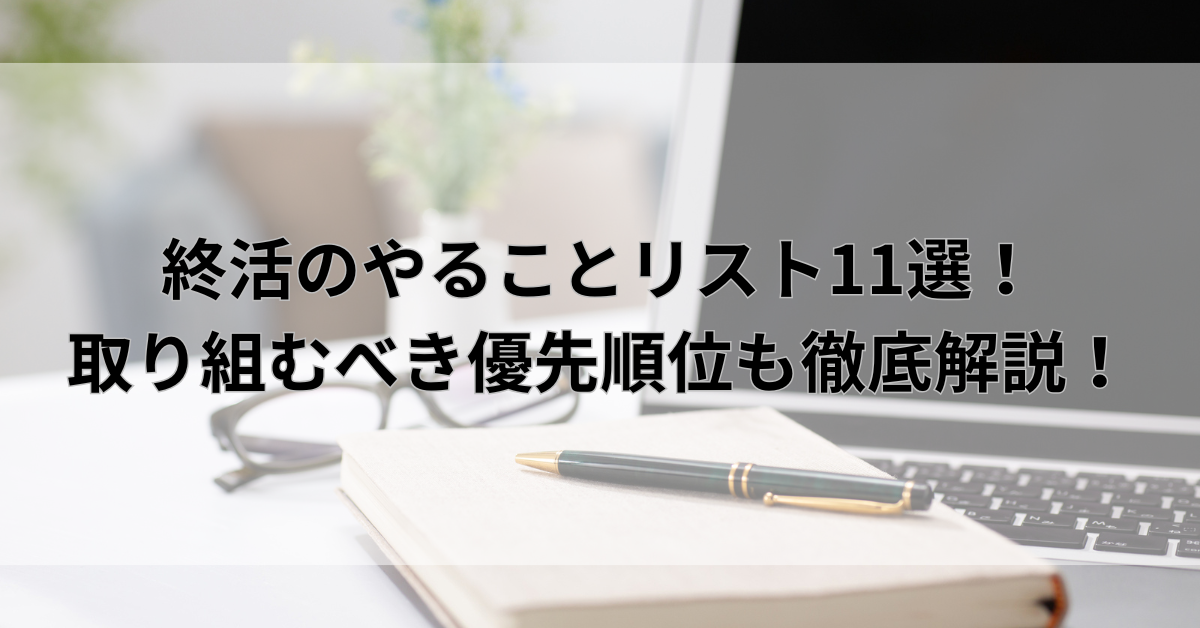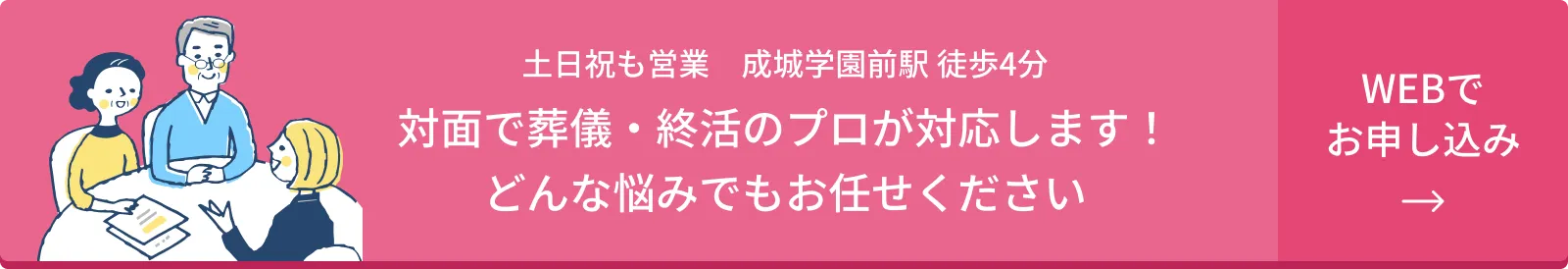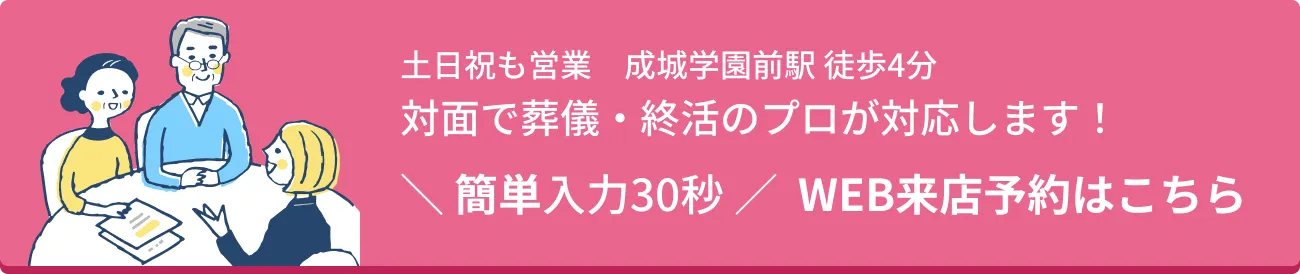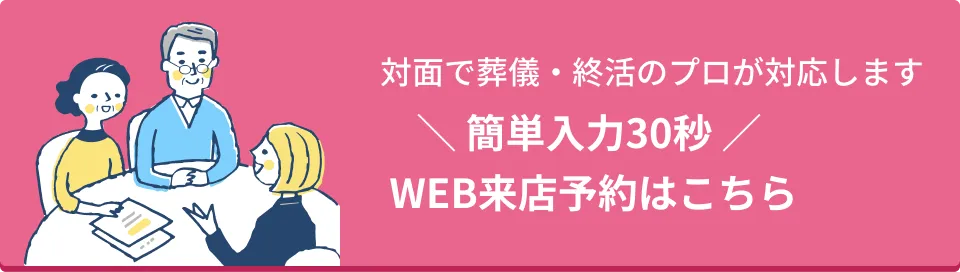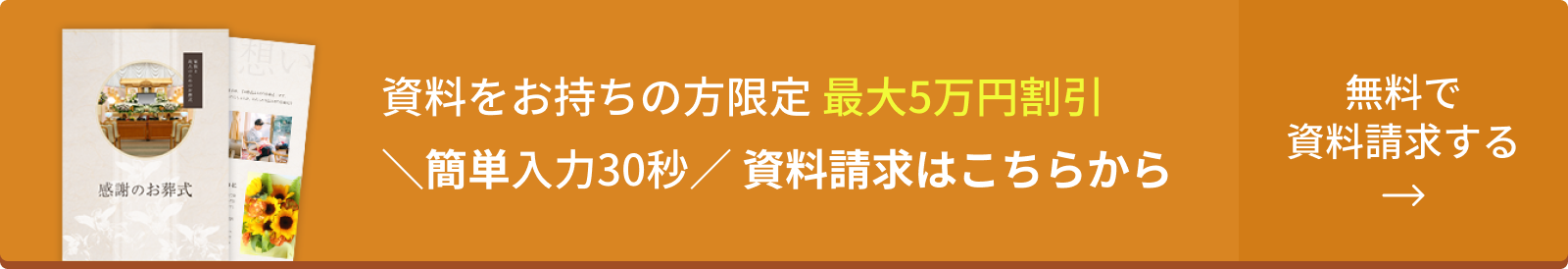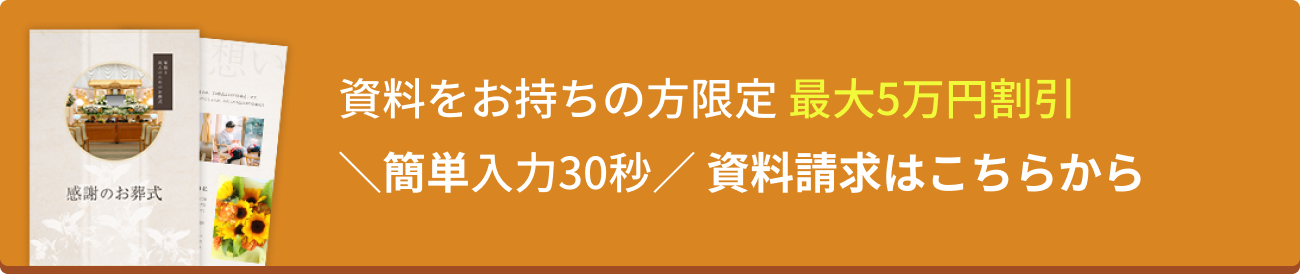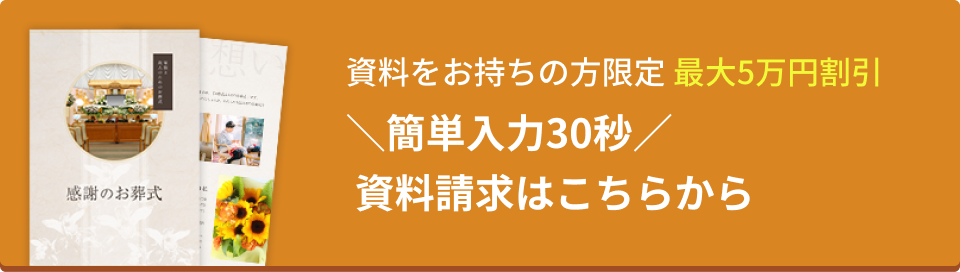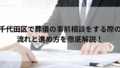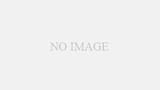終活を考えるとき「やることが多すぎて何から始めればよいのか分からない」と悩む方は少なくありません。
漠然とした不安を抱えたまま過ごすと、万一のとき家族に大きな負担を残してしまう可能性があります。
その解決策として有効なのが「やることリスト」を作成し、一つずつ整理していくことです。
終活リストを活用すれば、財産や葬儀だけでなく医療や人間関係まで、自分の意思を反映した準備が可能になります。
本記事では「終活やることリスト11選」として、必要な項目を網羅的に解説します。
相続や遺言、デジタル資産の整理など、見落としやすい内容も具体的に紹介します。
記事を最後まで読むことで、終活でやるべきことを体系的に把握でき、家族への安心と自分らしい人生の締めくくりに向けた行動を始められます。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。
終活でやることリストの基本
終活でやることリストの基本として、そもそもなぜやることリスト自体を作成する必要があるのか、リストに含める主な項目の全体像を把握しておくことが大切です。
- なぜやることリストが必要なのか
- リストに含める主な項目の全体像
なぜやることリストが必要なのか
終活は、人生の最終章を自分らしく充実させるための準備活動であり、単に「死への備え」という後ろ向きな意味合いだけではありません。
この活動を通じて、様々なメリットが得られるため、具体的な「やることリスト」の作成が推奨されます。
まず、終活は残される家族の負担を大きく軽減します。
もしもの時に、遺された人々が故人の意向を把握できず、財産整理、葬儀、お墓の手配などで多大な手間や精神的負担を強いられることを避けるためです。
特に、財産分与や相続について明確な意思表示がない場合、家族間でのトラブルや紛争につながるリスクも減らせます。
次に、終活は自分自身の不安を解消し、より前向きに生きるための機会を提供します。
自身の半生を振り返り、これからの人生で何をしたいか、どのような最期を迎えたいかを具体的に考えることで、漠然とした将来への不安が明確になり、その対策を立てることができます。
これにより、心穏やかに、充実した日々を送れるようになるでしょう。
リストに含める主な項目の全体像
終活で取り組むべきことは多岐にわたりますが、大きく分けて「旅立ちの準備」「残される家族のための準備」「残りの人生を充実させるための活動」という観点から項目を整理できます。
主な項目としては、自身の財産(預貯金、不動産、有価証券、債務など)の明確化と整理、それらに伴う遺言書の作成、保険や年金の現状把握と見直しが挙げられます。
また、将来の医療や介護に関する具体的な希望(延命治療の有無、介護場所など)を明確にすることも重要です。
さらに、葬儀やお墓に関する自身の意向を決定し、事前に準備を進めることもリストに含まれます。
身の回りの持ち物やデジタルデータの整理(断捨離やデジタル終活)も、遺族の負担を減らすために不可欠な要素です。
加えて、人間関係の整理や友人への連絡先リストの作成、ペットの世話に関する準備も考慮に入れるべきです。
そして、これらすべての情報をエンディングノートにまとめておくことが、終活をスムーズに進める上で非常に役立ちます。
最後に、老後の住まいや生活、今後の人生でやりたいことを具体的に計画することも、終活の重要な側面です。
終活でやることリスト11選
終活でやることリストを11選まとめましたので、ぜひご参考にしてください。
- 財産や預金の整理
- 相続に備える遺言書作成
- 保険や年金の確認
- 医療や介護の希望を伝える
- 延命治療や終末期医療の意思決定
- 葬儀のスタイルを選ぶ
- お墓や納骨方法の検討
- 持ち物や住まいの片付け
- デジタル資産(SNS・パスワード)の整理
- 家族や友人へのメッセージ作成
- エンディングノートの記入
財産や預金の整理
終活における財産整理は、所有しているすべての財産と負債を明確にすることから始まります。
具体的には、銀行口座(普通預金、定期預金など)の確認、クレジットカードの利用状況、有価証券(株式、投資信託、債券など)、不動産(自宅、土地、投資用物件)の有無を洗い出します。
特に、長期間使っていない口座や不要なクレジットカードは解約することで、死後の家族の解約手続きの負担を軽減できます。
また、不動産の評価額や名義、ローン状況なども把握し、必要であれば売却や名義変更を検討することも含まれます。
これらの情報を一覧にした財産目録を作成し、保管場所を家族に伝えておくことが推奨されます。
相続に備える遺言書作成
遺言書は、故人の財産を誰に、どのように分配したいかという明確な意思を法的に有効な形で示す書類です。
これにより、相続人による遺産分割の争いを未然に防ぎ、自身の希望通りの財産承継を実現できます。
遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、全文自筆や日付、署名・押印といった厳格な要件を満たさないと無効になるリスクがあります。
一方、公正証書遺言は、公証人が作成し、証人の立ち会いも必要となるため手間と費用はかかりますが、法的な確実性が高く、無効になる心配がほとんどありません。
相続人がいない場合や、NPO法人などの慈善団体に遺産を寄付したいと考えている場合にも、遺言書の作成が有効な手段となります。
遺言書は複数回書き直すことが可能で、常に最新のものが有効となるため、状況の変化に応じて見直すことが大切です。
保険や年金の確認
終活の一環として、現在加入している生命保険や医療保険の内容を見直し、今後の生活に合った保障があるかを確認することが重要です。
数十年前に契約した保険が、現在のライフスタイルや将来の医療ニーズに合致しているかを見極める必要があります。
不要な保障があれば解約や減額を検討し、必要な保障が不足している場合は追加加入も視野に入れます。
また、公的年金の受給額や受給開始時期を確認し、老後の生活資金として十分であるかをシミュレーションすることも大切です。
年金収入だけでは心許ないと感じる場合は、資産運用や私的年金の活用など、老後資金を補完する方法を検討しましょう。
医療や介護の希望を伝える
将来、病気や怪我、認知症などにより自分の意思を明確に伝えられなくなる事態に備え、どのような医療や介護を受けたいかという希望を事前に明確にしておくことが重要です。
具体的には、かかりつけ医や持病に関する情報、介護が必要になった際にどこで(自宅か施設か)誰に介護してほしいか、どのような介護サービスを希望するかなどを決めておきます。
これらの希望をエンディングノートに書き残すだけでなく、家族や信頼できる人と事前に話し合い、共有しておくことが非常に大切です。
これにより、いざという時に家族が判断に迷うことなく、故人の意向を尊重した対応ができるようになります。
延命治療や終末期医療の意思決定
医療や介護の希望の中でも特に重要なのが、延命治療や終末期医療に関する意思決定です。
自身の尊厳死の意思、臓器提供の有無、または緩和ケアの希望などを明確に示しておくことで、病状が悪化し意思表示ができなくなった際に、家族に重い決断を強いることを避けられます。
葬儀のスタイルを選ぶ
終活において、自身の葬儀に関する希望を事前に明確にしておくことは、残される家族の負担を軽減し、自分らしい最期を迎えるために重要です。
具体的には、葬儀の形式(家族葬、一般葬、一日葬、無宗教式など)、規模、予算、場所(葬儀社)などを検討します。
また、遺影に使ってほしい写真や、好きな音楽、祭壇の飾りつけなど、具体的な演出の希望を書き留めておくと良いでしょう。
最近では、葬儀の生前予約を受け付けている葬儀社もあり、生きているうちに契約を結んでおくことで、費用を明確にし、家族が急な手配に追われることを避けられます。
生前葬という、生きている間に自らが主催する葬儀も選択肢の一つとして注目されています。
これらの希望はエンディングノートに記入し、家族に伝えておくことが大切です。
お墓や納骨方法の検討
自身の供養方法やお墓に関する希望も、終活の重要な項目です。
先祖代々のお墓に入るか、新しいお墓を建てるか、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、海洋散骨など、様々な選択肢があります。
生前にお墓を購入する「寿陵(じゅりょう)」は、遺された家族の負担を減らし、相続税対策にもなることから増加傾向にあります。
お墓を選ぶ際は、立地、設備、費用(維持費を含む)を考慮し、複数の候補を見学することが推奨されます。
また、お墓の継承者がいない場合や、家族に維持管理の負担をかけたくない場合は、永代供養が特に有効な選択肢となります。
これらの希望も、エンディングノートに具体的に記入し、家族と事前に話し合って合意を得ておくことが大切です。
持ち物や住まいの片付け
終活において、自身の身の回りの持ち物を整理する「断捨離」や「生前整理」は非常に重要な項目です。
不要な物を残したまま亡くなると、遺された家族が遺品整理に多大な時間、労力、そして費用を要することになります。
「1年以上使っていないものは処分する」などのルールを決めることで、効率的に進められます。
また、思い出の品や譲りたい物がある場合は、それらを明確にし、保管場所を指定し、譲りたい相手に事前に確認しておくことが大切です。
体力や判断力が必要な作業であるため、元気なうちから少しずつ取り組むことが推奨されます。
老後の住まいについても、現在の住居に住み続けるか、子どもとの同居、高齢者施設への入居、またはダウンサイジングを目的とした住み替えを検討することが含まれます。
リフォームの必要性や、住み替えにかかる費用計画も立てておきましょう。
デジタル資産(SNS・パスワード)の整理
近年、スマートフォンやパソコンの普及に伴い、デジタル資産の整理も終活の重要な要素となっています。
SNSアカウント、ネットバンキング、オンラインサービス、サブスクリプション(月額課金)サービスなどの情報は、遺族が把握しにくいため、死後にトラブル(不正利用、解約不能による費用発生など)の原因となることがあります。
これらのアカウント情報やパスワードを一覧にまとめておくことが必須ですが、パスワードそのものを直接記載するのは危険です。
パスワードを推測できるヒントや、信頼できる人だけがわかる工夫をして記載し、安全な場所に保管しましょう。
不要なデータは削除し、大切な写真や文書は外部メディアにバックアップを取ることも重要です。
家族や友人へのメッセージ作成
終活は、残される家族や大切な人々への感謝の気持ちや伝えたい思いを形にする機会でもあります。
これまでの人生を振り返り、家族への感謝、友人への言葉、人生で経験したこと、伝えたい教訓などを書き記すことで、死後のコミュニケーションツールとなります。
これらのメッセージは、エンディングノートに自由に記載できます。
また、遺言書に「付言事項」として、相続人への感謝や配慮の言葉を添えることも可能です。
これは法的な効力を持つわけではありませんが、家族間の感情的な摩擦を和らげ、円満な相続を促す効果が期待できます。
手書きの便箋として残すなど、形式にこだわらず、自身の言葉で心を込めて綴ることが大切です。
エンディングノートの記入
エンディングノート(終活ノートとも呼ばれる)は、自身の基本情報、医療や介護の希望、葬儀やお墓の意向、財産状況、家族へのメッセージなど、終活に関する多岐にわたる情報を一冊にまとめるノートです。
書店やネットショップで様々な形式のノートが市販されており、必要項目があらかじめまとめられているため、初心者でもスムーズに情報を整理できます。
大学ノートを代用したり、デジタルで作成することも可能です。
ただし、エンディングノートには法的な拘束力はありません。
財産の相続など、法的な効力を持たせたい内容については、別途遺言書を作成する必要があります。
重要なのは、エンディングノートの存在と保管場所を家族や信頼できる人に伝えておくことです。
記載内容はいつでも書き換え可能であるため、定期的に見直し、最新の情報に更新することが望ましいです。
終活でやることリストの進め方
終活でやることリストを進める際には最初に取り組むべき優先順位を抑えたり、無理なく続けるための工夫が必要です。
- 最初に取り組むべき優先順位
- 無理なく続けるための工夫
- 家族と共有するポイント
最初に取り組むべき優先順位
終活を始めるにあたり、「何から手をつければ良いのか」と悩むのは自然なことです。
終活には明確なルールや手順はありませんが、スムーズに進めるためのいくつかのコツがあります。
まず、体力や気力があるうちに、比較的簡単な項目や、身体的な負担が大きい項目から着手することが推奨されます。
例えば、エンディングノートの作成や資産の棚卸し、不用品の整理(断捨離)などは、始めやすい項目とされています。
特に、不動産の見直しや介護施設の候補地巡り、お墓の検討など、体力が要求される活動は、元気なうちに済ませておくのが賢明です。
また、遺言書の作成など、法的な効力を持つ重要な書類の準備は、判断能力が低下する前に確実に行っておくべき項目として優先されます。
無理なく続けるための工夫
終活は多岐にわたる作業のため、一度にすべてを終わらせようとせず、自身のペースでゆっくりと進めることが成功の鍵です。
無理をすると、途中で挫折したり、本意ではない選択をしてしまったりする可能性があります。
例えば、エンディングノートは、書きやすい項目から少しずつ記入していくのがおすすめです。
また、「やりたくない」「面倒」と感じる項目は無理に手を出さず、後回しにするのも賢い方法です。
気持ちに余裕を持ち、楽しみながら終活を進める視点も大切です。
定期的に計画を見直し、状況に応じて内容を修正する習慣をつけましょう。
自身の健康状態やライフステージの変化に合わせて、柔軟に対応することで、常に最新で適切な終活を維持できます。
家族と共有するポイント
終活は個人的な準備活動ですが、家族や信頼できる人々と情報を共有し、相談しながら進めることが非常に重要です。
まず、自身の希望や意向を一方的に押し付けるのではなく、家族の意見にも耳を傾ける姿勢が求められます。
特に葬儀の形式やお墓の場所など、家族にも影響する事柄は、事前に話し合い、合意を得ておくことで、死後のトラブルを防ぎ、家族間の円満な関係を維持できます。
また、エンディングノートや遺言書の存在と保管場所をきちんと伝えておくことは非常に重要です。
せっかく準備しても、家族に見つけてもらえなければ意味がありません。
デジタル情報についても、アクセス方法を家族に共有する工夫が必要です。
日頃から家族とオープンに将来について語り合い、お互いの価値観を共有する雰囲気づくりを心がけましょう。
これにより、家族は故人の意思を尊重し、安心して対応できるようになります。
終活でやることリストに関連するよくある質問
終活でやることリストに関連するよくある質問をご紹介。
まだ50代でも始めるべき?
終活を始める年齢に明確な決まりはありません。
一般的には60代や70代で始める人が多いですが、20代や30代から取り組むことも可能です。
終活は、自身の体力や判断力が充実している元気なうちに始めることが理想とされています。
なぜなら、身の回りの整理、施設の見学、書類の作成など、多くの作業には時間、体力、そして冷静な判断力が必要だからです。
認知症などで判断能力が衰えてしまうと、希望通りの終活を進めることが困難になる可能性があります。
親の介護経験や自身の健康への不安、定年退職や子どもの独立といったライフイベントが終活を始めるきっかけとなることが多いです。
終活は「死の準備」というだけでなく、「これからの人生をより良く生きるための活動」と捉えれば、どの年齢からでも前向きに取り組むことができます。
終活に興味を持ったその時が、始めるべき最適なタイミングと言えるでしょう。
リストを紙とデジタルどちらで作る?
終活の「やることリスト」や「エンディングノート」の作成には、紙媒体とデジタル媒体の両方の選択肢があります。
紙のエンディングノートは、書店で様々な種類が市販されており、手書きで自由に記入できるのが特徴です。
電気やガス、金融機関の連絡先など、緊急時に家族が見てほしい情報をまとめておくのに便利です。
手書きで気持ちを込めてメッセージを残したい人にも適しています。
ただし、紛失や破損のリスク、保管場所を家族に伝える必要性があります。
一方、スマートフォンアプリやパソコンのファイルなど、デジタル形式で作成することも可能です。
デジタル終活の一環として、SNSアカウントやオンラインサービスのパスワード、写真データなどを整理する際に効率的です。
しかし、デジタル情報はパスワードの管理が非常に重要で、家族がアクセスできるように工夫しつつ、流出のリスクを避けるための注意が必要です。
どちらの形式を選ぶかは個人の好みによりますが、重要なのは情報が「必要な時に」「必要な人に」伝わるようにしておくことです。両方を組み合わせて活用することもできます。
全部一度にやらなくても大丈夫?
終活には多くの項目があり、すべてを一度にやろうとすると時間も手間もかかり、途中で挫折してしまう可能性が高いです。
そのため、焦らず、できるところから少しずつ進めることが非常に重要です。
リストの上から順番に取り組む必要もなく、自分が最も興味を持った項目や、手をつけやすいと感じる項目から始めても問題ありません。
例えば、エンディングノートの作成や不用品の整理(断捨離)は、比較的始めやすい項目として挙げられます。
また、終活の計画は一度決めたら終わりではなく、時間や状況の変化に応じて見直しや修正が必要になる場合があります。
無理なく、「いつかそのうち」ではなく「今のうち」に少しずつでも行動を開始することが、後悔のない終活に繋がります。
記事全体のまとめ
終活とは、自身の人生の終焉に向けて、より良い人生を全うし、残される家族の負担を軽減するために行う準備活動です。
これは決して後ろ向きな行為ではなく、将来への漠然とした不安を解消し、残りの人生を自分らしく、前向きに生きるための大切な機会となります。
終活には決まったルールや順序はありませんが、「やることリスト」を作成することで、取り組むべき事項を明確にし、効率的に進めることができます。
終活は、体力や判断力がある元気なうちに、興味のある項目や簡単な項目から少しずつ始めるのがおすすめです。
一人で抱え込まず、家族と話し合い、情報を共有し、必要に応じて葬儀社に相談をしたり弁護士や税理士、行政書士などの専門家の助けを借りることで、より確実で安心できる終活を進められます。
このリストを参考に、あなたらしい人生の終焉に向けて、今できることから一歩を踏み出してみませんか。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。