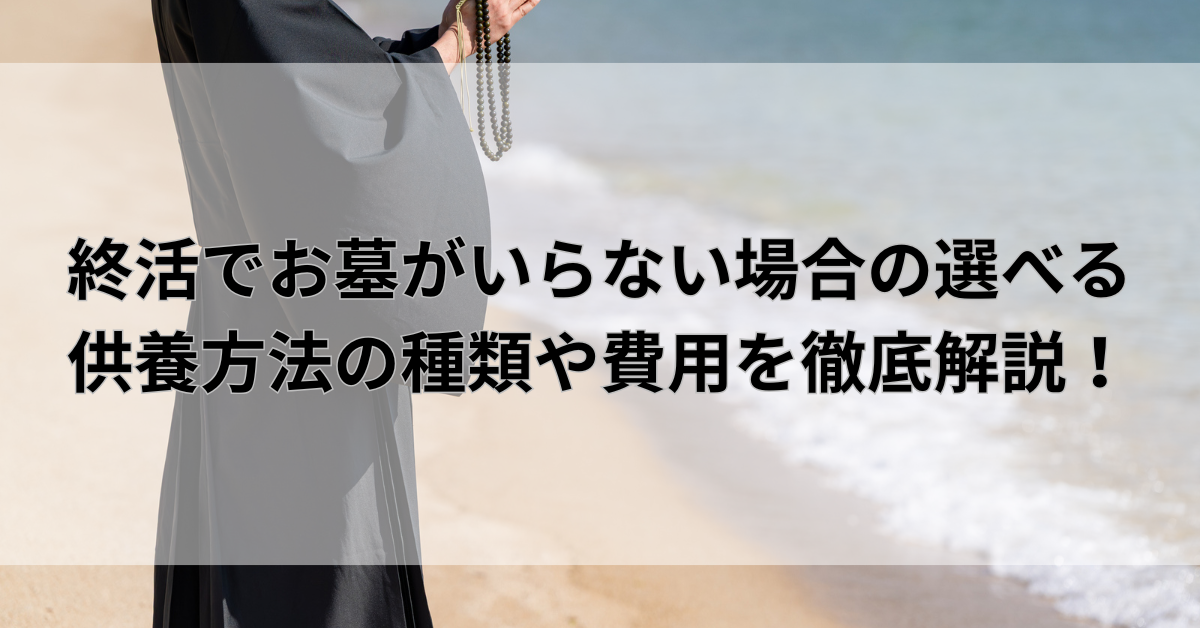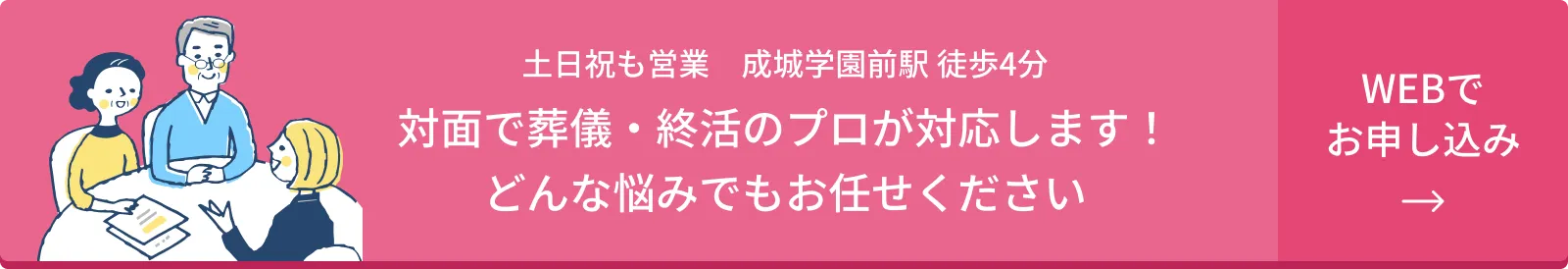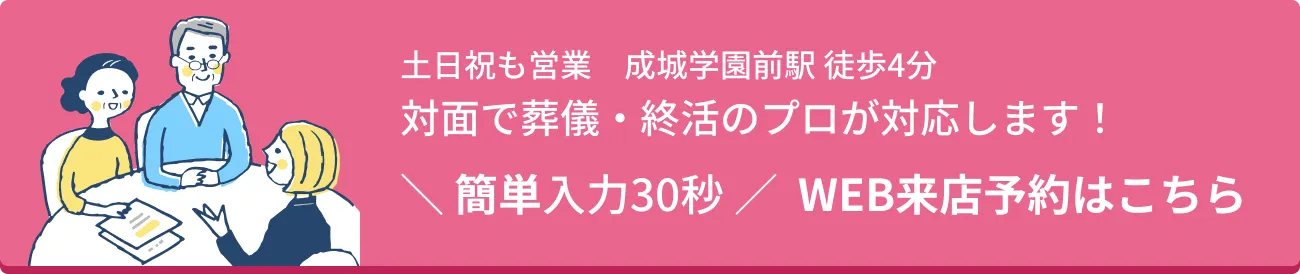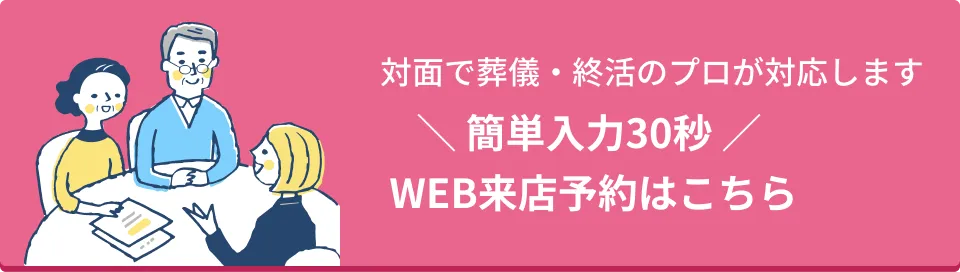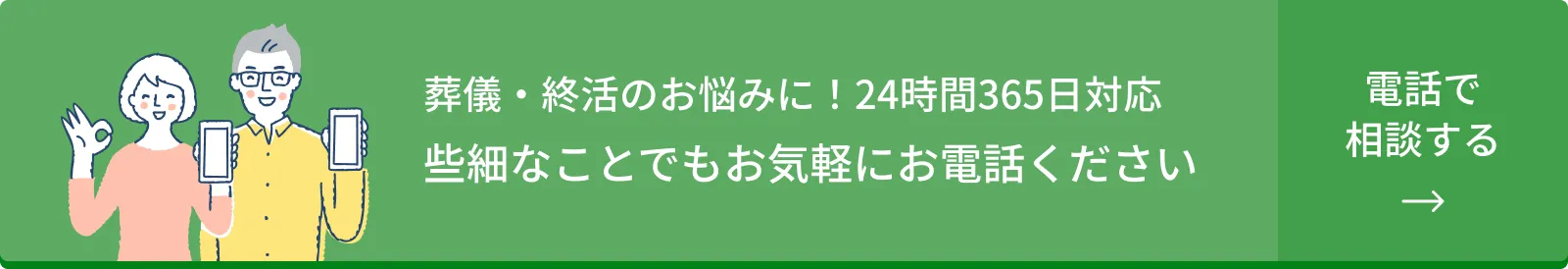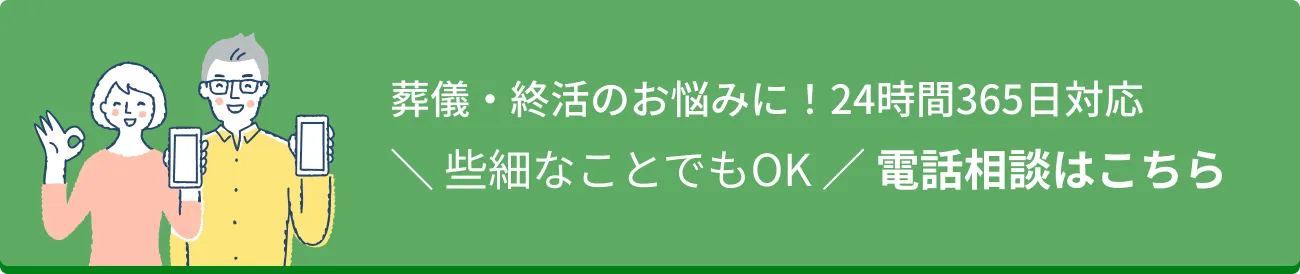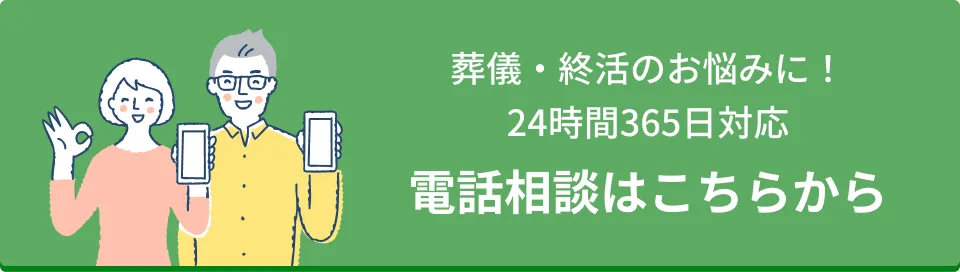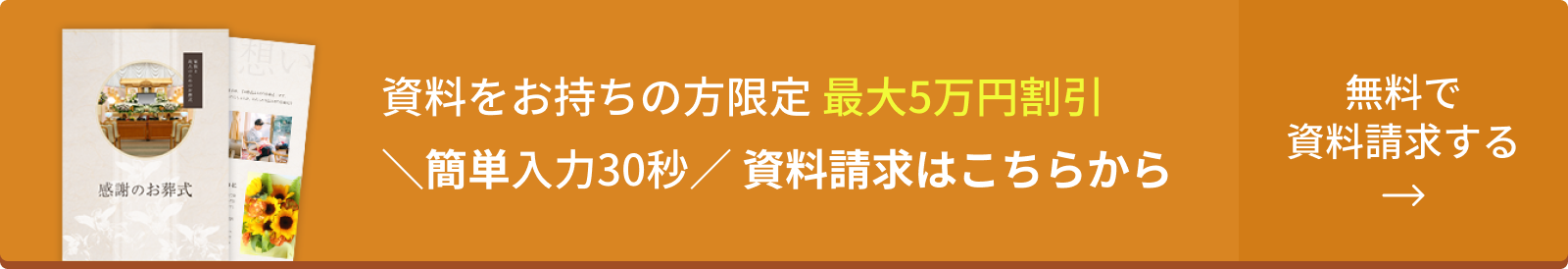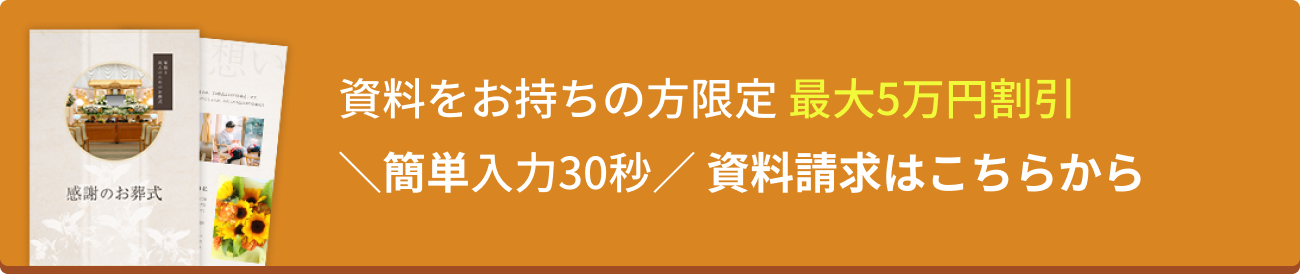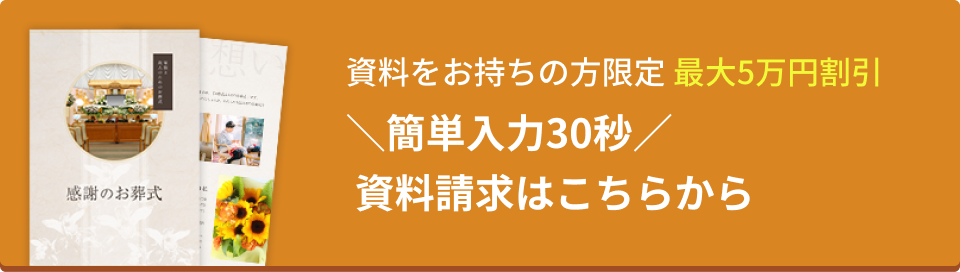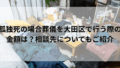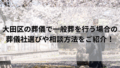終活を考える中でお墓はいらないのではないかと悩む方が増えています。
少子化やライフスタイルの変化により、従来のお墓を持つことは必ずしも当たり前ではなくなっています。
そこで注目されているのが、永代供養や樹木葬、散骨といった新しい供養の形です。
これらは家族への負担を軽減し、管理や費用の心配を和らげる選択肢として有効です。
本記事では、「お墓を持たない終活」という考え方の背景から、代表的な供養方法の特徴、選び方の基準まで詳しく解説します。
自分と家族にとって後悔のない供養方法を見極められる視点を得られるでしょう。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。
終活でお墓がいらない場合に選べる供養方法
終活の一環でお墓選びを検討する際に、お墓が既にあるけど管理をしたくない場合は永代供養、お墓はなく今後も不要な場合は樹木葬・散骨という供養方法があります。
- 永代供養の特徴と費用の目安
- 樹木葬の魅力と選び方のポイント
- 散骨を選ぶ際の注意点と手続き
永代供養の特徴と費用の目安
永代供養とは、個人や家族に代わって、寺院や霊園といった施設の管理者が、故人の供養や遺骨の管理を永続的に、あるいは定められた期間にわたって引き受ける形式を指します。
最大の魅力は、お墓の継承者を立てる必要がなく、残された親族が管理や供養に関する手間から解放されることです。
多くの場合、契約時にすべての費用を支払えば、その後の管理費用の心配がないという経済的な利点もあります。
供養の形態は幅広く、合祀墓や納骨堂、樹木葬といった多様な形式が、この永代供養として提供されています。
費用の目安は、供養の方法や施設、遺骨を個別に安置する期間の有無によって大きく変わり、およそ10万円から150万円程度とされています。
複数の故人の骨を一緒に納める合祀型であれば、3万円から30万円程度で、費用を最も抑えられます。
一方、納骨堂は10万円から200万円程度、樹木葬は3万円から150万円程度の範囲で検討が可能です。
樹木葬の魅力と選び方のポイント
樹木葬は、自然への回帰を願う「自然葬」の一つであり、墓石の代わりにシンボルとなる樹木や花を墓標として、その周囲に故人の骨を埋葬する供養方法です。
この供養の形式が持つ大きな魅力は、環境に配慮できること、そしてお墓を建立する費用を抑えられることです。
ほとんどのケースで後継者を必要としないため、家族に管理の負担をかけたくないという方や、おひとりさまの終活として選ばれています。
さらに、一般的に宗旨や宗派を問わず利用できる点も、多くの方に受け入れられる理由の一つです。
自然に溶け込むような山林での埋葬だけでなく、都市部や住宅地では、花壇のような整備された区画に納骨し、一定の期間が過ぎた後に合祀されるタイプが多く見られます。
個別の墓碑を残せるプランもあるため、手を合わせる場所を求めるか、あるいは自然への還元を優先するかなど、ご自身の価値観に基づいて最適な形式を選ぶことが肝心です。
費用はプランによって大きく異なり、数万円からこだわると100万円以上にもなりますので、樹木葬を選ぶ際に何を目的にするかによって選びましょう。
ただし、粉骨が必須となる場合があること、一度埋葬すると故人の骨を取り出すのが難しいこと、また遠方に位置する場合はお参り時のアクセスが不便になる可能性があることは、事前に理解しておくべきでしょう。
散骨を選ぶ際の注意点と手続き
散骨とは、故人の骨を粉状に細かく砕き、海や山、川といった自然環境に撒いて供養する、お墓を必要としない葬送の方法です。
故人が生前、自然を愛していたり、特定の場所に深い思い入れがあったりする場合に選ばれる供養の形です。
注意点として、散骨を行うためにはいくつかのルールを守る必要があります。
遺骨をそのまま撒くことはできず、必ず2mm以下のパウダー状に砕く「粉骨」をしなければなりません。
また、自治体の条例などにより散骨が禁止されている地域もあるため、個人で勝手に散骨することは避けるべきであり、専門の業者に依頼して節度を持って行うことが推奨されます。
一度散骨を実行すると、故人の骨は二度と手元に戻らないため、お墓参りをする物理的な場所がなくなることや、親族から理解が得られない可能性があることについては、特に慎重に検討する必要があります。
手続きと費用については、法律により許可された墓地以外の場所への埋葬は禁じられているため、専門業者が定めるガイドラインに沿って進めることになります。
費用は、業者が遺族に代わって散骨を代行する委託散骨で3万円~10万円程度、家族が船を貸し切って立ち会う貸切散骨では15万円~30万円程度が目安となります。
終活でお墓がいらない選択をするメリットとデメリット
お墓をいらない、という選択をする際にはメリットデメリットがありますので、それぞれ詳細をご紹介。
家族の負担を減らせるメリット
お墓を持たない供養方法を選択する最も大きな利点は、後の世代にかかる精神面および経済面での負担を大きく軽減できることです。
- 費用負担の解消
- 維持管理の手間からの解放
- 継承問題の解決
費用負担の解消
従来のお墓を建てる際に必要な初期費用(一般墓で80万円から250万円程度)や、毎年継続して支払う年間管理費(5千円から2万円程度)が不要になります。
寺院の檀家である場合は、お墓とは別に発生する檀家料やお布施などの金銭的負担も回避できます。
維持管理の手間からの解放
定期的なお墓参りや、掃除、墓地の草むしりといった物理的なメンテナンスが不要となります。 特に家族が遠方に住んでいる場合、お墓参りのための交通費や時間、労力を大幅に節約できます。
継承問題の解決
少子高齢化や核家族化が進む現代社会で、お墓の承継者を探す心配がなくなり、子や孫に「お墓を守る義務」を負わせずに済みます。
伝統的供養との違いによるデメリット
お墓を持たない供養方法は多くのメリットをもたらしますが、伝統的な供養との違いから、いくつかの課題や不都合が生じる可能性があります。
- 心の拠り所を失うこと
- 親族間でトラブルとなる可能性
- 故人の骨を個別に取り戻せなくなること
- 将来的な負担の先送り
心の拠り所を失うこと
お墓がないと、故人を思い、手を合わせるための物理的な場所を失うことになります。
故人との繋がりを感じ、悲しみを癒す心の支えとなる場所がなくなることに、寂しさや喪失感を覚える人もいます。
親族間でトラブルとなる可能性
昔ながらの供養の慣習や考え方を大切にする親族や地域の方々から、お墓を持たない選択に対して反対や非難を受けるリスクがあります。
特に、散骨や合祀など、一度実行すると故人の骨を取り戻せない方法を選択した場合、後々まで親族間のわだかまりが残る原因になることがあります。
故人の骨を個別に取り戻せなくなること
散骨や永代供養における合祀(合葬墓への納骨など)を選んだ場合、一度供養を終えると、後から個別に故人の骨を取り出すことは不可能となります。
将来的な負担の先送り
お墓を建てるという選択をしないことで、後の世代がやはりお墓が必要だと判断した場合、その建立費用や手間を子どもが負担することになる可能性があります。
また、自宅で手元供養を選んだ場合、その本人が亡くなった後、残された故人の骨を誰がどうするのかという課題が残ります。
終活でお墓がいらない選択をするときの判断基準
終活でお墓がいらない選択をする際の判断基準として、自分の価値観と家族の意向のすり合わせ方や費用の確認方法についてご紹介していきます。
- 自分の価値観と家族の意向のすり合わせ方
- 費用の確認方法
自分の価値観と家族の意向のすり合わせ方
お墓を持たないという決断は、ご本人だけでなく、遺された家族や親族の将来に影響を与える重要な事柄です。
まず、ご自身がどのような供養を望んでいるのか(散骨、永代供養、樹木葬など)を明確にし、その意向を家族や身近な人に生前にしっかりと伝えることが不可欠です。
この意向をエンディングノートに書き残すほか、口頭でも話し合っておくことが勧められます。
次に、故人を偲び、供養を行うのは遺族であるため、家族が故人との繋がりを感じる場所を必要としているかなど、家族の気持ちをよく確認し、終活を協力して進めることが大切です。
特に、すでにあるお墓を墓じまいする場合や、形が残らない供養を選ぶ場合は、親族間の揉め事を避けるために、関係者全員の理解と同意を得る努力が非常に重要となります。
もし家族や親族がいない、あるいは自分の希望を確実に実行してほしい場合は、弁護士や行政書士といった専門家と死後事務委任契約を結び、葬儀や供養の手続きを委託することも有効な手段です。
費用の確認方法
お墓を持たない供養方法を選んでも、永代供養や樹木葬、散骨などには費用が発生します。
複数の業者や施設から見積もりを取り、価格を比較検討することで、出費を抑えられる可能性があります。
また、初期費用だけでなく、納骨堂や一部の永代供養墓で必要となる年間管理料など、継続的にかかる費用も事前に確認しておくことが重要です。
終活でお墓がいらないに関するよくある質問
終活でお墓がいらない時によくある質問をいくつかご紹介。
永代供養はどれくらいの期間続く?
永代供養とは、霊園や寺院が遺骨の管理と供養を永続的に行うサービス全般を指しますが、遺骨が個別に安置される期間には、通常制限が設けられています。
多くの場合、契約で定められた一定期間(例えば、三回忌、十三回忌、三十三回忌など)は、個別の区画や納骨堂で管理されます。
この個別安置期間が終了すると、遺骨は他の故人の骨と共に一つの場所に集められ、「合祀(合葬)」されます。
合祀された後は、施設が半永久的に合同で供養を続けていくというのが一般的なシステムです。
納骨堂などでは、更新料を支払うことで個別安置の契約期間を延長できる場合があります。
樹木葬を選んだ後に後悔しない方法は?
樹木葬を選んだ後に後悔しないためには、事前の十分な検討と準備が必要です。
家族や親族との合意形成:樹木葬は比較的新しい供養の形式であるため、伝統的な供養観を持つ親族の理解が得られず、後々トラブルの原因となる可能性があります。
記事全体のまとめ
終活において「お墓はいらない」という考えを持つ人が増えているのは、少子高齢化に伴う継承者の不在、高額な費用負担、そしてお墓の管理の難しさといった、現代社会の構造的な変化が背景にあります。
お墓を持たなくても故人を供養する方法は多様化しており、永代供養、樹木葬、散骨、納骨堂、手元供養などが主な選択肢です。
これらの供養方法は、従来の一般墓と比較して費用や手間が軽減され、遺族の負担を大幅に軽くできるという大きなメリットを持っています。
しかし、お墓がないことで故人を偲ぶ物理的な場所が失われることや、伝統的な供養を重んじる親族との間で意見の対立が生じる可能性があるというデメリットも考慮しなければなりません。
特に散骨や合祀を選んだ場合、一度供養を終えると故人の骨を個別に取り戻すことが不可能になるため、その決断は慎重に行うべきです。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。