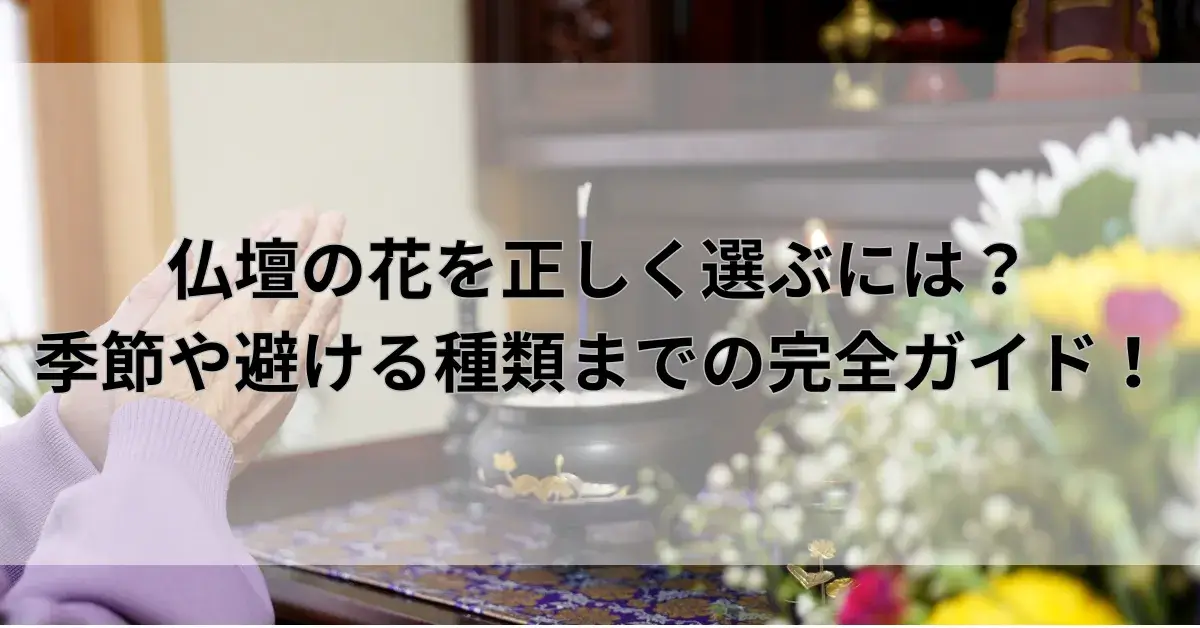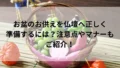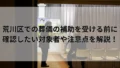仏壇に供える花は「何を選べばいいのか」「どれが失礼に当たるのか」迷いやすいものです。
特に季節や宗派によって判断基準が変わるため、初めて準備する方ほど不安は大きくなります。
本記事では、仏壇の花を正しく選ぶための種類・色・季節ごとのおすすめに加え、避けたほうが良い花の特徴もわかりやすく解説します。
さらに長持ちさせるコツや購入時のチェックポイント、よくある疑問もまとめています。
読んだ後は、迷わず故人にふさわしい花を自信を持って選べるようになります。
仏壇の花を選ぶ基本ルールについて
仏壇やお墓に花をお供えする行為は「仏花(ぶっか)」と呼ばれ、故人やご先祖様への敬意や感謝を示す大切な供養の一つです。
仏花を選ぶ際には、古くからの慣習に基づいた色や本数、花の種類に関するいくつかの基本を考慮することが望ましいとされています。
仏壇の花で守るべき色と本数の基本
仏壇に供える花の色彩については、一般的に使用される色が定まっています。
基本となるのは3色(白、黄、紫)か、または5色(白、黄、紫、ピンク、赤)の組み合わせです。
ただし、ご不幸があってから四十九日の期間は、まだ忌明け前であるため、白色を基調とした、淡い色合いの花を選ぶのが通例です。
四十九日を過ぎてからは、白だけでなく、黄色や紫、ピンク、赤といった明るい色を加えても問題ないとされています。
花の本数に関しては、3本、5本、7本といった奇数で揃えるのが望ましいという考え方が広くあります。
奇数は割り切れない数字であることから、「縁が切れない」といった縁起の良さや、全体のバランスを取りやすいという理由で好まれます。
厳密な決まりはありませんが、バランスを考慮すると奇数本数が一般的とされます。
仏壇に花立(花瓶)が左右一対で設けられている場合は、同じ花束を二つ用意し、左右対称になるよう飾るのが基本の作法です。
仏壇の花で避けるべき種類と選定基準
仏花として最も重要視される選定基準は、長期間美しい状態を保てる、日持ちの良い花を選ぶことです。
仏花には、すぐに傷んで仏壇周りを汚してしまうような花は適しません。
避けるべき花の種類としては、主に以下の特徴を持つものが挙げられます。
トゲや毒を持つ花
バラやアザミなどのトゲは殺生や怪我を連想させるため、また彼岸花やシャクナゲなどの毒は仏様に毒を供えることになると考えられるため、避けるべきとされています。
香りが強すぎる花
ユリやキンモクセイのように香りが強いものは、お線香や他の供物の香りを妨げてしまう可能性があるため、避けるのが無難です。
ただし、故人が特に好きだった場合は、トゲを取り除いたり、香りを抑えた品種を選んだりといった工夫をすれば、飾ってもよいという柔軟な考え方も広まっています。
縁起の悪い連想をさせる花
「死人花」(彼岸花)のように名前に「死」を連想させるものや、花が首から落ちるツバキ(椿)やサザンカ(山茶花)は不吉な連想を招くため、避けた方が良いでしょう。
また、一日でしおれる「一日花」(ムクゲなど)も、無常を連想させることから避けられることがあります。
人が食べる植物の花
アワ、麦、稲、オクラ、アスパラなど、食用となる植物の花を仏花として選ぶことは、縁起が悪いとされる場合があります。
仏壇の花で避けたいトラブルと注意点
仏花を選ぶ際や飾る際には、周囲との調和や、お供えとしての品位を保つために、いくつかの一般的な注意点を知っておく必要があります。
誤解されやすい色や香りの問題
仏花の色については、四十九日を過ぎれば白以外も使えますが、赤色をメインに使うことには注意が必要です。
赤は悲しみを連想させるとされ、仏花として避けるべき色とされることもあります。
しかし、五色のうちの一つとして淡い赤やピンクが使われることは一般的です。
また、香りの強い花は、しばしば誤解を生む原因となります。
ユリやバラといった香りの強い花は、お供えの基本であるお線香の香りを邪魔すると考えられるため、避けるべきとされることがありますが、実際にはユリは仏花として人気があります。
もしユリを使う場合は、香りが控えめな品種(例えばLAユリなど)を選び、花粉をあらかじめ取り除くことで、仏壇を汚さず、香りも抑えることができます。
マナー違反になりやすいケース
仏花に関する厳密なルールは存在しないものの、故人やご先祖様への敬意を示すために、伝統的に避けるべきとされるケースがあります。
マナー違反となりやすいのは、主に不吉な連想や怪我、仏壇の汚損につながる花を選ぶ場合です。
トゲのある花の使用
バラやアザミなど、トゲを持つ花は殺生を連想させるため、避けるのが基本です。
毒を持つ花の使用
彼岸花やシャクナゲなど、毒性のある花を仏様に供えることはタブーとされています。
ツル科の植物
クレマチスやスイートピーのようなツルがある花は、「故人の成仏を妨げる」という連想から避けるべきとされることがあります。
花の向きの誤り
花束を飾る際、お花を仏壇側ではなく、お参りをする人(自分たち)の方へ向けて飾るのが一般的なマナーです。
これは、仏様からの慈悲の心をお参りする側が享受するという意味が込められています。
故人の好きだった花を選ぶことは最大の供養となりますが、贈答用として仏花を用意する場合は、相手方や地域の慣習、親戚の考え方を尊重し、タブーとされる花は避けるか、事前に確認することが賢明です。
仏壇の花の管理で起こる傷みやすいリスク
生花は、長持ちする種類を選んでも、手入れを怠るとすぐに傷み、枯れた花がお仏壇を汚してしまうリスクがあります。
花が早く傷む主な原因は、花瓶(花立)の中でのバクテリアの繁殖です。
花立が汚れていたり、水が頻繁に交換されていないとバクテリアが増殖し、それが花の茎の切り口を塞いでしまうため、花が水を吸い上げられなくなり、結果として枯れてしまいます。
また、水に浸かっている部分に葉が残っていると、その葉が腐敗してバクテリアの増殖源となり、水質を悪化させる原因となります。
特に気温や湿度が高い夏場は、花の傷みが早くなるため、注意深い管理が必要です。
仏壇の花を長持ちさせる方法について
生花を長期間美しく保つためには、日々の手間を惜しまないことが大切です。
適切な手入れを行うことで、花の寿命を延ばし、常に清らかな状態でお供えすることができます。
仏壇の花を長持ちさせる水替えと温度管理
仏花を長持ちさせるための最も基本的な手入れは、水を毎日入れ替えることです。
これにより、花立の清潔さが保たれ、バクテリアの繁殖が抑えられます。
水を替える際には、花立の内側をきれいに洗い、花の茎にぬめりがある場合はそれも洗い流すと効果的です。
仏壇の花を置く環境で気をつけるポイント
仏花を飾る環境にも配慮することで、花の傷みを防げます。
花立に生ける際、水に浸かってしまう茎の下部の葉はすべて取り除くことが大切です。葉が水に浸かると腐敗し、バクテリアが繁殖する原因となるからです。
また、仏花は直射日光の当たらない、風通しの良い涼しい場所に置くことが推奨されます。
高温や強い日差しは花を早くしおれさせてしまうため、仏壇の配置によっては、温度管理に注意が必要です。
仏壇の大きさに合わせて、供える花のサイズを選ぶことも重要です。
花が大きすぎると仏具やご本尊を隠してしまい、全体のバランスが悪くなるだけでなく、供養本来の意味が薄れてしまう可能性があるため、仏壇のサイズに見合った高さやボリュームの花を選ぶようにしましょう。
仏壇の花に関するよくある質問
仏壇の花に関するよくある質問をいくつかご紹介していきます。
いつ取り替えるべき?
本来、仏壇の花は枯れるたびに頻繁に取り替えるのが最も好ましいとされています。生花は命あるものとして、仏の世界(お浄土)を表現し、常に新鮮な状態を保つことが理想です。
しかし、現代の生活において頻繁な交換が難しい場合は、故人の月命日に合わせたり、月に2回(例えば月初めと15日頃)に交換したりする方が多くいます。
季節によっても花の寿命は異なり、夏場は3〜4日、冬場は5〜7日を目安に交換するのが望ましいでしょう。
造花やプリザーブドフラワーでも問題ない?
一般的に、仏花は生花を供えることが望ましいとされています。
生花がやがて枯れる姿は、「諸行無常」という仏教の教えを体現し、私たちに命の尊さを再認識させる機会を与えるからです。
また、仏様は花の香りを楽しんでくださるという考え方もあります。
しかし、毎日の手入れの負担、費用、アレルギーの懸念、長期不在など、様々な理由から造花やプリザーブドフラワー(特殊加工された生花)を供えることも問題ありません。
特にプリザーブドフラワーは生花のような見た目を長期間保つため、人気が高まっています。
最も大切なのは、お供えする際の故人やご先祖様を敬う心(気持ち)です。
無理のない範囲で、生花と造花などを上手に使い分ける方法も推奨されています。ただし、ドライフラワーは「死」を連想させることから避けるべきという意見もあります。
宗派によって選ぶ花は変わる?
仏花として選ぶ花の種類や飾り方について、宗派による厳密な違いはほとんどありません。
どの宗派においても、奇数本で、菊やカーネーションなどを中心にした花束を供えるのが基本です。
ただし、浄土真宗では、他の宗派と異なり、樒(しきみ)を華瓶(けびょう)という仏具に挿してお供えすることが一般的です。
樒は手に入りにくい場合、木製の造花で代用されることもあります。
仏花の選び方や飾り方は、宗派だけでなく、地域固有の風習や、お寺(菩提寺)の方針によって異なる場合もあるため、迷う場合は事前に確認しておくと安心です。
記事全体のまとめ
仏壇にお供えする仏花は、単なる飾りではなく、故人への感謝と、私たちがお参りする人自身が命の尊さや仏教の教え(諸行無常)を再認識するための大切な供養品です。
仏花を選ぶ際の基本的なマナーとして、色彩は四十九日までは白や淡色を基調とし、その後は白、黄、紫、赤、ピンクの5色を基本に、奇数本で一対(左右対称)に飾ります。
また、トゲや毒がある花、香りが強すぎる花、すぐに散ってしまう花は避けるべきとされています。
日常的には菊やカーネーションなど日持ちの良い花を選び、季節の花を加えて故人を偲びます。
仏花を長持ちさせるためには、毎日の水替えと花立の清掃が不可欠であり、茎の水切りや水に浸かる葉を取り除く手入れが花の寿命を延ばします。
生花を供えるのが理想ですが、日々の管理が難しい場合は、造花やプリザーブドフラワーも供養の心を込めて使用しても問題ありません。
大切なのは、形式に囚われすぎず、故人を想う清らかな心です。