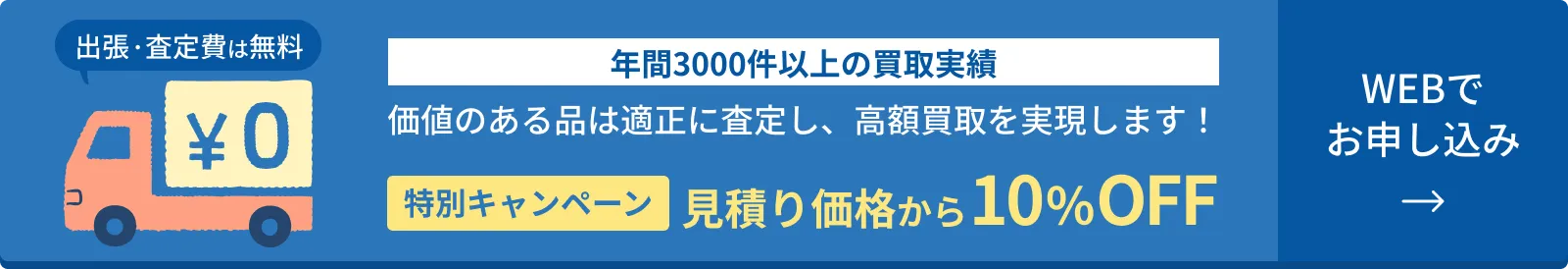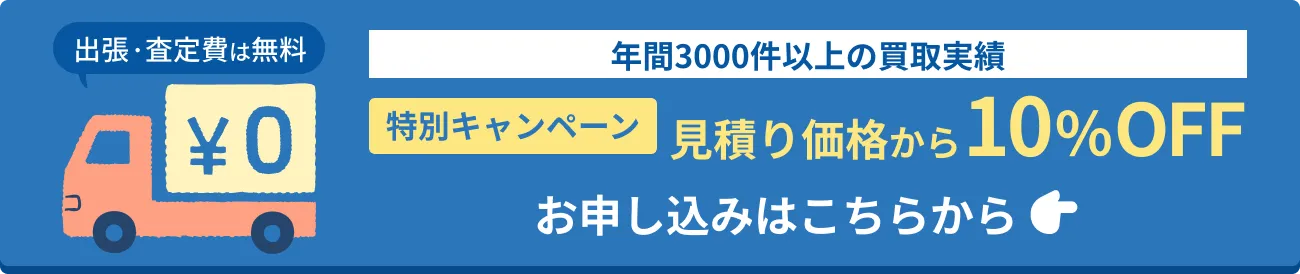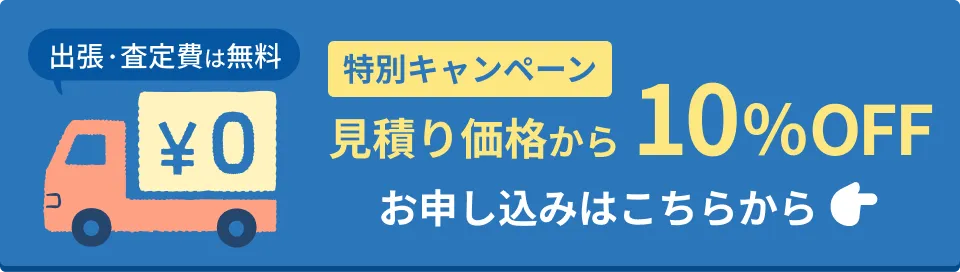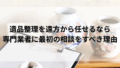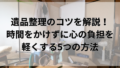家族や親族が亡くなった際、感情の整理が追いつかない中で遺品整理を始めることは難しいものです。
一方で、終わらせねばならない期限はないのか、作業にどれだけの期間を要するのかなど、遺品整理を始めるタイミングで悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
ここでは、遺品整理をいつから始めるべきかについて、状況に応じた適切なタイミングを解説します。
この記事を読めば、遺品整理の進め方を把握しスケジュールを立て、自分の状況に合ったタイミングで作業を進めることができるようになります。
本記事ではまず、遺品整理を始める最適なタイミングをそれぞれなぜ適当なのか、理由と共に説明します。
更に、遺品整理の進め方や注意点についても抑えていきます。
また、遺品整理は費用のトラブルや親族間でもめることもありますので、感謝の遺品整理お任せください!
感謝の遺品整理であれば出張費・査定費は0円で対応する可能、遺品の整理から買取までワンストップで行えますので、ぜひご連絡お待ちしております!


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。
遺品整理を始める最適なタイミング
遺品整理を始めるタイミングは、明確に規定されているわけではありません。
葬儀や各種手続きが終わり時間に余裕ができ、気持ちが落ち着いたタイミングで始めるのが一般的ですが、期限が設けられているものもあることに注意しましょう。
タイミングが早く来るものから順に見ていきます。
亡くなってから1か月以内のタイミング
故人が亡くなって間もなくは気持ちの整理がつきづらいものですが、早急に始める必要がある場合、1か月以内に遺品整理を始めることもあります。
葬儀や役所・保険関連の手続き後が、遺品整理を始める最も早いタイミングになります。
このタイミングがおすすめとなるケースは、今後全ての相続人が集まる機会が少ない場合などが挙げられます。
葬儀の後
葬儀を終えるまでは、最短で3日、長くて1週間程度かかります。
このタイミングは家族や親族も集まり、遺品整理について話すことができるかもしれません。
ただし、親族全ての方が同じタイミングで感情の整理をつけれるわけではないため、特段急ぐ理由がなければ少し時間を置いた方がスムーズに進むかもしれません。
役所・保険関連の手続きの後
故人が亡くなった後は、役所への死亡届、年金・健康保険などの届け出が必要になります。
死亡届出は亡くなって14日以内 (厚生年金は10日以内) に手続きをする必要があるので、まずは手続きを終わらせましょう。
公共料金・金融機関への利用停止などの連絡も必要です。
これら手続きが完了後、気持ちと時間に余裕があれば遺品整理につき家族・親族と話しておくといいかもしれません。
亡くなってから3か月以内のタイミング
次に亡くなってから3か月以内に始めるケースです。
このタイミングは、ある程度気持ちの整理がついてから遺品整理を始めたいという方におすすめです。
また、相続放棄の期限も3か月以内に設定されており、遺品整理を開始する一つの目安となります。
四十九日法要後
故人の命日から四十九日目には、四十九日法要が行われ親族が多く集まります。
葬儀後の落ち着かない状況と違い、遺品整理や形見分けの相談ができる良い機会なので、このタイミングで親族と話し合っておくと良いでしょう。
仏教の多くの宗派では、故人は亡くなってから四十九日間で来世の行き先が決定され、それをもって喪に服していた遺族も日常生活に戻るという意味合いもあることから、遺品整理の話し合いをする一般的なタイミングともされています。
相続放棄の期限の前
相続放棄を選択する場合、故人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述をする必要があります。
この期限を過ぎると自動的に単純承認を選択したと見なされ、仮に借金や保証債務などのマイナス財産がプラス財産を上回る場合も全ての財産を引き継いでしまいます。
こういった事態を避けるためにも、遺品整理は3か月以内を目安に始めると不要なトラブルを避けることができます。
亡くなってから10か月以内のタイミング
相続税の申告と納税の期限が、亡くなってから10か月以内に設定されていることに注意が必要です。
申告が必要になるケースでは、このタイミングで遺品整理を始めるのがおすすめです。
相続税の申告前
遺産相続が非課税枠を超えている場合は、故人が亡くなってから10か月以内に相続税の申告が必要です。
正しい相続税を算出するためにも、申告期限から数か月前から遺品整理を始めると安心です。
亡くなってから1年後のタイミング
遺品整理の開始タイミングや期限は明確に設けられていないため、亡くなってから1年後に自分のペースで始めることもできます。
遺品整理を始めても、感情に左右され作業が進まないという方にはこのタイミングがおすすめです。
気持ちが落ち着いてから
遺品整理は故人を偲びながらゆっくりと行いたいという方も多いので、自分や家族・親族の気持ちが落ち着くのを待ちましょう。ただし、上述の各種手続きは事前に済ませておくことをおすすめします。
遺品整理のスケジュール・進め方
遺品整理を進めるにあたり、スケジュールを立てて計画的に進めることが大事になってきます。
必要な手続きの期限を確認して逆算
まずは、重要事項の期限を確認しましょう。
具体的には、相続放棄の申述期限(3か月以内)、相続税の申告期限(10か月以内)に加え、賃貸の場合は賃料発生日時、所有不動産がある場合は固定資産税発生タイミングなどです。
遺言書やエンディングノートを確認
次に遺品整理にどれだけの期間がかかるかを把握するために、遺言書やエンディングノートがあれば確認します。
この際、自分だけで行うのではなく、全ての相続人の合意を取ることに注意し、その後実際に遺品整理の作業に取り掛かります。
自分たちで行うか業者に依頼するかを検討
遺品の量や種類を把握できたら、自分たちで行うのか業者に依頼するかを検討します。
自分たちで行う場合は、作業の計画を立て、遺品を分類していきます。分類は、貴重品・思い出の品・判断が難しいもの・明らかに処分すべきもの、などに仕訳けていくとよいでしょう。
業者に依頼する場合も、後々のトラブルを防ぐためにも、仕訳けは慎重に行う必要があります。
遺品整理を業者に依頼する場合の注意点や選び方については、下記記事をご覧ください。
自分たちで行うメリット・デメリット
自分たちで行うメリットは、ご自身のペースで費用を抑えて行うことができる点です。
親族と協力して行うことができれば、誤って捨ててしまったなどのトラブルを防ぐこともできます。
デメリットは、遺品の量が膨大な場合、多くの労力と時間がかかることです。
気持ちが整理できていない状況で遺品整理をすることは、精神的な負担にもなりかねません。
業者に依頼するメリット・デメリット
一方で業者に依頼することのメリットは、短時間で遺品の整理を済ませることができることです。
業者によっては、遺品供養や買い取りが可能な業者もあるため、処分を迷う物の整理にも便利です。
デメリットは、やはり費用が高くつくこともありますが、業者によっては悪徳業者も存在する点です。
検討している業者に不信な点がないか、依頼をする際に慎重に調査することが必要です。
感謝の遺品整理であれば出張費・査定費は0円で対応する可能、遺品の整理から買取までワンストップで行えます。
遺品整理を行う際の注意点
遺品整理を行う際は、以下のことに注意が必要です。
不動産の賃料や固定資産税の支払いに注意
賃貸物件で遺品整理を行う場合は、そのまま放置しておくと賃料が発生し続けることに注意が必要です。
できるだけ翌月の家賃が発生する前に終わらせることが理想です。
また、持ち家の場合は固定資産税が発生します。
毎年1月1日時点の土地の所有者に納税義務が課されるため、不要な支出を防ぐためにも、この期日を意識して遺品整理を進めるとよいでしょう。
空き家になる場合、空き巣や火災・倒壊に注意
故人が住んでいた住宅が空き家になる場合、空き巣や火災・倒壊のリスクがあります。
本格的な遺品整理を始める前でも、水道・ガス・電気の停止、発火の恐れのある電子機器の処分や、定期的な点検とメンテナンスを行うようにしましょう。
遺品整理前に親族・相続人全員との話し合いを忘れぬよう注意
遺品整理を行う前には、進め方について親族・相続人全員との話し合いが欠かせません。
誰が遺品整理をするかを決めず勝手に一人で始めてしまうと、思い出の品を処分してしまったり、形見分けで揉めたりとトラブル発生の元です。
相続関連は非常にトラブルが多い問題ですので、遺品整理を始める前に親族間で十分に話し合いをすることを心がけましょう。
記事全体のまとめ
本記事では、遺品整理を始めるタイミングについて解説しました。
始めるタイミングについては明確な指定はないため、自分や親族の気持ちが落ち着いてから進めるべきですが、期日が定められている手続きには注意が必要です。
特に、相続放棄の申述の期限である3か月、相続税申告の期日である10か月以内には意識をして進めましょう。
また、遺品整理を進めるにあたり、相続人・親族との事前の話し合いは重要です。
遺品整理を始めるのが遅れると、賃料や固定資産税などの発生や、空き家になる場合は火災や倒壊などのリスクが起こることもあります。
故人が亡くなった後は、やることも多く精神的にも身体的にも負担が大きい日々が続きます。
遺品整理の進め方や注意点、必要な手続きを把握しておくことで、故人を偲び、気持ちが落ち着いたタイミングで整理を進められるようにしましょう。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。