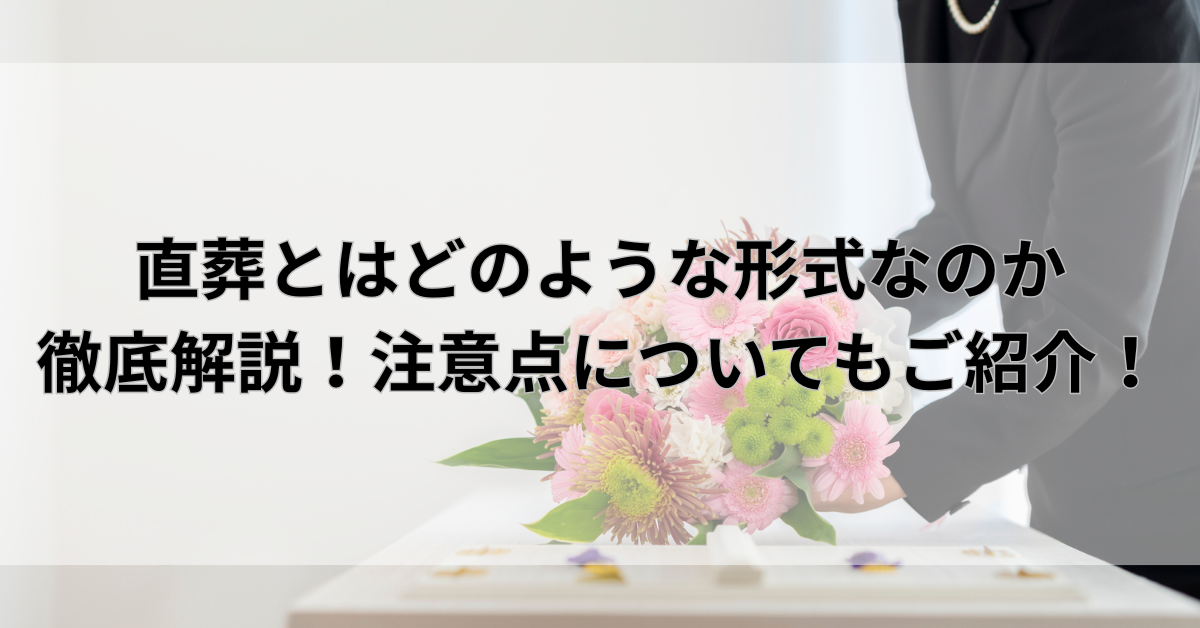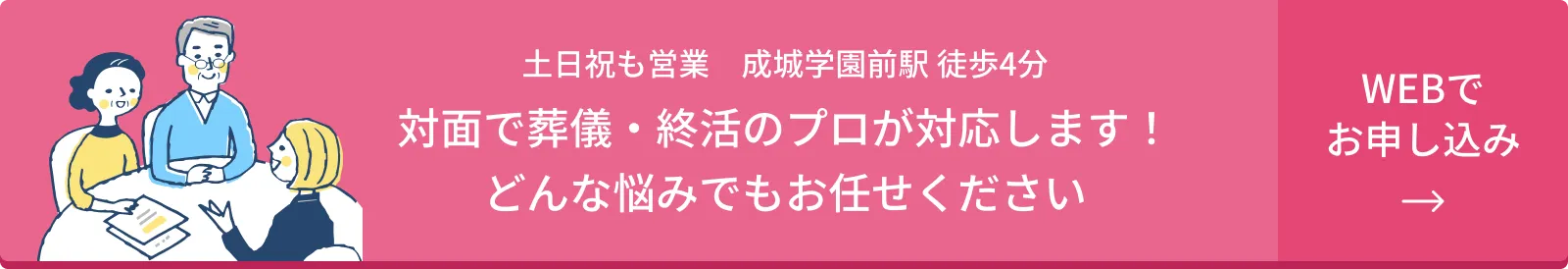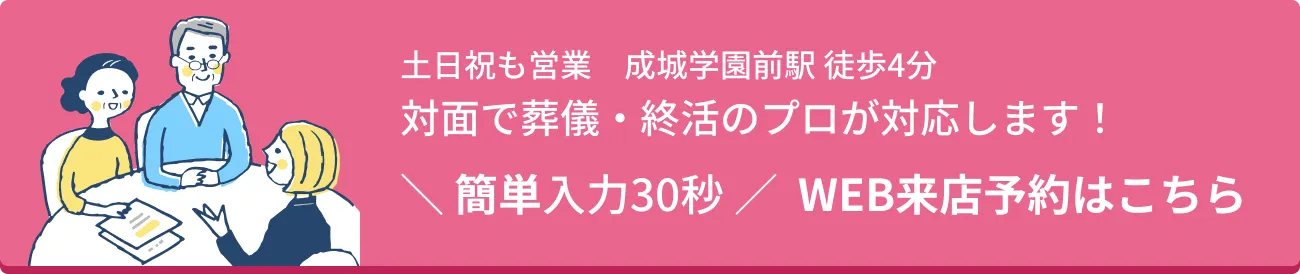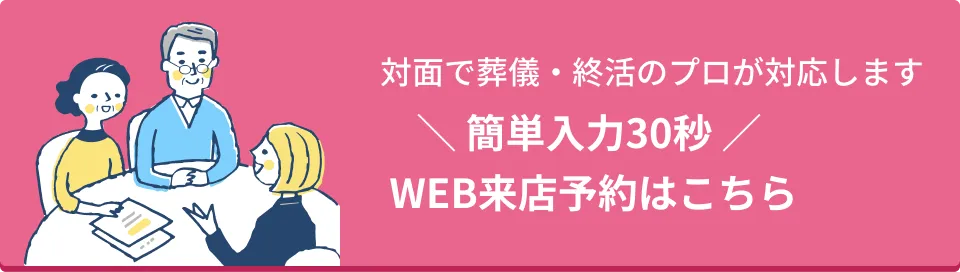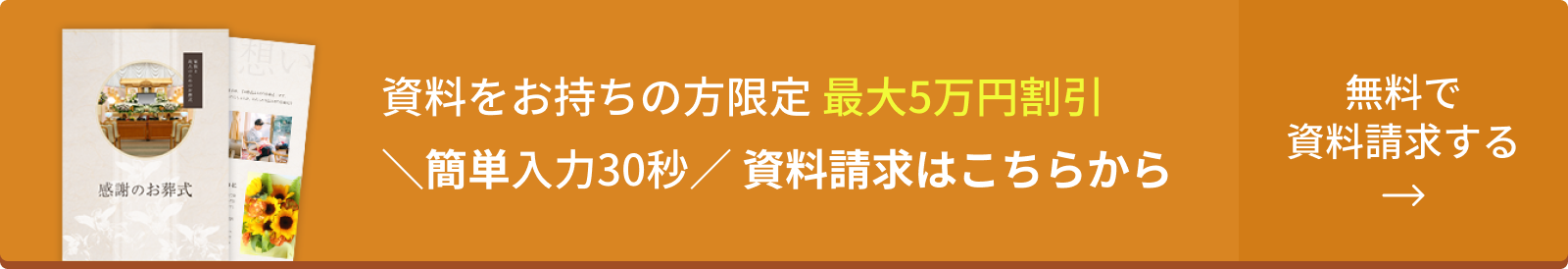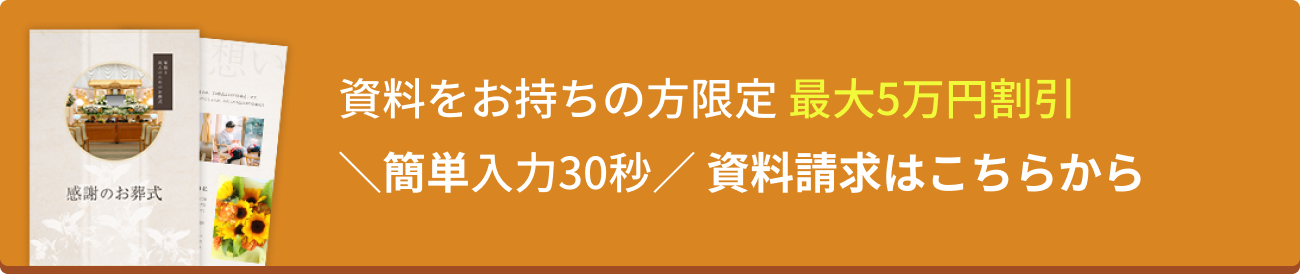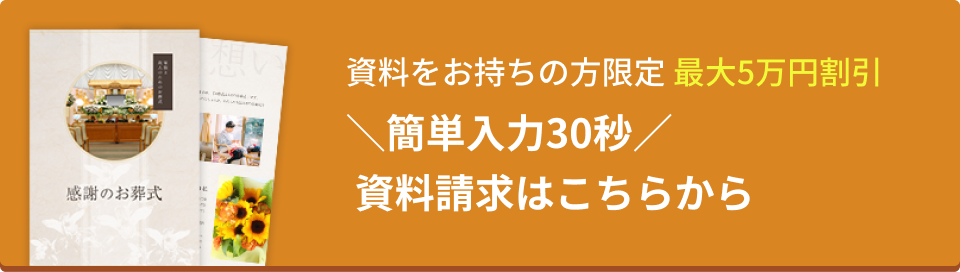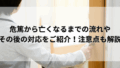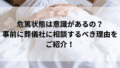直葬という言葉を聞いても、実際どんな葬儀なのか、費用はどのくらいか、何を準備するのかがわからず不安に感じませんか?
一般的な葬儀よりも費用を抑えられる方法として注目される一方で、準備不足や誤解によってトラブルや後悔につながるケースもあります。
この記事では、直葬とは何か、どのような流れで進むのか、必要な手続きや費用の目安、そして気をつけたいポイントまでをわかりやすく解説します。
よくある質問も交えながら、葬儀に慣れていない方でも迷わず準備できる内容にまとめています。
親や家族の最期を穏やかに送り出すために、選択肢のひとつとして直葬を正しく理解し、自分にとって後悔のない判断をするための一歩としてご活用ください。
感謝のお葬式では熟練のスタッフが葬儀・遺品整理・終活・相続などの一括サポート可能ですので、ぜひにお気軽にお電話ください。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。
直葬とは何か?基本的な意味と最近の傾向
直葬とはお通夜や告別式を省略して火葬のみの形式のことで、近年増加傾向にあります。
増えている背景や一般葬との違いについてご紹介。
- 直葬が増えている背景
- 一般葬との違い
直葬が増えている背景とは?
直葬は、伝統的なお通夜や告別式といった儀式を省き、火葬のみで故人を弔う葬送形式を指し、「火葬式」とも呼ばれます。
この葬儀形態は、近年日本で選択されることが増えており、その背景にはいくつかの要因があります。
主な増加傾向の理由の一つは、経済的な事情です。
従来の葬儀にかかる費用を抑えたいというニーズが高まっています。
また、社会の高齢化が進み、故人に縁のある方々がすでに他界しているケースや、近親者の数が少ないといった家族構成の変化も影響しています。
さらに、地域社会との関わりが薄れ、葬儀の形式にこだわりを持たない人が増えたことや、故人自身が生前から直葬を希望していた場合も、その意思が尊重される傾向にあります。
一般葬との違いをわかりやすく解説
直葬と一般的な葬儀(一般葬)の最大の違いは、儀式の有無と規模です。
一般葬は通常2日間かけて行われ、1日目にお通夜、2日目に告別式と火葬を執り行い、親族だけでなく故人と縁のあった多くの人々が参列します。
これに対して、直葬は通夜や告別式を一切行わず、火葬のみを行うため、儀式に要する時間が大幅に短縮されます。
参列者は基本的に、ごく近しい家族や親族など少人数に限定されることがほとんどです。
火葬炉の前で短時間のお別れを行い、数時間で終了することが多いのが特徴です。
直葬の特徴をわかりやすく解説する
直葬の特徴として、費用を時間を抑えることができるシンプルな形式であることが挙げられます。
費用と時間を抑えたシンプルな形式
直葬は、故人を見送る形式の中で最もシンプルであり、これが大きな特徴です。
費用面
通夜や告別式のための式場使用料や祭壇、装飾などが不要になるため、葬儀費用を大幅に抑えることができます。
また、参列者が少ないため、飲食の接待や返礼品にかかる費用も最小限で済みます。
時間と負担
準備や当日の対応が簡素化されるため、喪主や遺族の身体的・精神的な負担が軽減されます。
弔問客への挨拶や気遣いの必要がほとんどなく、時間的な拘束も短いため、特に高齢の遺族にとっては大きなメリットとなります。
通夜や告別式を行わないことの意味
直葬では、一般的な葬儀で行われる通夜や告別式といった宗教的な儀式は、原則として行いません。
これは、形式にとらわれず、故人とごく近しい人々だけで静かにお別れをしたいという遺族の意向を反映しています。
厳密には葬儀というよりも、故人の遺体を滞りなく火葬することに特化した形式とも言えるでしょう。
直葬にかかる費用と内訳を詳しく紹介する
直葬にかかる費用としては20万円から50万円とされており、一般葬と比較してもかなり安い金額で葬儀をすることができます。
- 平均費用と最安の目安
- 具体的な項目
平均費用と最安の目安
直葬の費用は、一般的な葬儀に比べて大幅に抑えられます。
平均的な費用は20万円から50万円程度とされており、これは一般葬の相場(約100万円~300万円)の約1/3から1/7程度に相当します。
葬儀社によっては、さらに低価格のプラン、例えば10万円前後のプランを提供しているところもあります。
具体的な内訳や項目
直葬では遺体運搬・安置や管理・葬祭用具一式・スタッフ人件費・火葬場の使用料などの項目があり、それぞれ費用が発生します。
- 遺体搬送費用
- 安置や管理費用
- 葬祭用具一式
- スタッフ人件費
- 火葬場の使用料
遺体搬送費用
病院や施設から安置場所、そして火葬場への搬送にかかる費用です。移動距離によって金額が変わる場合があります。
安置や管理費用
法律で死後24時間以内の火葬が禁じられているため、火葬までの間、遺体を安置する場所の利用料や、ドライアイスなどの管理費用が含まれます。
葬祭用具一式
棺、骨壺、棺用の布団などが含まれます。棺の価格は3万円から7万円前後が一般的です。
スタッフ人件費
葬儀社スタッフによる搬送や手続きのサポートなどにかかる人件費です。
火葬場の使用料
火葬施設を利用するための料金です。
これは葬儀社のプランに別途費用として計上されることが多い項目です。
公営の火葬場は比較的安価(無料~5万円程度)ですが、民営は高額(5万円~20万円程度)になることがあります。
また、故人や喪主がその自治体の住民であるかによっても料金が変動します。
オプションやプランに含まれていない追加費用とは
提示されている直葬プランの費用には、安置期間の延長や面会の希望、その他物品などの項目が含まれていない場合があり、別途追加費用が発生する可能性があります。
- 僧侶へのお布施
- 安置期間の延長
- 面会の希望
- その他の物品
僧侶へのお布施
火葬炉の前での読経や、故人への戒名(法名)授与を依頼する場合、僧侶への費用(お布施)が必要になります。
読経で5万円~10万円程度、戒名で15万円~20万円程度が目安とされています。
安置期間の延長
火葬場の予約状況により、予定よりも安置期間が長引く場合、追加の安置施設利用料やドライアイス代が発生することがあります。
面会の希望
葬儀社の安置施設での故人との面会には、追加料金がかかったり、面会時間が制限されたりする場合があります。
その他の物品
遺影写真、故人へのお別れ花、線香、ろうそくなどがプランに含まれていないこともあります。
安価なプランを提示している葬儀社では、これらの「当然含まれていると思われがちなもの」がオプション扱いになっていることがあるため、事前にプラン内容と費用の内訳を詳細に確認することが重要です。
直葬を選ぶメリット
費用を大きく抑えることができる、精神的・肉体的な負担軽減、宗教儀式にとらわれず自由な送り方ができる、故人の意思を尊重しやすい柔軟な選択肢、時間や日程の調整が比較的しやすいなどのメリットがあります。
- 費用を大きく抑えられる
- 精神的・身体的な負担を軽減できる
- 宗教儀式にとらわれず自由な送り方ができる
- 故人の意思を尊重しやすい柔軟な選択肢
- 時間や日程の調整が比較的しやすい
費用を大きく抑えられる
直葬は、通夜や告別式といった伝統的な儀式を省き、火葬のみを行う非常に簡素な葬儀形態です。
このシンプルな形式により、葬儀にかかる費用を大幅に削減できる点が最大の魅力です。
一般的な葬儀費用が平均で130万円から200万円程度とされるのに対し、直葬の平均費用は20万円から50万円前後、中には10万円を切るプランを提供する葬儀社もあります。
費用が抑えられる主な理由は、式場の利用料、祭壇の装飾費、飲食接待費、返礼品などの費用が不要になるためです。
ただし、火葬場の利用料金は別途発生する場合が多く、地域や施設の種類によって費用が異なります。
精神的・身体的な負担を軽減できる
直葬は、遺族の精神的および身体的な負担を大きく軽減できるという利点も持ち合わせています。
通夜や告別式を省略することで、準備にかかる時間や労力が最小限に抑えられます。
また、参列者が限定されるため、多くの弔問客への挨拶や対応、返礼品の準備といった葬儀後の作業も大幅に減らすことができます。
葬儀の拘束時間が短いことも、体力的な負担軽減につながります。
特に高齢の親族や遠方からの参列者にとっては、宿泊などの必要がなく、移動による負担も少ないため、安心して故人を見送ることが可能になります。
宗教儀式にとらわれず自由な送り方ができる
直葬は、通夜や告別式といった宗教的な儀式を一切行わない葬儀形式です。
これにより、特定の宗教宗派にこだわらず、故人や遺族の意向に合わせた自由な見送りが可能となります。
故人や遺族に信仰する宗教がない場合や、特定の寺院との関わりが薄い場合でも、形式にとらわれずに故人を弔うことができます。
火葬炉の前で僧侶に読経を依頼するなど、部分的に宗教的な要素を取り入れることも選択肢としてあり、柔軟な対応が可能です。
参列者もごく身近な人々に限定されるため、気兼ねなく故人との最後の時間を過ごすことができるでしょう。
故人の意思を尊重しやすい柔軟な選択肢
現代社会におけるライフスタイルの多様化や価値観の変化に伴い、直葬は故人や遺族の意思を反映しやすい柔軟な選択肢として注目されています。
故人が生前に「質素に見送ってほしい」「家族に負担をかけたくない」といった意向を示していた場合、直葬はその意思を尊重する形として選ばれることが増えています。
また、少子高齢化や核家族化が進む現代において、親族の数が少ない場合や、近隣との関係が希薄になっている場合でも、故人や遺族の状況に合わせて最適な見送りの方法を選ぶことができます。
これにより、形式に縛られることなく、故人との関係性を大切にしたお別れが可能になります。
時間や日程の調整が比較的しやすい
直葬は、通夜や告別式を行わないため、葬儀自体の所要時間が短く、通常は数時間で終了します。
これにより、遺族は葬儀に割く時間を最小限に抑えられ、スケジュールの調整が比較的容易になります。
ただし、日本の法律では死亡から24時間以内の火葬が認められていないため、故人の遺体は最低24時間は安置する必要があります。
そのため、火葬場の混雑状況によっては待機期間が発生することもありますが、従来の二日間かける葬儀に比べて、日程調整の柔軟性は高いと言えるでしょう。
直葬のデメリットを正しく理解しておく
直葬のデメリットは親族や知人に誤解を与えるリスク、お別れの時間が十分に取れないこともある、火葬場の空き状況で日程調整が難しい場合もあることが挙げられます。
- 親族や知人に誤解を与えるリスク
- お別れの時間が十分に取れないこともある
- 火葬場の空き状況で日程調整が難しい場合もある
親族や知人に誤解を与えるリスク
直葬は簡素な形式であるため、親族や故人の友人・知人からの理解が得られず、トラブルに発展する可能性があります。
親族からの不満
特に高齢の親族の中には、伝統的な葬儀を「故人への礼儀」と考える方も多く、「盛大な葬儀で見送ってあげたい」「故人がかわいそうだ」といった不満の声が上がることがあります。
友人・知人からのクレーム
直葬は近親者のみで行われるため、故人と親交の深かった友人や知人が最期のお見送りに立ち会えないことで、不満や寂しさを感じることがあります。
葬儀後の弔問対応
葬儀に参列できなかった人々が後日自宅へ弔問に訪れることがあり、その都度対応が必要になるため、かえって遺族の負担が増えることも考えられます。
お別れの時間が十分に取れないこともある
直葬の大きなデメリットは、故人とのお別れの時間が非常に短いことです。
火葬炉の前での数分間のお別れが、故人との最後の対面となることが多く、ゆっくりと故人を偲んだり、顔を見て別れを告げたりする時間がほとんどありません。
この短さから、葬儀後に「故人を十分に見送れなかった」「もっと手厚い供養をすればよかった」と後悔や罪悪感に苛まれる遺族も少なくありません。
感情の整理がつきにくいと感じる方もいるでしょう.
火葬場の空き状況で日程調整が難しい場合も
日本では法律により、故人の死後24時間以内は火葬ができないと定められています。
そのため、直葬であっても、火葬までの間は自宅や葬儀社の安置施設などに遺体を安置する必要があります。
特に都市部では、火葬場が混み合っていることが多く、火葬の予約が数日〜1週間程度先になることも珍しくありません。
この場合、安置期間が長くなり、その分の安置費用やドライアイス代などが追加で発生する可能性があります。
直葬を選んだからといって、必ずしも全体の期間を短縮できるわけではない点に注意が必要です。
直葬を行う際の注意点を確認する
直葬を行う際には、事前に家族・親族と話し合っておくことや本人の意思を記録に残しておくことが大切です。
また、地域の風習や宗教的配慮も忘れないことが重要です。
- 事前に家族・親族と話し合っておく
- 本人の意思を記録に残しておくことが大切
- 地域の風習や宗教的配慮も忘れずに
事前に家族・親族と話し合っておく
直葬を検討する際には、事前に家族や親族と十分に話し合い、理解を得ておくことが非常に重要です。
直葬という形式がまだ馴染みがなく、故人への見送りの仕方に対する価値観が異なる場合があるため、事前の説明なしに進めると、後々の人間関係に影響を及ぼすトラブルに発展する可能性があります。
故人の意向や、経済的な理由など、直葬を選択する明確な理由を丁寧に伝えるようにしましょう。
本人の意思を記録に残しておくことが大切
故人が生前から直葬を希望していた場合、その意思をエンディングノートや遺言などに記録として残しておくことが大切です。
これにより、遺族が直葬を選択する際に、親族からの理解を得やすくなることがあります。
故人の生前の意思を尊重していることを伝えることで、反対意見を和らげ、スムーズな進行につながるでしょう。
地域の風習や宗教的配慮も忘れずに
直葬を行う際には、特に以下の点に注意が必要です。
菩提寺(先祖代々のお墓がある寺院)との関係
直葬は宗教的な儀式を省略するため、菩提寺との関係がある場合は、事前に寺院に相談し、了解を得ることが不可欠です。
事前の相談なしに直葬を行うと、お墓への納骨を拒否されたり、その後の法要を行ってもらえなかったりするトラブルに発展する可能性があります。
埋葬方法の検討
菩提寺に納骨を断られた場合や、もともと菩提寺がない場合は、永代供養墓、散骨、樹木葬など、他の埋葬方法を検討する必要があります。
地域の慣習
火葬後の骨上げの方法など、地域によって慣習が異なる場合があるため、火葬場のスタッフの指示に従うか、事前に確認しておくことが賢明です。
直葬に関するよくある質問
直葬に関するよくある質問を4つご紹介していきます。
- 直葬に親族を呼んでもいいの?
- お坊さんやお経は必要ないの?
- 直葬でも後からお別れ会はできる?
- 直葬と家族葬の違いは何ですか?
直葬に親族を呼んでもいいの?
直葬は、通夜や告別式を行わない簡素な形式であり、一般的にはごく近しい家族や親族など少人数で行われます。
誰を呼ぶかについては厳密な決まりはありませんが、「故人と最後にお別れをしてほしい」と思う人を呼ぶことができます。
ただし、火葬場のスペースや時間には限りがあるため、大人数を招くことは難しい場合が多いです。
参列を希望する人には、直葬であることを事前に伝えることが、後々のトラブルを防ぐ上で重要です。
お坊さんやお経は必要ないの?
直葬では、通夜や告別式のような宗教儀式を省略することが一般的です。
そのため、僧侶を呼ばずにお経も読まないケースが多いです。
しかし、故人や遺族の宗教的背景によっては、火葬炉の前で短時間だけ僧侶に読経をしてもらうことも可能です。
菩提寺がある場合は、戒名が必要かどうかも含めて事前に相談することが大切です。
また、宗教的な儀式を行わない「無宗教葬儀」も、直葬を検討する人が選ぶことの多い代替案です。
直葬でも後からお別れ会はできる?
はい、直葬後でも「お別れ会」を開くことは可能です。
直葬は故人とのお別れの時間が短いというデメリットがあるため、後になって「もっとゆっくりお別れしたかった」「知らせていない人にも見送ってもらいたかった」と後悔する遺族もいます。
そうした思いを解消するために、四十九日や一周忌などのタイミングで改めて「お別れ会」を催すケースが増えています。
お別れ会は、従来の葬儀のような厳格な決まりがなく、故人の人柄や思い出に合わせた内容で自由に企画できるのが特徴です。
直葬と家族葬の違いは何ですか?
直葬と家族葬は、どちらも小規模な葬儀形式ですが、儀式の有無において明確な違いがあります。
直葬
お通夜や告別式といった宗教的な儀式を一切行わず、火葬のみで故人を送る最もシンプルな形式です。
参列者はごく少数の近親者に限定されます。費用と時間が最も抑えられます。
家族葬
参列者を家族や親族、特に親しい友人に限定し、通夜や告別式といった儀式を執り行う葬儀形式です。
一般葬よりも規模は小さいものの、故人とゆっくりお別れする時間を持ち、従来の葬儀の流れを踏襲します。
費用は直葬よりは高くなりますが、一般葬よりは抑えられます。近年、一般的な葬儀形式の主流になりつつあります。
直葬の記事全体のまとめ
直葬は、通夜や告別式などの宗教儀式を省略し、火葬のみで故人を弔う、極めてシンプルな葬儀形式です。
直葬を選択する際は、故人の生前の意向を尊重しつつ、事前に家族や親族と十分に話し合い、地域の風習や宗教的な配慮を怠らないことが重要です。
後悔のないお見送りのために、プラン内容や費用の詳細をしっかりと確認することをおすすめします。
感謝のお葬式では熟練のスタッフが葬儀・遺品整理・終活・相続などの一括サポート可能ですので、ぜひにお気軽にお電話ください。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。