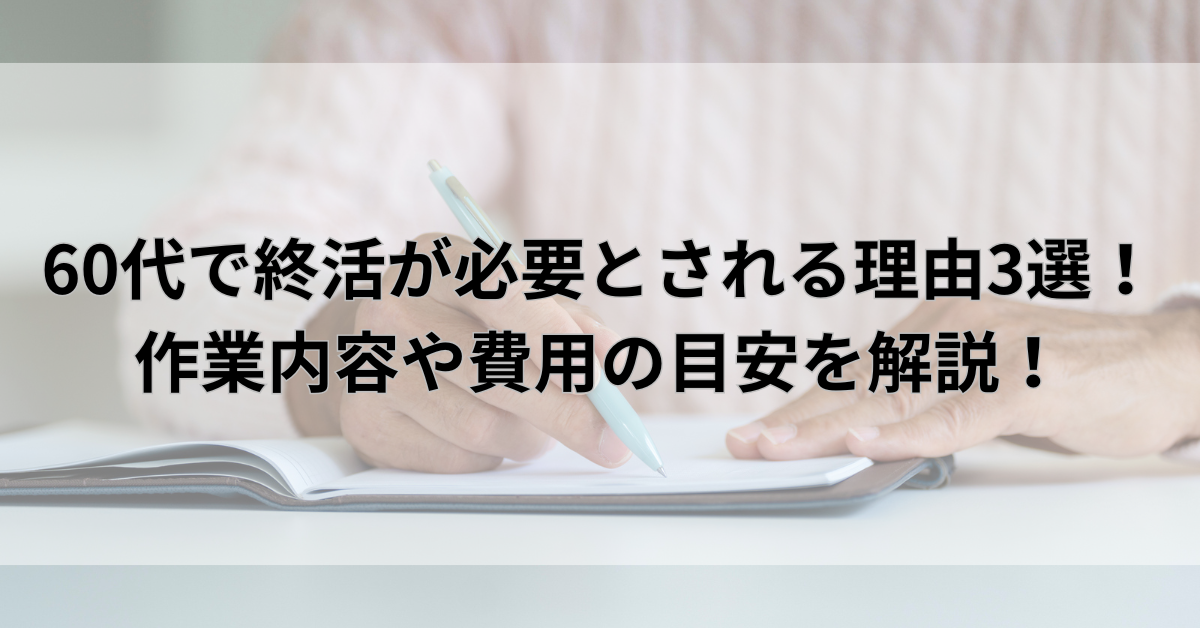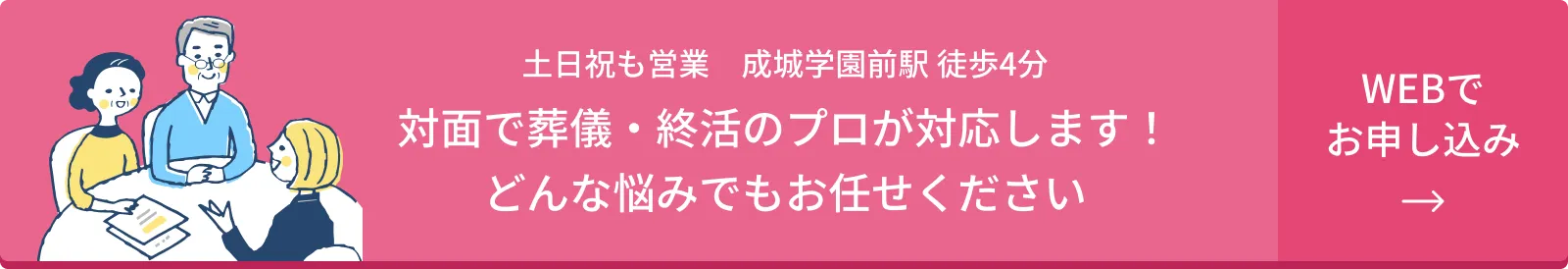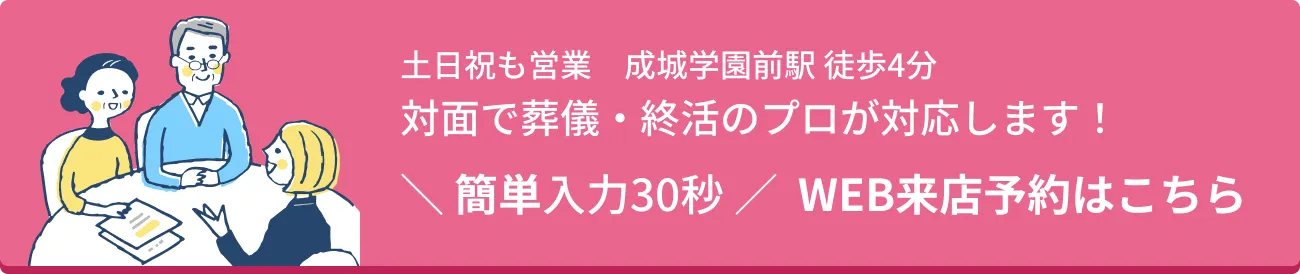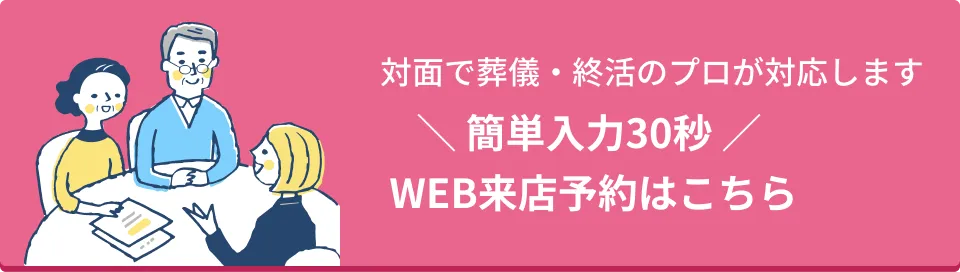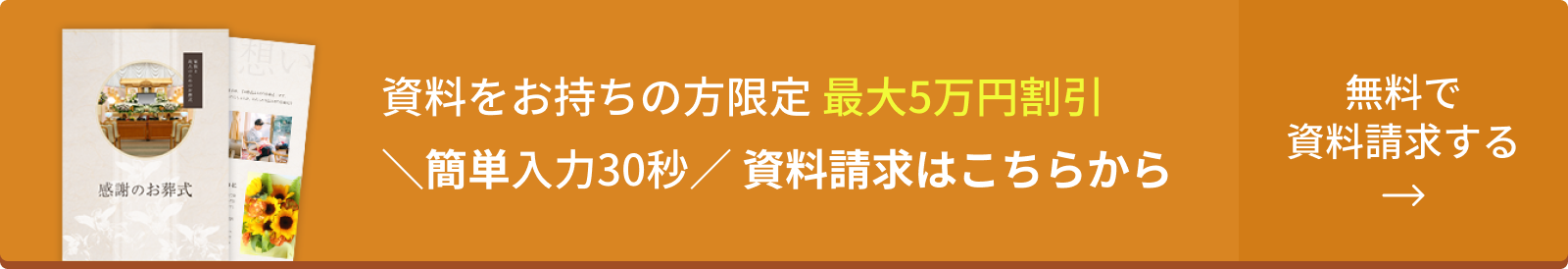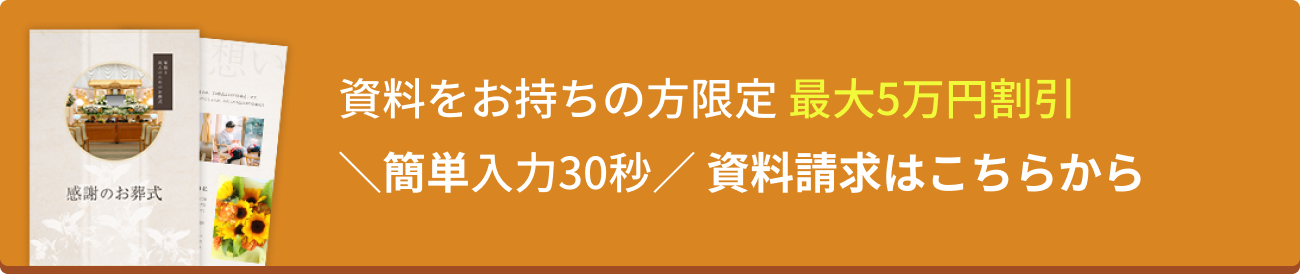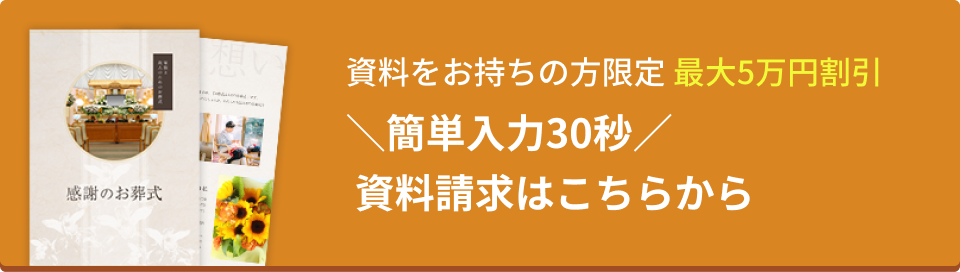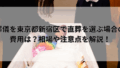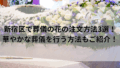60代になると、定年退職や老後の生活を意識し始める方が多いのではないでしょうか。
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、突然の病気や介護、葬儀などの備えが不十分だと、家族に大きな負担を残してしまう可能性があります。
その不安を解消するために役立つのが「終活」です。
エンディングノートの作成や財産整理、葬儀やお墓の準備などを60代から少しずつ進めておくことで、将来への不安を軽減し、安心した日々を過ごせるようになります。
この記事では、60代から始める終活の必要性ややるべきこと、費用の目安、失敗しないためのポイントをわかりやすく解説します。
最後まで読むことで、今すぐ行動に移せる終活の具体的なステップが理解でき、家族に安心を残す準備が整うでしょう。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。
60代で終活が必要とされる理由
老後の生活費と介護リスク、家族に迷惑をかけないための備え、心の整理としての終活の役割などの理由で終活が必要とされています。
- 老後の生活費と介護リスク
- 家族に迷惑をかけないための備え
- 心の整理としての終活の役割
老後の生活費と介護リスク
年齢を重ねるにつれて認知症などで判断能力が低下するリスクが高まり、健康状態が悪化すると、預金口座の凍結解除や不動産の売却、法的に有効な遺言書の作成などが困難になることがあります。
また、60代は親や配偶者の介護をする立場になる可能性が高い年代でもあります。
介護が必要になった際の住まいや、それに伴う費用について、元気なうちから検討しておくことが大切です。
退職後は年金が主な収入源となるため、貯蓄が枯渇するリスクを避けるためにも、老後の生活費、医療費、介護費、葬儀費用、お墓の費用などを具体的に計算し、経済的な安定を築くための計画が不可欠です。
家族に迷惑をかけないための備え
終活の重要な目的の一つは、自身の死後に家族にかかる精神的・経済的な負担を軽減することにあります。
もし事前準備がなければ、家族は故人を失った悲しみの中で、葬儀、埋葬、遺品整理、遺産相続といった多くの手続きに追われることになります。
故人の友人知人の連絡先が不明であったり、利用していた金融機関が特定できないといった問題が生じることもあり、これらを避けるためには、生前に必要な情報をまとめておくことが極めて重要です。
遺品整理や財産整理を事前に進めておくことで、家族は故人の思い出をゆっくりと振り返る時間を持つことができます。
また、遺産分割を巡る家族間のトラブルを未然に防ぐためにも、遺言書の作成や財産整理が有効な手段となります。
さらに、スマートフォンやパソコンに残されたデジタル遺品(データやSNSアカウントなど)の扱いについても、あらかじめ処分方法を検討しておくべきです。
心の整理としての終活の役割
終活は、単に人生の終焉を準備するだけでなく、残りの人生をいかに充実させるかを再考する貴重な機会でもあります。
自身の人生を振り返り、何に価値を置き、どのように日々を過ごしたいかを整理することで、将来への漠然とした不安が和らぎ、心穏やかな日常を送れるようになります。
「やりたいことリスト」を作成したり、新しい趣味に挑戦したりすることは、積極的に人生を楽しむためのきっかけとなります。
断捨離を通じて過去を振り返ることは、未来を生きる活力にもつながります。
また、自己を見つめ直し、今後の生活における意義や目標を明確にすることで、より充実した日々を送ることが可能になります。
身の回りのモノを減らすことは、気持ちを身軽にし、精神的なストレスの軽減にも寄与します。
終活を60代で始める際の作業内容
終活を60代で始める際の作業内容として、エンディングノートの作成、財産や相続の整理、葬儀やお墓の準備、医療や介護の意思表示、身の回りの断捨離があります。
- エンディングノートの作成
- 財産や相続の整理
- 葬儀やお墓の準備
- 医療や介護の意思表示
- 身の回りの断捨離
エンディングノートの作成
エンディングノートは、終活の記録帳として機能し、自分の基本情報、緊急連絡先、希望する葬儀の内容などを記すものです。
特に、医療や介護に関する意向、葬儀やお墓の希望、遺言の内容、財産や資産の詳細、重要な書類の保管場所、デジタルデータのパスワードのヒント、そして家族への感謝のメッセージなど、多岐にわたる情報をまとめることができます。
法的な拘束力は持ちませんが、家族に自身の意思を伝える非常に有効な手段です。
市販のノートやパソコンのテンプレートを活用できるほか、自分に合った形式で自由に手作りすることも可能です。
作成後は、エンディングノートの存在と保管場所を家族に明確に伝えておくことが肝心です。
メッセージバンクのようなデジタルでの作成・送信サービスも存在します。
財産や相続の整理
まずは、現在の自分の財産状況を正確に把握し、老後の生活に十分な資金があるかを確認することが重要です。
次に、遺言書を作成し、自身の財産を誰にどのように分与したいか、相続に関する具体的な意向を明確に示しておくべきです。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ法的な形式が定められているため、作成時には注意が必要です。
特に公正証書遺言は、専門家によって作成され公証役場で保管されるため、最も確実な方法とされています。
また、現在利用していない金融機関の口座は、遺族の相続手続きの負担を減らすためにも、早めに解約することをおすすめします。
財産の一覧表を作成し、生活に不可欠なもの、もしもの時に備えるもの、手放しても良いものなど、財産を分類して使い道を検討しましょう。
必要に応じて、弁護士、司法書士、税理士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家へ相談することも検討すべきです。
葬儀やお墓の準備
自分の葬儀に誰に参列してほしいか、斎場の規模や場所、希望する宗教や宗派、火葬後の遺骨の供養方法など、具体的な希望を検討しておくべきです。
これらの要望やこだわりがある場合は、事前に家族や親しい人に伝えておくことが大切です。
生前予約を受け付けている葬祭会社や霊園に相談し、事前に予約をしておくことは、残される家族の精神的・経済的負担を軽減する良い方法です。
その際は、業者名や連絡先を必ず家族に共有しておきましょう。
お墓に関する選択肢も多様化しており、墓じまいや散骨といった「お墓を持たない」供養方法も検討できます。
その他にも、新しいお墓を建てる、納骨堂や樹木葬などの永代供養墓を契約する、遺骨を自宅で手元供養するといった選択肢があります。
医療や介護の意思表示
病気の際の延命措置の要否、臓器提供の意思、将来介護が必要になった場合に自宅と施設のどちらを希望するかなど、自身の医療や介護に関する具体的な意向を家族に伝えておくことが重要です。
認知症などで自己判断能力が低下する前に、これらの意思を明確にしておくことで、いざという時の家族の大きな精神的負担を軽減できます。
また、判断能力が不十分な人を保護するための後見制度(法定後見制度、任意後見制度)の利用を検討することも有効です。
特に任意後見契約は、判断能力が衰える前に、将来誰に、どのような権限で判断を依頼するかを事前に決めておく制度です。
さらに、死後事務委任契約を結んでおくことで、自身の死後に発生する様々な手続きや届け出を専門家などに依頼することができます。
身の回りの断捨離
不要な物を処分し、身の回りの整理を進めることは、日々の生活を快適にするだけでなく、万が一の際の家族の遺品整理の負担を大幅に軽減します。
スマートフォンやパソコンに保存されているデジタル遺品についても、その処分方法を検討しておくべきです。
具体的には、1年以上使用していない物、今後使う予定がない物、見ることで気分が落ち込む物、住居スペースを圧迫している物、家族に遺したくない物、電子化できる物などを断捨離の対象とすると良いでしょう。
一方で、重要な書類や資料、写真・思い出の品(デジタル化を推奨)、日常生活に不可欠なもの、使用目的が明確なもの、価値のある骨董品やコレクション品、緊急時に必要となる防災グッズ、故人の遺品や形見、他人から借りているものや共有物、寄付が可能な物品、そして薬や衛生用品などは、安易に処分すべきではないとされています。
断捨離を進める際は、一度にすべてを終わらせようとせず、計画的に、無理のないペースで、適度な休憩を挟みながら進めることが大切です。
判断に迷うものは一時的に保留し、後で見直す選択肢も有効です。また、家族の持ち物を勝手に捨てることはトラブルの原因となるため、必ず本人に確認を取りましょう。
必要に応じて、不用品回収業者や生前整理業者といった専門家の協力を得ることも検討すると良いでしょう。
終活で60代にかかる費用の目安
終活を60代で始める際のかかる費用について、葬儀やお墓にかかる費用、相続や遺言書作成の費用、断捨離や不用品処分の費用をそれぞれご紹介。
- 葬儀・お墓にかかる費用
- 相続や遺言書作成の費用
- 断捨離や不用品処分の費用
葬儀・お墓にかかる費用
葬儀にかかる費用は、選択する葬儀のスタイルによって大きく異なります。
一般葬、家族葬、一日葬、直葬といった形式があり、それぞれの希望に応じて費用が変わるため、事前に複数の葬儀プランを調べておくことが重要です。
生前予約や見積もりを事前に取ることで、予期せぬ出費を抑えることが可能になります。
お墓についても、継承墓、永代供養墓、樹木墓などの種類や、新しいお墓を建立するかどうかによって費用が発生します。
また、現在のお墓を閉じる「墓じまい」を選択する場合にも費用がかかることがあります。
生前に自分のお墓を建てる「寿陵」は、相続税がかからないという利点も指摘されています。
相続や遺言書作成の費用
遺言書の作成を弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合(特に公正証書遺言の作成など)には、費用が発生します。
また、財産や相続に関する相談を専門家(税理士、ファイナンシャルプランナーなど)に行う場合も、相談料がかかることがあります。
遺産相続時の税金対策や、資産運用に関するアドバイスを受ける際にも、費用が発生する場合があります。
断捨離や不用品処分の費用
大規模な断捨離や不用品の処分で、不用品回収業者や生前整理業者に依頼する場合には、そのサービス利用に費用が発生します。
業者の料金は、部屋の広さや処分する物の量、契約内容によって変動するため、複数の業者から見積もりを取って比較検討することが推奨されます。
自分で計画的に断捨離を進めることで、業者に依頼する費用を節約することも可能です。
終活を60代で成功させるポイント
終活を60代で初めて成功させるためのポイントとしては、無理なく段階的に進める、家族との共有を忘れない、専門家に相談するなどがあります。
- 無理なく段階的に進める
- 家族との共有を忘れない
- 専門家に相談する
無理なく段階的に進める
終活は、一度に全てを完結させようとすると、疲弊して途中で挫折してしまう可能性があります。
そのため、「今日は引き出し一つだけ」「今週は本棚一列だけ」といった小さな目標を設定し、継続可能なペースで段階的に進めることが成功の鍵です。
特に、断捨離は玄関や洗面所のような小さなスペースから始めることで、達成感を味わいやすく、モチベーションを維持しやすくなります。
作業中は適度な休憩を挟みながら、無理なく進めることが重要です。
家族との共有を忘れない
終活は、自分一人の努力だけでは完結できません。
自身の終活の進捗状況や内容を家族や大切な人に事前に伝え、理解と協力を得ることが不可欠です。
特に配偶者がいる場合は、介護や葬儀など、夫婦双方に関わる事柄について、共に話し合い、足並みを揃えて進めることが理想的です。
ただし、医療や介護に関する個人の希望は尊重しつつ、意見の相違がある場合も考慮して話し合いを進めるべきです。
家族の持ち物を勝手に処分することはトラブルの原因となるため、思い出の品やデジタル遺品なども含め、必ず確認を取ってから判断しましょう。
エンディングノートや遺言書の存在と保管場所は、家族に確実に伝えておくことが大切です。
専門家に相談する
財産や相続の管理、遺言書の作成といった専門的な知識を要する事柄については、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することを強く推奨します。
終活セミナーやイベントに参加することで、有益な情報収集や専門家による個別相談の機会を得られます。
また、不用品の処分で困った際には、不用品回収業者や生前整理業者などのプロに依頼することも有効な手段です。
終活を60代で始める際によくあるQ&A
終活を60代で始める際によくある質問をご紹介。
まだ元気なのに始めるのは早い?
60代で終活を始めることは、決して早すぎるということはなく、むしろ「早くもなく遅くもない、最適なタイミング」であると広く認識されています。
専門家の意見では、心身ともに健康で、冷静な判断ができる「今」こそが、終活を始める理想的な時期とされています。
体力や判断能力が低下してからでは、重要な決定や手続きが困難になるリスクが高まります。
60代は定年退職を迎え、仕事に一区切りがつくことで時間に余裕が生まれるため、自身の人生をじっくりと見つめ直し、終活に取り組む絶好の機会です。
終活は「死の準備」ではなく、「残りの人生を自分らしく豊かに生きるための、前向きな準備」であるという認識が大切です。
費用をかけずに進める方法はある?
終活を費用を抑えて進める方法はいくつか存在します。
例えば、エンディングノートは市販品を購入するだけでなく、自分自身で手作りすることも可能です。
断捨離は、自分で計画的に進めることで、専門の業者に依頼する費用を削減できます。
また、不要なものをリサイクルショップやフリマアプリなどを利用して売却することで、臨時収入を得られる場合もあります。
まだ使えるものであれば、寄付団体に寄付することで、処分費用をかけずに社会貢献もできます。
終活に関するイベントやセミナーの中には、無料で参加できるものもあるため、積極的に情報収集に活用するのも良いでしょう。
老後資金計画においては、年金受給額の確認や保険の見直しを行うことで、経済的な見通しを立てることができます。
家族に終活の話を切り出すコツは?
家族に終活の話を切り出す際は、彼らの理解と協力を得ることが不可欠です。
まずは、自身が終活に取り組む意思があることを明確に伝え、事前に話し合いの場を持つことが重要です。
もし親の介護や看取りを経験したことがある場合は、その経験から自身の終活の必要性を話すことが、家族にとって受け入れやすいきっかけとなることがあります。
また、「残された家族に迷惑をかけたくない」という思いを素直に伝えることも有効です。
配偶者がいる場合は、介護や葬儀、財産など、夫婦双方に関わる事柄について、一緒に話し合う機会を設けることが理想的です。
ただし、医療や終末期医療、臓器移植に関する希望など、個人の意思は夫婦間でも異なる場合があるため、お互いの意思を尊重しながら進めることが大切です。
記事全体のまとめ
60代は、人生の大きな節目である定年退職を迎え、平均余命も長いことから、自身のセカンドライフを豊かにするための終活に最適な時期です。
体力や判断能力が充実しているうちに終活を始めることは、将来の不測の事態に備え、自分自身の不安を軽減し、残される家族の負担を大きく減らすことにつながります。
60代からの終活は、残りの人生を自分らしく、心豊かに生きるための準備であり、未来への投資と捉え、今日からできることから始めてみましょう


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。