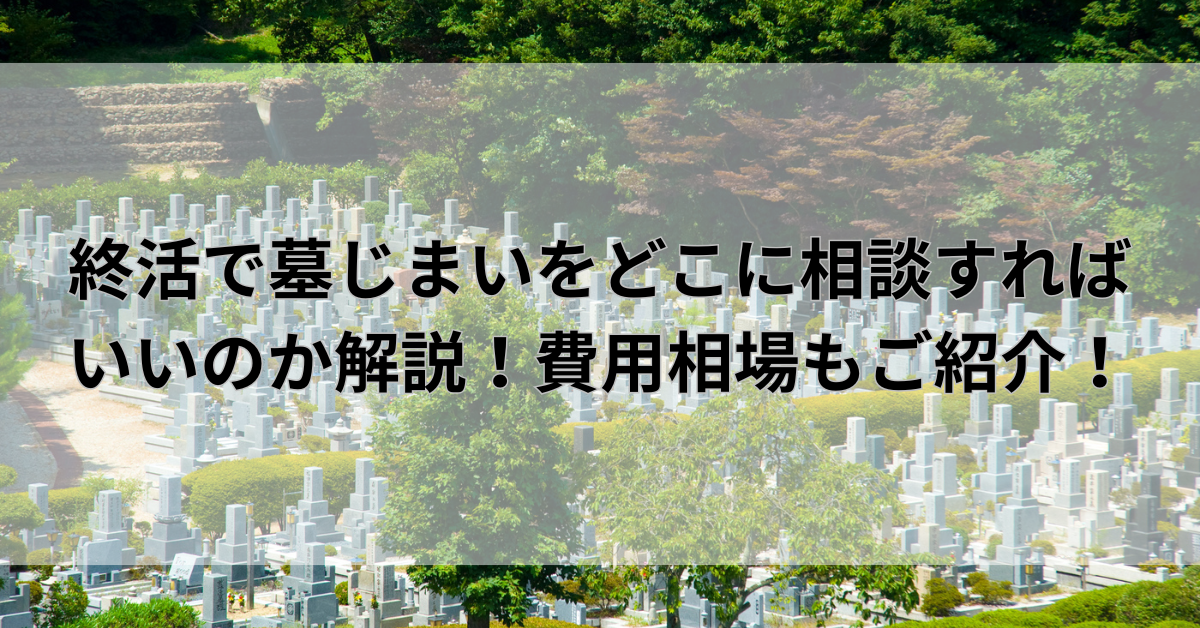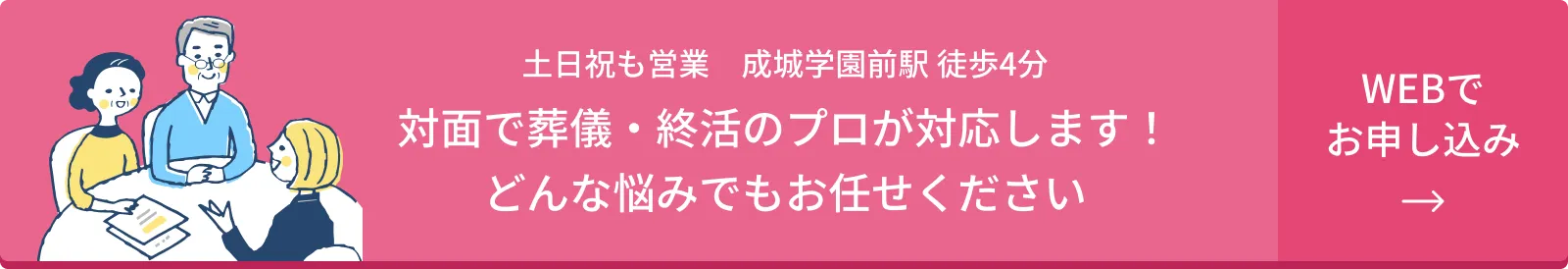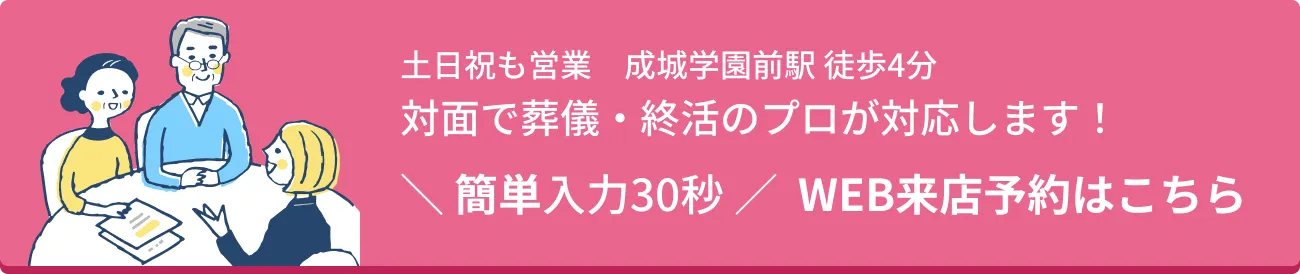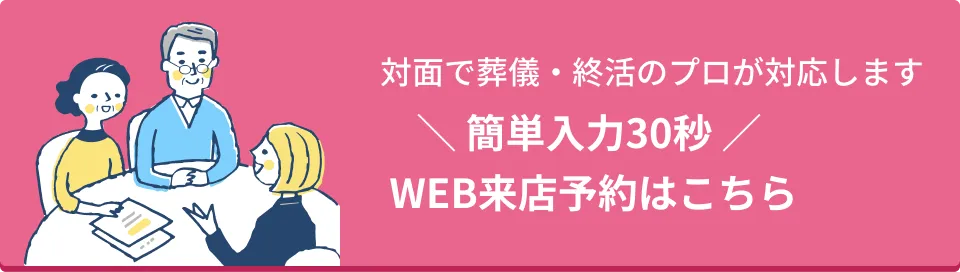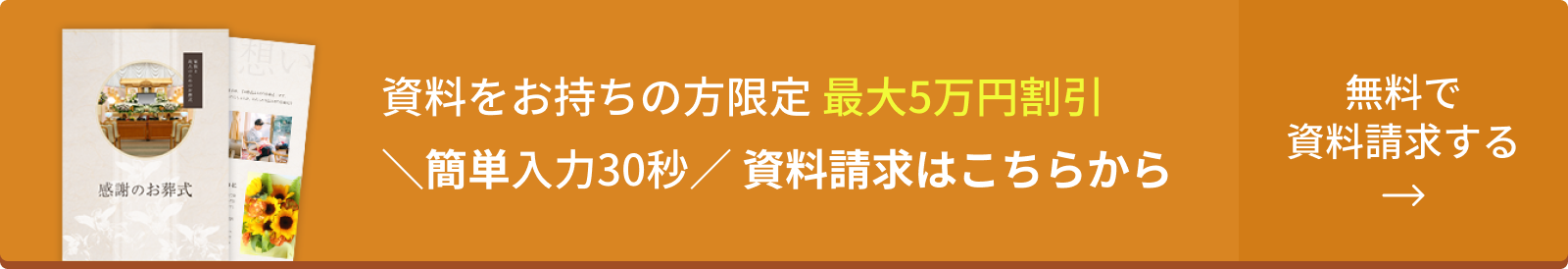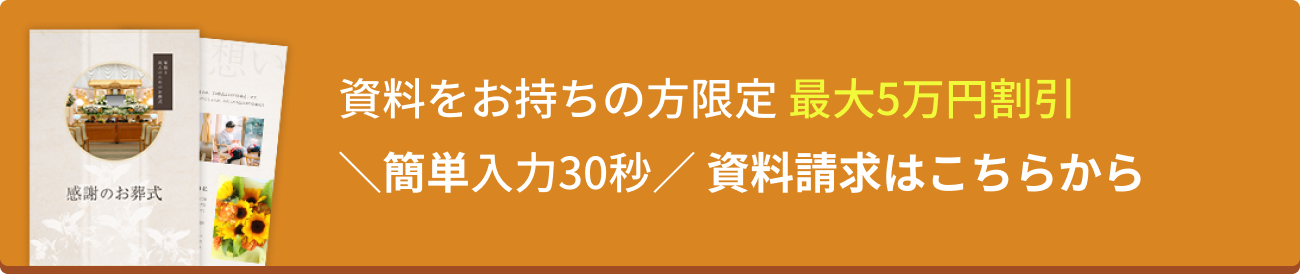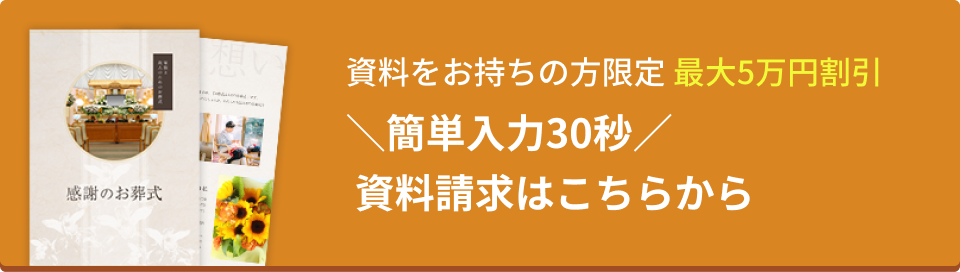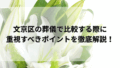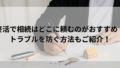お墓の維持や管理に悩みを抱える方は年々増えています。
特に高齢になり、遠方のお墓に通うのが難しくなると「子どもに負担をかけたくない」と考える方も多いのではないでしょうか。
そんなとき選択肢のひとつとなるのが「墓じまい」です。
墓じまいを進めることで維持費や管理の不安を解消し、安心して終活を進められます。
しかし実際には「どんな流れで行うのか」「費用はどれくらい必要か」「遺骨はどうすればよいか」といった疑問が多く、具体的な情報がないと一歩を踏み出しにくいものです。
本記事では、墓じまいを検討する方のために、流れや費用の相場、供養方法、よくある疑問と解決策をわかりやすく解説します。
読み進めることで、墓じまいに関する不安を解消し、子どもや家族に安心を残すための具体的な行動が見えてくるはずです。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。
終活の墓じまいを考える人が増えている背景
近年、終活の一環としてお墓のあり方を見直す人が増加しています。
従来の「先祖代々のお墓を守る」という考え方から、個人の価値観やライフスタイルに合わせた供養方法へと意識が変化していることが背景にあります。
- お墓の維持管理の負担が大きい理由
- 遠方にお墓がある場合の問題点
- 少子化や核家族化による影響
お墓の維持管理の負担が大きい理由
お墓を持つことには、経済的および労力的な負担が伴います。
墓石の購入費用や永代使用料といった初期費用に加え、年間管理料が毎年発生します。
また、寺院墓地を利用している場合は、檀家としての付き合いや、お寺の修繕費としてのお布施など、別途費用がかかることもあります。
さらに、定期的なお墓参りや清掃、草むしりなどの物理的な管理作業も、多くの人にとって大きな負担となっています。
遠方にお墓がある場合の問題点
現代社会では、実家を離れて都市部に住む人が多いため、遠方にお墓があると頻繁なお墓参りが困難になります。
お盆やお彼岸などの限られた機会にしか帰省できない場合、そのたびに交通費や宿泊費がかさむことも少なくありません。
また、年齢を重ねるにつれて、遠距離移動や重労働であるお墓の管理が身体的な負担となり、継続が難しくなるという問題も生じます。
少子化や核家族化による影響
少子高齢化や核家族化の進展も、墓じまいを検討する大きな要因です。
お墓を継ぐ人がいない、あるいはいても一人で複数のお墓を管理しなければならないケースが増えています。
子どもたちに「お墓の面倒をかけたくない」という親世代の思いから、自身が元気なうちに墓じまいを行い、次の世代に負担を残さないよう考える人が増えているのです。
終活の墓じまいの流れを理解する
終活として墓じまいを進めるには、事前の準備と正確な手続きが不可欠です。
円滑に進めるためには、全体の流れを把握しておくことが重要です。
- 墓じまい前に確認すべきこと
- 改葬許可申請の手続き方法
- 遺骨の移転先を決めるポイント
墓じまい前に確認すべきこと
墓じまいを検討する際は、まずご家族やご親族にその意思を伝え、同意を得ることが最も大切です。
親族間の合意がないまま進めると、後々トラブルに発展する可能性があります。
また、現在お墓を管理している寺院や霊園にも事前に相談し、墓じまいの意向を伝える必要があります。
特に寺院墓地の場合は、一方的な決定ではなく、相談という形で話を切り出すことが円満な解決につながります。
改葬許可申請の手続き方法
墓じまいによって遺骨を他のお墓に移す「改葬」を行う場合、行政手続きが必要です。
具体的には、現在のお墓の管理者から「埋葬証明書」、新しいお墓の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。
これらの書類を揃え、現在のお墓がある市区町村役場に「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」の交付を受けます。
手元供養や散骨を選ぶ場合は、基本的に改葬許可証は不要ですが、依頼する業者によっては提出を求められることがあるため、事前に確認が必要です。
実際の流れや必要な書類については墓じまいを依頼する葬儀社などの担当者に必ず確認をしておきましょう。
遺骨の移転先を決めるポイント
墓じまい後の遺骨の移転先は多岐にわたります。
永代供養墓(合祀墓、集合墓、個別型など)、納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養などが主な選択肢です。
それぞれの供養方法には、費用、管理体制、アクセス、宗教・宗派の条件などが異なります。
故人や遺族の希望、経済状況、お参りの頻度などを考慮し、家族でよく話し合って最適な方法を選ぶことが重要です。
終活の墓じまいにかかる費用の相場
墓じまいには様々な費用が発生し、総額は数十万円から数百万円と幅があります。
費用を事前に把握し、準備しておくことが重要です。
- 墓石撤去や工事費用の目安
- 改葬にかかる行政手続き費用
- 遺骨の移転先ごとの費用比較
墓石撤去や工事費用の目安
墓じまいの中心となるのは、墓石の撤去と墓地の更地化にかかる費用です。
墓石の解体工事費は、広さによって異なりますが、一般的に1平方メートルあたり8万円から10万円程度が目安とされています。
これに加えて、お墓から魂を抜く「閉眼供養(魂抜き)」のためのお布施として1万円から5万円程度、寺院墓地の場合はお寺との関係を解消する「離檀料」として1万円から20万円程度が必要となることがあります。
改葬にかかる行政手続き費用
改葬許可申請自体にかかる手数料は比較的少額ですが、行政書士などの専門家に手続き代行を依頼する場合は、別途費用が発生します。
これらの費用は、依頼する事務所や手続きの複雑さによって異なります。
遺骨の移転先ごとの費用比較
墓じまい後の遺骨の供養先によっても費用は大きく異なります。
散骨
3万円から30万円程度。業者に全て委託する場合は3万円程度から、家族が乗船して行う場合は10万円以上かかることが多いです。
手元供養
1万円から30万円程度ですが、ミニ骨壺やアクセサリーへの加工には費用が高くなる傾向にあります。
合祀墓(合葬墓)
3万円から30万円程度。費用を抑えたい場合に選ばれることが多く、永代供養料として10万円からというところもあります。
樹木葬
3万円から150万円程度。合祀型は比較的安価ですが、個別の区画を選ぶと費用は高くなります。
納骨堂
10万円から200万円程度。ロッカー型、自動搬送型、仏壇型など種類が多く、設備や個別安置期間によって価格が変動します。
個別型の永代供養墓(墓石あり)
50万円から150万円程度。一般的なお墓に近い形式で、費用もそれに準じます。
これらの費用はあくまで目安であり、実際の金額は選択する施設やサービス内容によって大きく変動するため、複数の業者から見積もりを取り比較検討することが推奨されます。
終活の墓じまい後の供養の方法
墓じまいを終えた後、故人の遺骨をどのように供養するかは、終活における重要な選択です。
多様な供養方法から、自分や家族の希望に合ったものを選ぶことができます。
- 永代供養を選ぶ場合の特徴
- 樹木葬や納骨堂という選択肢
- 手元供養や散骨のメリットと注意点
永代供養を選ぶ場合の特徴
永代供養とは、寺院や霊園といった管理者が、遺族に代わって長期的に遺骨の管理と供養を行う形式です。
多くの場合、契約時に費用を支払えば、その後の年間管理料は不要となるため、将来的な負担を軽減できます。
承継者を必要としないため、お墓の継承問題に悩む人にとって非常に魅力的な選択肢です。
ただし、多くの永代供養では、一定期間(例えば三十三回忌まで)個別で供養された後、他の遺骨と一緒に合祀墓に移されるのが一般的です。
また、宗教や宗派を問わず利用できる場所が多いですが、一部には条件がある場合もあるため、事前に確認が必要です。
樹木葬や納骨堂という選択肢
樹木葬や納骨堂という選択肢もあります。
樹木葬
墓石の代わりに樹木や草花を墓標として遺骨を埋葬する、自然志向の供養方法です。
故人が生前自然を愛していた場合や、「自然に還りたい」という願いを持つ人に選ばれています。
永代供養が付いていることが多く、継承者の心配が不要で、費用も一般的なお墓に比べて抑えられる傾向にあります。
合祀型、集合型、個別型があり、合祀型を選ぶと遺骨を後から取り出すことはできません。
納骨堂
屋内の施設に遺骨を保管する供養方法です。ロッカー型、自動搬送型、仏壇型など、様々な形式があり、好みや予算に合わせて選べます。
永代供養付きの納骨堂も多く、継承者不要で利用できるメリットがあります。
屋内にあるため、天候に左右されず一年中お参りできる点も特徴です。
都市部に多く見られ、アクセスが良い場所にあることが多いです。樹木葬と同様に、一定期間後に合祀されるプランが一般的です。
手元供養や散骨のメリットと注意点
手元供養や散骨のメリットと注意点をご紹介していきます。
手元供養
故人の遺骨の一部または全てを自宅に保管して供養する方法で、故人を常に身近に感じられるという精神的なメリットがあります。
骨壺に納めて自宅に安置したり、加工してペンダントなどのアクセサリーとして身に着けたりすることも可能です。
費用は無料から30万円程度と幅広く、手軽に始められますが、最終的に遺骨をどうするか、本人が亡くなった後のことを考慮しておく必要があります。
遺骨加工品も法的には遺骨と同様に扱われる可能性があるため、注意が必要です。
散骨
粉末状にした故人の遺骨を、海や山などの自然環境に撒いて供養する方法です。
故人の「大自然に還りたい」という願いを叶えることができ、お墓を持たないため維持管理費がかからないというメリットがあります。
しかし、一度散骨してしまうと遺骨は二度と取り戻せないため、この点を十分に理解しておく必要があります。
また、個人で勝手に散骨を行うと法律や条例に触れる可能性があるため、散骨専門の業者に依頼しましょう。
親族の同意も非常に重要であり、トラブルを避けるためにも事前の話し合いが不可欠です。
終活の墓じまいでよくあるQ&A
終活の墓じまいでよくあるQ&Aをご紹介。
墓じまいにはどのくらいの期間が必要か
墓じまいには、様々な手続きが必要となるため、今日明日で完了するものではありません。
親族との話し合いから始まり、新しい供養先の選定、行政手続き、墓石の撤去工事、そして新しい供養先への納骨までの一連の流れには、通常、数ヶ月から半年程度の余裕を見ておくことが推奨されます。
親族が反対する場合の対応策
墓じまいにおいて親族の反対は、しばしば起こりうる問題です。
最も重要なのは、ご自身の意思や希望を事前に家族や親族に伝え、理解と同意を得ることです。
エンディングノートや遺言書に自分の明確な意思を残しておくことも有効な手段です。
また、親族の意見を考慮し、遺骨の一部を分骨して手元供養にするなど、双方にとって納得できる折衷案を検討することも有効です。
必要であれば、行政書士などの専門家に相談し、第三者を交えて話し合いを進めることも検討しましょう。
自分で手続きを進められるか
墓じまいの一連の手続きは、自分自身で進めることも可能ですが、非常に煩雑で手間がかかる場合があります。
墓地管理者との交渉、石材店の選定、行政への改葬許可申請など、各段階で専門的な知識と時間が必要です。
これらの手続きを負担に感じる場合は、墓じまい代行業者や行政書士、葬儀社などの専門家に依頼することも可能です。
不明な点があれば、遠慮なく担当者に質問し、納得した上で進めることが大切です。
記事全体のまとめ
終活における墓じまいは、現代の多様なライフスタイルや価値観の変化に伴い、ますます多くの人が検討する重要なテーマとなっています。
墓じまいの手続きは複雑な場合もあるため、必要に応じて専門家(行政書士、葬儀社など)のサポートを得ることも有効な手段です。
ご自身の終活を「残される家族への優しさ」として捉え、後悔のない選択をするために、早めの情報収集と計画的な準備をおすすめします。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。