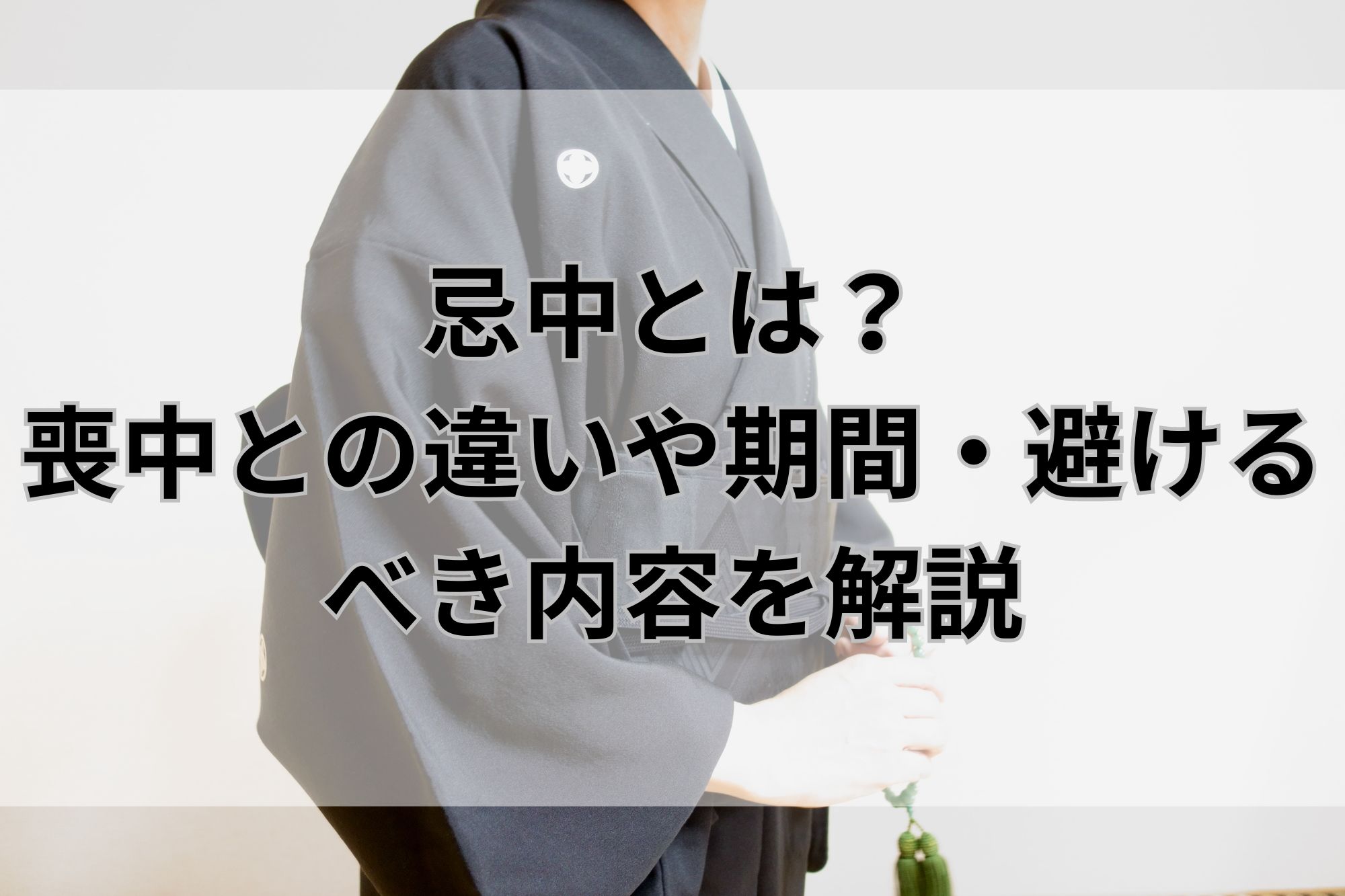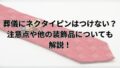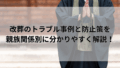近親者の死去により、喪主として葬儀を執り行ったあなた。
その後の生活で「忌中」と「喪中」の違いや、それぞれの期間中に避けるべき行動について悩んでいませんか?
例えば、年賀状の送付や新年の挨拶、贈り物のタイミングなど、知らずに行動した結果マナー違反にならないように注意したいところです。
本記事では、忌中と喪中の定義や期間、避けるべき行動について、具体的なケーススタディを交えて解説します。
これを読むことで、周囲との関係を良好に保ちつつ、故人を偲ぶ時間を大切にすることができます。
また、法事などの法要は感謝のお葬式に、遺品整理などの作業はぜひ感謝の遺品整理にお任せください!
「感謝の遺品整理」は、東京・埼玉・神奈川・千葉を対象に、遺品の整理から買取までワンストップで対応するサービスで、出張費や査定費は無料、価値のある品は適正に査定して高額買取を実現します。
忌中とはどんな期間か?意味や目的を解説
「忌中(きちゅう)」とは、故人が亡くなってから四十九日(満中陰)までの期間を指す言葉です。
主に仏教における考え方で、故人の魂があの世へ旅立つまでの間、遺族が故人の死を悼み、清らかな環境で過ごすために設けられた期間とされています。
この期間中は、神道では「穢れ(けがれ)」があるとされ、神社への参拝など神事への参加が避けられます。
仏教でも、故人の供養に集中するため、祝い事への参加やお酒を伴う会合などを控えるのが一般的です。
忌中の長さは、宗派や地域によって異なりますが、仏教では「死後49日間」が目安とされ、「七七日忌(しちしちにちき/なななぬか)」として区切られる法要が一般的です。
喪中とはどんな期間か?忌中との違いとは
一方の「喪中(もちゅう)」とは、故人を偲びながら生活を送る一定の期間を指します。
一般的には親族が亡くなってから1年間を喪中とする場合が多いですが、これはあくまでも慣習によるもので、法律的な定義があるわけではありません。
喪中の目的は、故人との別れを悼み、心の整理を行う期間を設けることにあります。
日常生活は通常通り送りますが、慶事(結婚式、正月行事、賀詞など)への参加や実施は控えるべきとされています。
忌中が「宗教的な穢れを避ける期間」であるのに対し、喪中は「社会的な礼儀として故人を悼む期間」であるという違いがあります。
また、忌中は基本的に四十九日で終わるのに対して、喪中は一年を目安にするのが一般的です。
忌中と喪中の違いとは?期間・目的・行動マナーを比較
「忌中(きちゅう)」と「喪中(もちゅう)」は、どちらも故人を悼む期間を指しますが、その意味や期間、行動上のマナーには明確な違いがあります。
期間
まず「忌中」は、仏教における四十九日(七七日忌)までの期間を指します。
この間は、故人の霊が成仏の道をたどるとされ、遺族は身を慎み、供養に集中する期間とされています。
また、神道では死を「穢れ(けがれ)」とみなし、忌中は神社への参拝など神事を控えるべき期間とされています。
一方「喪中」は、忌中よりも長い、一般的に1年間の期間を指し、故人との別れを受け入れながら、社会的にも哀悼の意を示すための期間です。
喪中の間は日常生活は送れるものの、年賀状を控える、祝い事への出席を見送るなど、慶事を避けるのがマナーとされています。
つまり、忌中は「宗教的な意味合い」が強く、喪中は「社会的なマナー」の側面が強いという違いがあります。
避けるべき行動
忌中と喪中では、避けるべき行動にも違いがあります。
忌中の間は、以下のような行動を控えるべきとされています。
忌中
忌中では、主に下記のようなことを避けましょう。
- 神社への参拝
- 結婚式やお祝い事への参加
- 飲酒を伴う会食やパーティー
- 年始の挨拶、年賀状のやり取り
- 正月飾りや門松、鏡餅の設置
このように忌中は、宗教的な配慮の元、外部との慶事的な関わりを完全に避けることが一般的です。
仏教ではこの期間に供養の法要を重ね、四十九日の忌明け法要をもって「忌中が明ける」とされます。
喪中
一方、喪中は、日常生活を送りながらも、次のような行動を控えるのがマナーとされます。
- 年賀状の送付や正月のお祝い
- 結婚式・誕生日パーティーなどの慶事
- 派手な服装や華やかな装飾
- 祝い酒や宴会の主催・参加
喪中の期間中に届いた年賀状に対しては、「寒中見舞い」としてお返しをするのが礼儀です。
また、喪中期間中でも、やむを得ず慶事に参加する場合は、控えめな装いを心がけ、簡潔に対応するなどの配慮が求められます。
忌中と喪中でマナーが異なる理由とは
忌中と喪中のマナーが異なる背景には、宗教や文化、そして社会的な変化があります。
忌中は仏教や神道における「死の穢れ」や「故人の魂の浄化」を目的とした、宗教的な意味合いが強いものです。
そのため、信仰を重んじる家庭や地域では、今でも厳格に忌中のしきたりが守られています。
一方、喪中はより「社会的・文化的なマナー」に近い性質を持ちます。
故人に対する哀悼の意を示し、周囲にその旨を知らせることで、不用意な祝辞や挨拶が交わされることを防ぐ役割があります。
最近では、核家族化や宗教観の変化、地域差などにより、忌中・喪中に対する考え方にも個人差が大きくなってきています。
とはいえ、「知らなかった」では済まされない場面もあるため、基本的なマナーは押さえておくことが重要です。
忌中・喪中における年賀状と挨拶マナー
年末年始の挨拶や年賀状のマナーは、忌中・喪中期間中でも特に注意が必要です。
忌中の場合
忌中の間は、年賀状を出すことも受け取ることも控えるのが基本です。
もし年賀状が届いた場合は、1月7日以降に「寒中見舞い」として返信するのがマナーです。
また、職場での年始の挨拶についても、「喪中のためご挨拶は控えさせていただきます」とひと言添えると丁寧です。
喪中の場合
喪中はがきを出すことで、年賀状を辞退する意向を相手に伝えるのが慣例です。
タイミングとしては、11月中旬から12月初旬までに出すのが望ましいとされています。
喪中はがきには「本年中に○○が永眠いたしましたため、年頭のご挨拶を控えさせていただきます」などの文言がよく使われます
受け取る側も、それを踏まえて賀詞を控えるようにしましょう。
忌中・喪中のケース別対応例
忌中や喪中などでケース別対応例を3つご紹介していきます。
忌中に初詣へ誘われたら?
忌中期間中は神社への参拝を避けるべきとされています。
初詣もその対象になるため、断るのが一般的ですが、やむを得ず行く場合は「仏教の考え方を優先して参拝する」など家族と相談の上決めましょう。
喪中に年賀状を受け取った場合
送った方が喪中を知らなかった場合、寒中見舞いで返信を出すのが丁寧です。
感謝の気持ちと喪中である旨を簡潔に伝えるとよいでしょう
喪中期間中に結婚式に招待された場合
参加するかどうかは状況によりますが、故人との関係性や親族の意向により判断します。
参加する場合は、派手な服装や余興を控え、祝辞なども簡潔にとどめる配慮が必要です。
記事全体のまとめ
「忌中」と「喪中」は似ているようで、その意味合いや対応方法が異なります。
忌中は、仏教や神道のしきたりに基づいた、より厳粛な期間であり、喪中は社会的マナーとしての意味合いが強い期間です。
これらを正しく理解し、状況に応じて適切に行動することが、故人への敬意を示すとともに、周囲との良好な関係を保つことにもつながります。
不安なときは、家族や親戚、信頼できる葬儀社などに相談しながら、自分にとって最適な弔い方を選んでください。