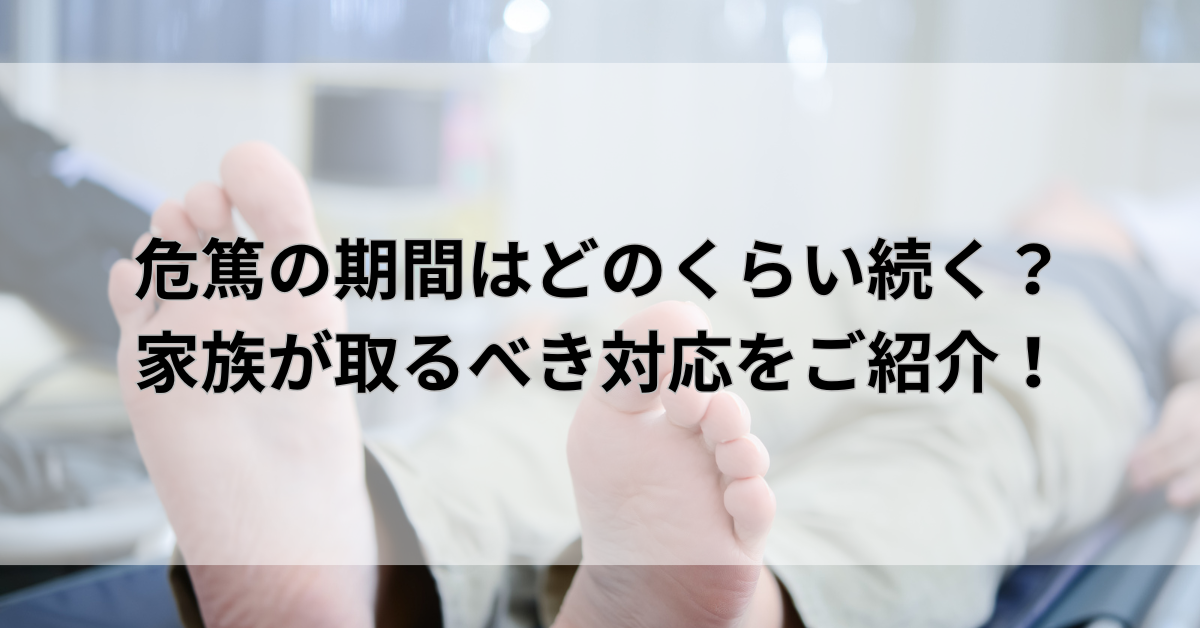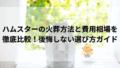突然「危篤」と告げられたとき、頭が真っ白になっていませんか。
この先どのくらいの期間続くのか、家族として何をすればいいのか、不安でいっぱいの方も多いでしょう。
この記事では、実際に経験した人たちの声をもとに、危篤状態が続く期間の目安や家族ができる準備、心の持ち方について詳しく解説します。
これを読むことで、限られた時間をどう過ごすべきかが見えてきます。
「何から手をつけたらいいの?」という方に向けて、すぐ行動に移せる情報をまとめました。
危篤の期間とはどんな状態なのか
危篤とは、病気や怪我の容体が非常に重く、命の危険が差し迫っており、回復の見込みがほとんどないと医師が判断した状態を指します。
危篤と言われるタイミングと意味、一般的な長さについてご紹介。
危篤と言われるタイミングと意味
危篤と言われる判断は、医師が患者の意識レベル、心拍数、呼吸の状態、その他のバイタルサインなど、様々な要素を総合的に見て行われます。
「危篤」と似た言葉に「重篤」がありますが、これらは意味合いが異なります。
「重篤」は、重い病状で死に至る危険性があるものの、まだ回復の可能性が残されている状態を示す言葉です。
一方、「危篤」は、回復が極めて困難で、患者がいつ亡くなってもおかしくない差し迫った状況であることを意味し、深刻さの度合いとしては危篤の方が重い状態であると考えられます。
医師から危篤を告げられるのは、通常、患者の最期の時が近いと判断され、家族や親しい人々を呼び集めるよう促される場合が多いです。
危篤期間の一般的な長さとパターン
危篤状態がどのくらい続くかについて、明確に「何分」「何日」と言い切れるものではなく、人によって大きく異なります。
一般的には、危篤と告げられてから数時間から2〜3日以内に亡くなるケースが多く見られます。
しかし、中には危篤状態が10日以上、あるいは数週間続くこともあります。
非常に稀なケースでは、数ヶ月や数年にわたって危篤状態が続くことや、一時的に回復して元の生活に戻ることもありますが、これはあくまで例外的な状況です。
危篤状態は、一時的に容体が落ち着き「小康状態」となることもありますが、これは完全な回復を意味するものではありません。
小康状態になった後も、再び危篤状態に陥るなど、状態が変動を繰り返す可能性があるため、引き続き注意深く見守る必要があります。
危篤の期間中に家族ができる対応
危篤の期間中に家族ができる対応として、心の準備と家族内での役割分担、職場への連絡と休みの取り方の工夫、緊急時に必要な持ち物リストと準備があります。
心の準備と家族内での役割分担
身近な人が危篤状態にあると知らされた場合、多くの方が動揺し、冷静でいられなくなるのは自然なことです。
しかし、危篤状態である時こそ、まずは深く深呼吸をして落ち着き、心の準備をすることが非常に重要です。
回復を願う気持ちを持ちつつも、最悪の事態(亡くなること)を想定しておく必要があります。
危篤期間中には、医療方針の決定や葬儀の準備など、大きな決断を迫られる可能性があります。
このような状況でパニックを避けるためにも、日頃から心の平静を保つ方法を見つけておくことが勧められます。
また、家族間で協力し、役割分担を決めることも大切です。
例えば、一人が病院に付き添い、別の家族が葬儀の準備を進めるなど、手分けして対応することで、一人の負担が重くなりすぎるのを防ぐことができます。
悲しみや不安な気持ちは一人で抱え込まず、家族や親しい人と共有し、お互いに支え合うことで、心の負担を軽減できるでしょう。
職場への連絡と休みの取り方の工夫
家族が危篤状態になった場合、勤めている方は速やかに職場に連絡を入れる必要があります。
これは、忌引休暇の対象とならないため、有給休暇や特別休暇などを利用して休むのが一般的です。
有給休暇の日数には限りがあるため、会社の就業規則を確認し、上司や人事担当者と相談することが重要です。
会社によっては、特別な休暇制度を設けている場合もあります。
危篤状態が長期化する可能性がある場合、定期的に職場に状況を報告し、必要に応じて休暇の延長や業務の引き継ぎについて相談しましょう。
自営業やフリーランスの場合は、クライアントや取引先への連絡、代理対応の依頼、納期延長の交渉などを検討し、緊急時の連絡体制を明確にしておくことが求められます。
また、お子さんがいる場合は、学校や園にも連絡を忘れずに入れるようにしましょう。
緊急時に必要な持ち物リストと準備
危篤の連絡を受けたら、可能な限り速やかに病院へ駆けつけることが大切です。
容体は予測できないため、少しでも長くそばにいられるように急ぐべきです。
病院での滞在が数日間続くことを想定し、あらかじめ京地電話と充電器、財布と現金、宿泊に対応できるもの、連絡先がわかるもの、メモ帳とペンなど必要な持ち物を準備しておくと安心です。
- 携帯電話と充電器
- 財布と現金
- 宿泊に対応できるもの
- 連絡先が分かるもの
- メモ帳とペン
携帯電話と充電器
連絡手段として必須です。
財布と現金
病院での飲食費や交通費、いざという時の入院費や治療費、遺体搬送費、葬儀費用などにまとまった現金が必要になる場合があります。
クレジットカードや電子マネーが使えない場面もあるため、現金を用意しておくと良いでしょう。
宿泊に対応できるもの
着替え(1〜2日分)、洗面用具、常備薬、コンタクトケースなど宿泊に対応できるものを用意しておくと安心です。
遠方から駆けつける場合は、葬儀の際に着用する喪服を持参することも検討すると良いでしょう。
連絡先が分かるもの
親戚や友人の連絡先リストも準備しておきましょう。
メモ帳とペン
医師の説明やその後の対応などを記録するために役立ちます。
危篤の期間が長い場合の対応について
危篤の期間が長い場合の対応について、注意点や周囲ができる声かけや付き添い方についてご紹介。
危篤の期間が長い場合の注意点について
危篤状態が長引く場合、医療スタッフとの密な連携、家族間での情報共有と協力、仕事や学校への対応、費用の準備、自身の心のケアの点に注意することが勧められます。
- 医療スタッフとの密な連携
- 家族間での情報共有と協力
- 仕事や学校への対応
- 費用の準備
- 自身の心のケア
医療スタッフとの密な連携
患者の病状や今後の見通しについて、常に医師や看護師から正確な情報を得るように努めましょう。
不明な点があれば、納得がいくまで質問することが大切です。
家族間での情報共有と協力
家族全員が現状を理解し、不安や悲しみを共有することが、精神的な負担を軽減する上で役立ちます。看病の分担や、必要に応じて外部のサポートも検討しましょう。
仕事や学校への対応
長期にわたる休暇が必要になる場合は、職場や学校に定期的に状況を報告し、業務の引き継ぎや休暇の調整について相談することが重要です。
費用の準備
入院費や医療費、そして将来的な葬儀費用など、まとまった現金が必要になる可能性が高いため、早めに準備を進めておくことが賢明です。
自身の心のケア
精神的、身体的に疲弊しないよう、適度な休息を取り、信頼できる人に話を聞いてもらうなど、自分自身の心の健康も大切にしましょう。
後悔のないお別れを迎えるためにも、無理のない範囲で最善を尽くすことが大切です。
周囲ができる声かけや付き添い方
患者の意識が朦朧としていても、聴覚は最期まで残っている可能性が高いと言われていますので、積極的に優しく話しかけ、感謝の気持ちやこれまでの思い出話などを伝えることが大切です。
静かに手を握ったり、好きだった音楽を流したりすることも、患者に安らぎを与えることにつながります。
一方で、ネガティブな言葉や死を連想させる言葉は避けるべきです。
例えば、「もうダメかもしれない」「ご愁傷様です」といった言葉は、患者や付き添う家族を傷つける可能性があります。
悲しい気持ちであっても、大声で騒いだり取り乱したりせず、病院内では静かに過ごし、他の患者やその家族への配慮を忘れないようにしましょう。
医療的な処置に関しては、患者本人の生前の意向(延命治療の有無など)や事前指示書がある場合は、それを尊重することが求められます。
医療チームと密に連携し、患者にとって最善のケアが行われるようサポートしましょう。
危篤の期間に関するよくある質問
危篤の期間に関するよくある質問をご紹介。
危篤状態から回復することはありますか?
危篤状態から完全に回復することは稀ですが、可能性はゼロではありません。
特に、怪我や事故が原因で危篤状態になった場合は、集中的な治療によって一時的に持ち直すケースが見られます。
また、患者の生命力や「生きたい」という強い意志が回復につながることもあると言われています。
意識が混濁していた患者が一時的に意識を取り戻し、元気な様子を見せる現象は「中治り現象」と呼ばれ、家族に希望や感謝を伝えた後に亡くなるケースもあります。
しかし、病気による衰弱や寿命が原因で危篤になった場合は、回復が難しいとされています。
危篤と診断されても、その後の状態は予測困難であり、一時的な回復があっても引き続き危険な状況であることには変わりありません。
危篤が長く続く場合どうすればよい?
危篤状態が長期間にわたって続くことは、付き添う家族にとって精神的、身体的に大きな負担となります。
長期間の危篤状態の場合どのような対応をする必要があるのかがご紹介。
- 医療スタッフとの継続的な情報共有
- 家族間の協力と役割分担
- 職場や学校への連絡と調整
- 経済的な準備
- 自身の心のケア
医療スタッフとの継続的な情報共有
患者の正確な病状や今後の見通しについて、医療スタッフから定期的に情報を受け取り、家族間で共有しましょう。
家族間の協力と役割分担
家族が複数いる場合は、交代で付き添うなど、看病の負担を分担することが重要です。お互いの体調を気遣い、無理のない範囲でサポートし合いましょう。
職場や学校への連絡と調整
長期休暇が必要になる可能性があるため、職場や学校には定期的に状況を伝え、業務の引き継ぎや休暇の延長について相談することが大切です。
経済的な準備
医療費だけでなく、葬儀費用なども含め、まとまった現金を事前に準備しておくことで、いざという時の金銭的な不安を軽減できます。
自身の心のケア
悲しみや疲労が重なる中で、自身の心の健康も忘れずにケアすることが重要です。
信頼できる家族や友人、または専門のカウンセラーに相談することも検討しましょう。
遠方に住む家族はすぐ来るべきですか?
危篤の連絡を受けたら、遠方に住む家族であっても可能な限り速やかに駆けつけることが強く推奨されます。
危篤状態はいつ容体が急変するか予測できないため、最後の瞬間に立ち会う機会を逃さないためにも、すぐに動くことが大切です。
連絡を受けた時点で、移動に時間がかかることを考慮し、優先して連絡を入れるべきです。
ただし、個々の事情(仕事、子どものこと、健康状態など)によっては、すぐに駆けつけることが難しい場合もあります。
そのような場合は、無理に病院に来るよう強く催促するのではなく、それぞれの状況を考慮した対応が求められます。
面会に制限が設けられている場合もありますので、病院のスタンスや現在の面会状況について、事前に確認しておくと良いでしょう。
海外に住む家族が危篤の場合には、パスポートやビザの確認、航空券の手配を急ぐとともに、現地の医療制度や死亡時の手続きについて在外公館に相談するなど、より入念な準備が必要になります。
病院に付き添う際は、数日間の宿泊に備え、着替えや常備薬、携帯電話の充電器、現金などの持ち物を用意しておくと安心です。
記事全体のまとめ
「危篤」 とは、病気や怪我により命の危険が差し迫り、回復の見込みがほとんどない状態を指す、医師による総合的な判断です。
危篤期間の長さは個人差が大きく、数時間から数日、あるいは数週間以上続くこともあります。
稀に一時的に持ち直すケースもありますが、基本的には死が近い状態であると理解し、心の準備をすることが重要です。
危篤の連絡を受けたら、まず冷静になり、深呼吸をして落ち着きましょう。
そのため、事前に葬儀社を選定し、葬儀の形式や予算について大まかな方針を決めておくなど、もしもの時に備えて準備をしておくことが、後悔のないお別れを迎えるための助けとなります