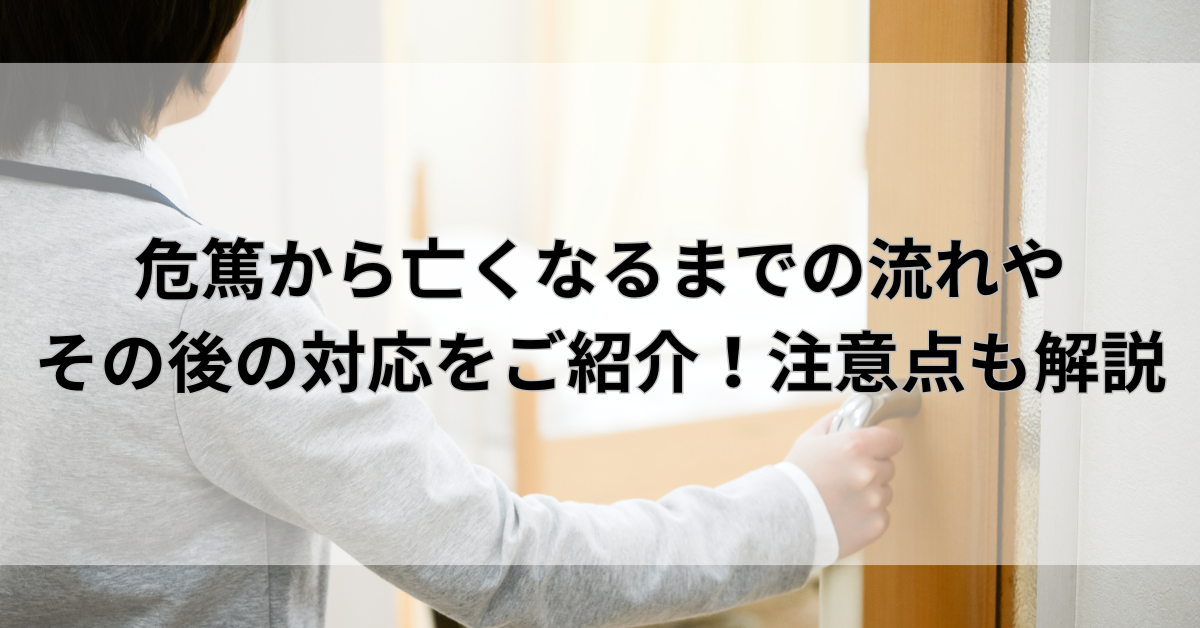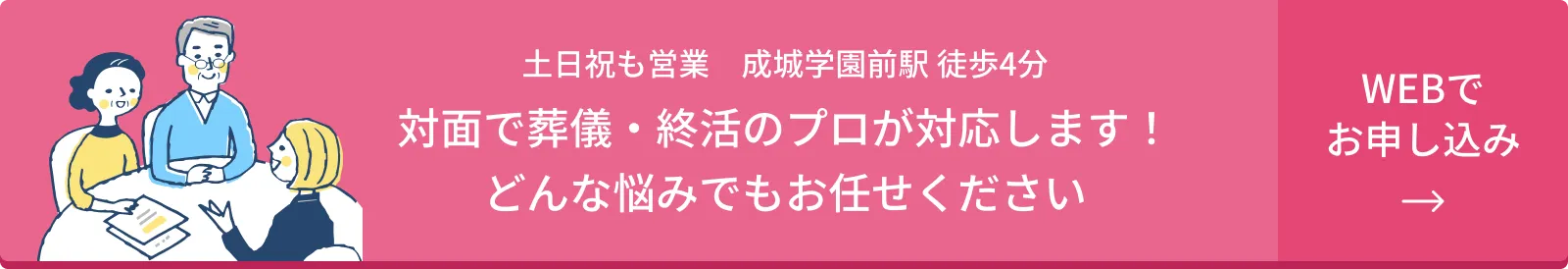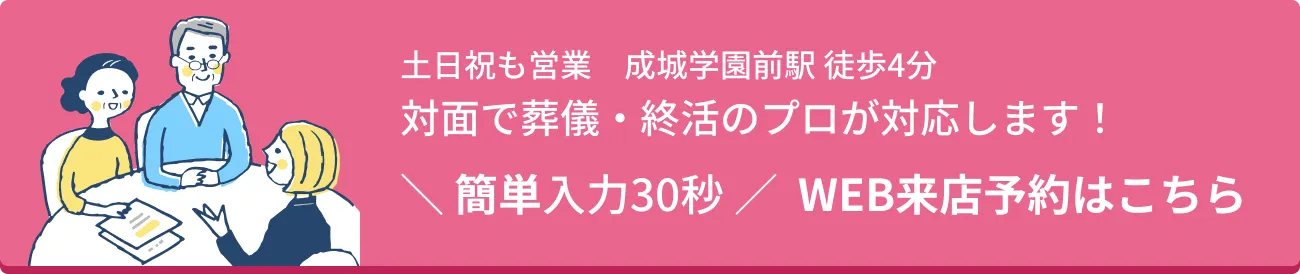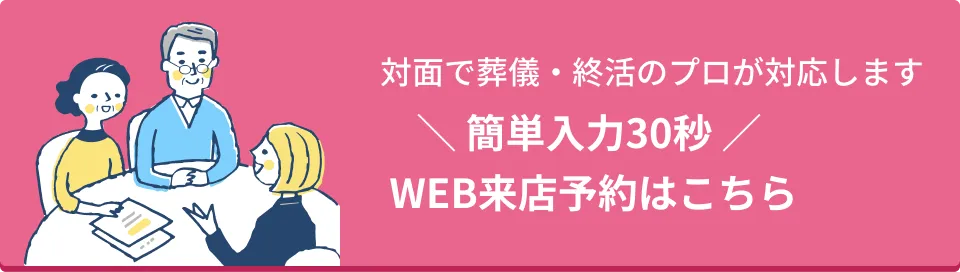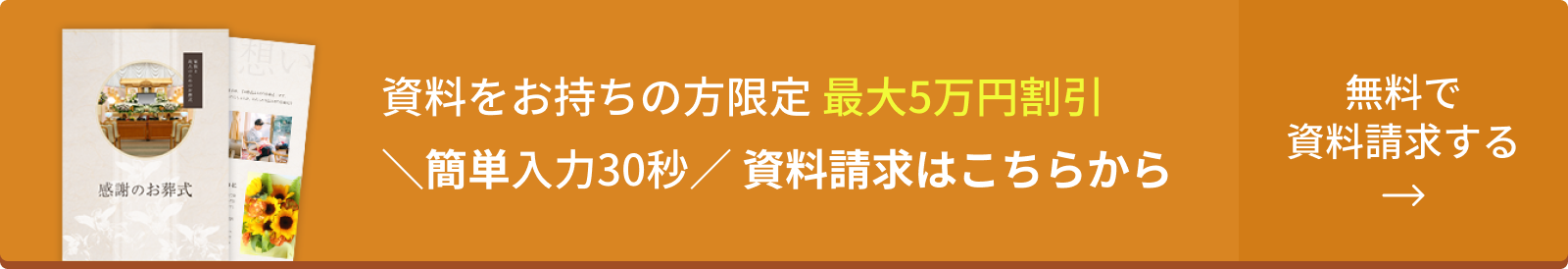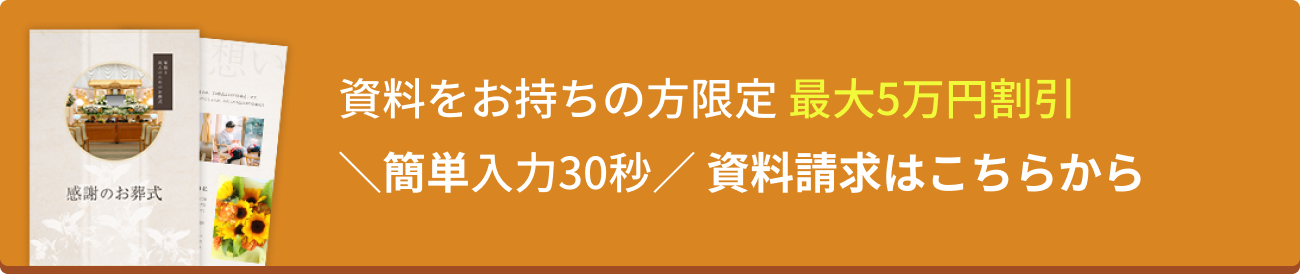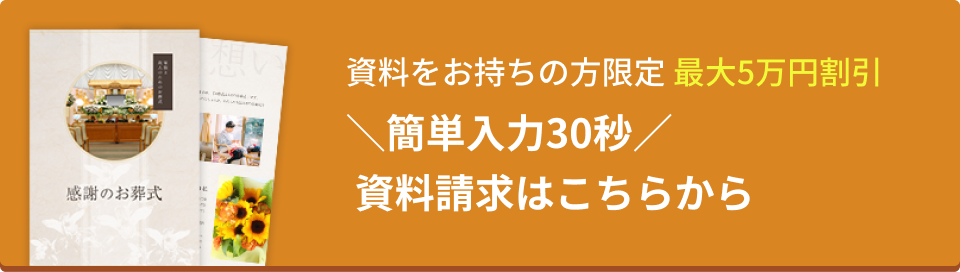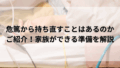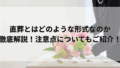ある日突然「危篤」と告げられたとき、私たちは何をすればよいのか、どこから手をつければいいのか迷ってしまいます。
その不安や混乱の中で、大切な人のそばに寄り添いながら、後悔のない時間を過ごすための行動を冷静に判断するのは決して簡単なことではありません。
そんなときにこそ、「危篤から亡くなるまで」の流れや注意点、家族としての行動、心構えを前もって知っておくことが、精神的な支えになります。
本記事では、実際に直面する場面での行動・感情・手続き・配慮のポイントまで網羅的に解説します。
誰でも理解できる言葉で、「今すぐ何をすべきか」がわかるよう構成しているため、難しい知識は必要ありません。
この記事を読むことで、「やるべきこと」と「やらなくていいこと」が明確になり、心のゆとりと安心を得ることができます。
限られた時間を、かけがえのない時間にするための支えとして、ぜひご活用ください。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。
危篤から亡くなるまでの流れ
まず危篤状態と連絡が来たら万が一の事態に備える心の準備をした後、必要な持ち物を用意して病院に向かい、亡くなった後は葬儀関連の準備をする必要があります。
危篤と診断された時に知るべきことや家族の過ごし方、亡くなった後の流れの詳細をご紹介していきます。
- 危篤と診断されたときに知っておくこと
- 最期が近づいたときの家族の過ごし方
- 亡くなったときの対応と必要な手続き
- 亡くなった後の葬儀準備について
危篤と診断されたときに知っておくこと
危篤とは、病気や怪我が進行し、生命維持が困難なレベルに達し、いつ命を落としてもおかしくない状態を指します。
これは医学的な明確な基準があるわけではなく、医師が患者のバイタルサイン(脈拍、呼吸、血圧、体温)や意識レベルの低下などから総合的に判断し、回復の見込みが低いと判断された場合に家族に告げられます。
最期が近づいたときの家族の過ごし方
危篤の連絡を受けたら、まず自身の気持ちを落ち着かせ、万が一の事態に備える心の準備をすることが大切です。
動揺したままでは、病院へ向かう途中で事故などのトラブルを引き起こす可能性もあります。
次に、できる限り迅速に病院へ駆けつけましょう。
危篤状態はいつ急変するか予測できないため、大切な人との最後の時間を少しでも長く過ごすことが重要です。
意識がない状態でも、聴覚は最後まで残っている可能性があるため、「ありがとう」や思い出話など、前向きな言葉を優しく語りかけることが勧められます。
また、数日間の泊まり込みが必要になる可能性も考慮し、着替え、携帯電話の充電器、現金などの最低限の持ち物を事前に用意しておくと安心です。
しかし、準備に時間がかかる場合は、すぐに病院へ向かうことを優先し、準備は後回しにしても問題ありません。
医療面では、担当医と密に連携を取り、患者の現在の状態を常に把握することが理想的です。
また、患者本人が延命治療や緩和ケアを希望しているか、リビングウィル(人生の最終段階における事前書)や事前指示書があるかを確認し、その後の治療方針について家族で話し合うことが重要です。
これは故人の尊厳に関わることであるため、可能であれば元気なうちに本人の意思を確認しておくことが望ましいとされています。
亡くなったときの対応と必要な手続き
危篤状態から実際に旅立たれた場合、まず医師による死亡確認が行われ、その後に死亡診断書が発行されます。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医または警察に連絡し、死亡診断を仰ぐ必要があります。
その後、看護師によるエンゼルケアが行われ、故人の体を清潔にし、身だしなみを整えます。
また、故人の口元を水で湿らせる「末期の水」という儀式を行うこともあります。
病院の霊安室に故人を安置できる時間は限られているため、速やかに葬儀社に連絡し、ご遺体の搬送と安置を依頼する必要があります。
基本的に慌てて冷静な判断ができない状態のことが多いため、死亡診断書や死体検案書などをどこに出せばいいのか、その後何をしたらいいのかについては、葬儀社に相談することをおすすめします。
亡くなった後の葬儀準備について
危篤の連絡を受けた時点で、もしもの時に備えて葬儀の準備を可能な範囲で始めておくと、後々の精神的負担を軽減できます。
事前に葬儀社を決めて、葬儀の形式や予算について相談しておくことで、冷静な判断が難しくなる臨終後も落ち着いて対応できるでしょう。
病院が紹介する葬儀社は割高になる傾向があるため、注意が必要です。
葬儀の形式や埋葬方法など、故人の生前の希望があれば事前に確認し、希望がない場合は宗教的儀式や規模などを家族で話し合って決定します。
危篤から葬儀までの間には、病院の入院費や治療費、遺体運搬費、そして葬儀費用など、まとまった現金が必要になる場合があります。
故人の銀行口座は臨終後に凍結されるため、相続関係が整理されるまで引き出しができなくなるので、事前に必要な費用を引き出しておくか、家族で立て替えを検討しましょう。
親族や友人、知人への連絡は、故人から見て三親等以内を基本とし、特に親しかった人にも連絡を入れます。
連絡は電話が最も適切で、深夜や早朝であっても緊急を要するため、時間を気にせず速やかに行うことが重要です。
電話が繋がらない場合は、メールやSNSも併用し、必要最低限の情報を簡潔に伝えます。
自身の勤務先や子どもの学校・園などへも、休暇の申請や仕事の引き継ぎのため、状況を早めに伝える必要があります。
危篤時には忌引き休暇が適用されないため、有給休暇や会社の特別休暇を利用するのが一般的です。
危篤から亡くなるまで家族が取るべき行動
危篤から亡くなるまでに家族ができるべきこととして、主治医とのコミュニケーションを深めたり延命治療の選択肢の確認、葬儀社に早急に連絡することが挙げられます。
- 主治医に容態の確認や質問をして状況を把握
- 延命治療の選択肢を確認する
- 葬儀社に早急に連絡をする
主治医に容態の確認や質問をして状況を把握
危篤状態では、患者の容態が刻一刻と変化する可能性があります。
そのため、主治医と密に連絡を取り合い、現在の状態や今後の見通しについて随時確認し、常に状況を把握しておくことが非常に重要です。
疑問や不安な点があれば、遠慮なく質問し、納得のいく説明を受けるようにしましょう。
延命治療の選択肢を確認する
患者の尊厳に関わる重要な決定として、延命治療や緩和ケアに関する本人の希望を事前に確認し、家族間で治療方針について話し合う必要があります。
もし、リビングウィル(人生の最終段階における事前書)や事前指示書が作成されている場合は、その内容を確認し、本人の意思を尊重した決断を下すことが求められます。
可能であれば、患者が元気なうちにこれらの意思を確認しておくことが理想的です。
葬儀社に早急に連絡をする
大切な人が危篤状態にあるときから、もしもの事態に備えて葬儀社に早めに連絡を取り、準備を進めておくことが強く推奨されます。
臨終を迎えた後では、悲しみの中で短時間で多くの手続きや決定を迫られることになり、精神的な負担が非常に大きくなります。
事前に葬儀社に相談し、葬儀の形式や予算の大枠について話し合っておけば、慌てることなく故人を穏やかに見送る準備ができます。
病院の霊安室でのご遺体安置時間は通常限られているため(数時間から半日程度)、搬送先となる葬儀社の安置施設や自宅への手配を迅速に行うためにも、事前の検討が不可欠です。
危篤から亡くなるまでの注意点
危篤から亡くなるまでの注意点として、移動手段はなるべく交通機関を利用する、夜間や休日でも連絡が取れるように準備する、付き添いの際は体調管理と交代制を心がける、持ち物は必要最小限にまとめておく、職場や学校への早めの相談や報告を忘れないなどがあります。
- 移動手段はなるべく交通機関を利用する
- 夜間や休日でも連絡が取れるように準備する
- 付き添いの際は体調管理と交代制を心がける
- 持ち物は必要最小限にまとめておく
- 職場や学校への早めの相談や報告を忘れない
移動手段はなるべく交通機関を利用する
危篤の知らせを受けて病院へ向かう際は、気が動転していることが予想されます。
自家用車を運転すると、焦りから事故のリスクが高まる可能性がありますので、タクシーや公共交通機関の利用を検討することが推奨されます。
タクシーは都心部であれば24時間利用可能で、運転の心配がありません。遠方の場合は、友人や家族に送ってもらうことも選択肢の一つです。
夜間や休日でも連絡が取れるように準備する
危篤の連絡は、時間帯を問わず突然入ることがあります。
緊急性が高いため、深夜や早朝であっても、電話で速やかに親族や関係者に連絡することが最も適切です。
この際、「夜分遅くに失礼します」といった配慮の一言を添えると良いでしょう。
電話が繋がらない場合は、留守番電話を残したり、メールやSNSを併用したりして、確実に情報を伝える工夫が必要です。
付き添いの際は体調管理と交代制を心がける
危篤状態の患者に付き添う期間は、数時間から数週間、あるいはそれ以上と予測が困難な場合があり、長期間にわたる付き添いは家族の心身に大きな負担をかけます。
疲労が蓄積しないよう、家族間で交代制を設け、適度な休息を取ることが非常に大切です。
また、食事や睡眠をしっかり取るよう互いに気遣い、感情を素直に表現できる環境を整えることも重要です。
必要であれば、病院のソーシャルワーカーや心理カウンセラーに相談することも検討しましょう。
持ち物は必要最小限にまとめておく
病院での付き添いは数日間に及ぶ可能性があるため、最低限の持ち物をまとめておくことが推奨されます。
これには、着替え(1〜2日分)、スマホや携帯電話の充電器や洗面用具、現金(5〜10万円程度)、メモ帳とペン(医師の説明を記録するため)などが含まれます。
もしもの際に備えて、喪服や葬儀関連の資料なども用意しておくとさらに安心です。
職場や学校への早めの相談や報告を忘れない
危篤の連絡を受けたら、自身の勤務先や子どもの学校・園などへも、休暇の申請や仕事の引き継ぎのため、できるだけ早く状況を伝える必要があります。
危篤状態はまだ死亡ではないため、忌引き休暇は適用されず、多くの場合、有給休暇を利用することになります。
会社によっては、家族看護休暇や特別休暇が認められる場合もありますので、就業規則を確認したり、人事部門に相談したりすることが推奨されます。
危篤状態が長引く場合は、状況を定期的に報告し、必要に応じて休暇の延長手続きを行うなど、職場との密なコミュニケーションを心がけましょう。
危篤から亡くなるまでのよくある質問
危篤から亡くなるまでのよくある質問をご紹介。
危篤と連絡を受けたらすぐに病院へ行くべきですか?
危篤の連絡を受けたら、可能な限りすぐに病院へ駆けつけるべきです。
危篤状態は容態が急変する可能性があり、いつ命を落としてもおかしくないため、少しでも長く大切な人のそばに付き添うことが重要です。
たとえ意識がない状態であっても、聴覚は最後まで残っている可能性があるため、語りかけることで気持ちを伝え、後悔のない時間を過ごすことができます。
遠方に住んでいる家族にはどう伝えればいいですか?
遠方に住む家族には、病院へ駆けつけるまでに時間がかかることを考慮し、できるだけ早く連絡を入れることが大切です。
その際、病院に来るよう「催促」するのではなく、あくまで現在の状況を「報告」する形で伝え、相手の気持ちを察して配慮のある言葉を選ぶようにしましょう。
交通費や宿泊費の負担が必要になる可能性も伝えることで、相手が適切に対応できるよう支援できます。
危篤から亡くなるまでの期間はどれくらいですか?
危篤状態から臨終までの期間は、個人差が非常に大きく、正確に予測することは困難です。
一般的な目安としては、数時間から2〜3日以内に旅立つケースが多いですが、まれに10日以上、あるいは数週間から数ヶ月続くこともあります。
一時的に容態が安定する「小康状態」に転じることもありますが、これは完全な回復を意味するものではなく、再び危篤状態に戻る可能性もあるため注意が必要です。
記事全体のまとめ
ご家族が危篤状態と告げられることは、非常に辛く、動揺を伴う出来事です。
しかし、この困難な時期を乗り越え、後悔のないお別れをするためには、事前の心の準備と具体的な行動計画が非常に重要です。
危篤の段階で葬儀社への事前相談を進め、葬儀の形式や予算について大まかな見当をつけておくことで、故人が旅立った後の慌ただしい時期に冷静に対応し、穏やかに送り出すことができるでしょう。
これらの情報を事前に把握し、心の準備と実務的な準備の両方を整えることで、大切な人との最後の時間を意味あるものにし、後悔の少ないお別れができるでしょう


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。