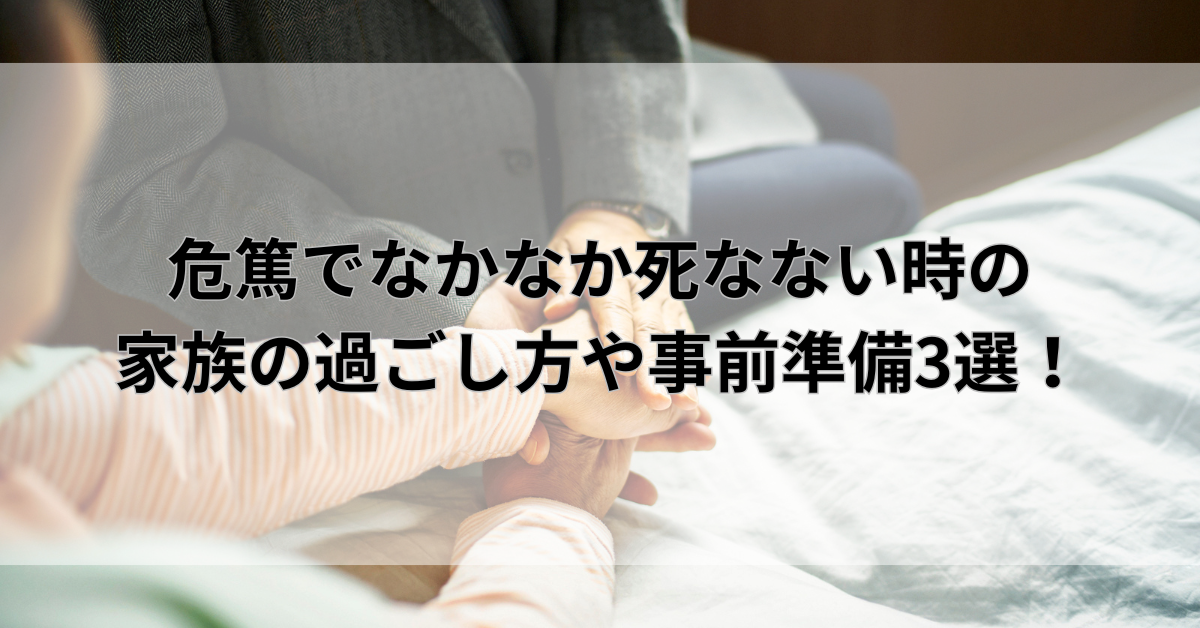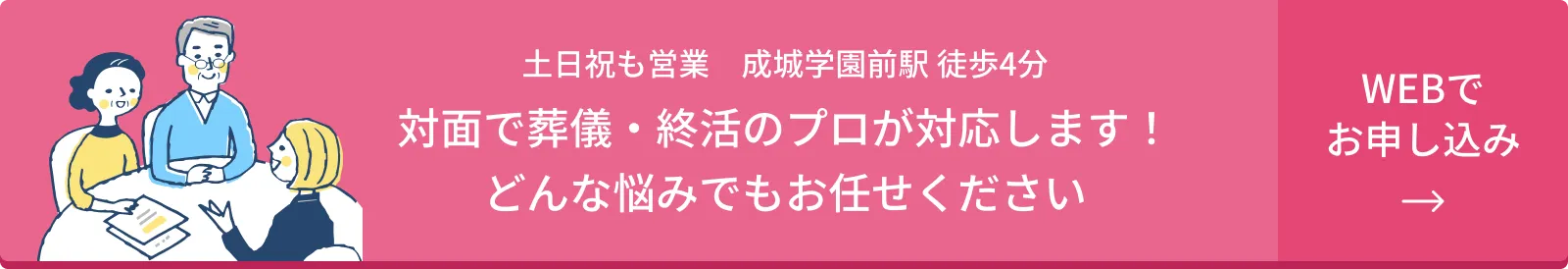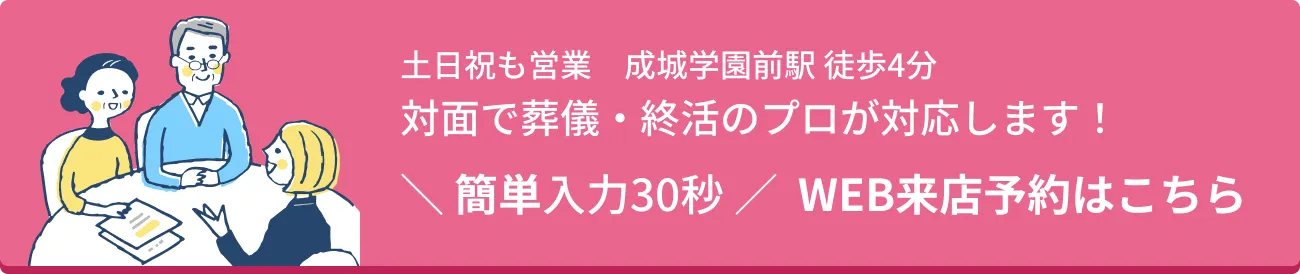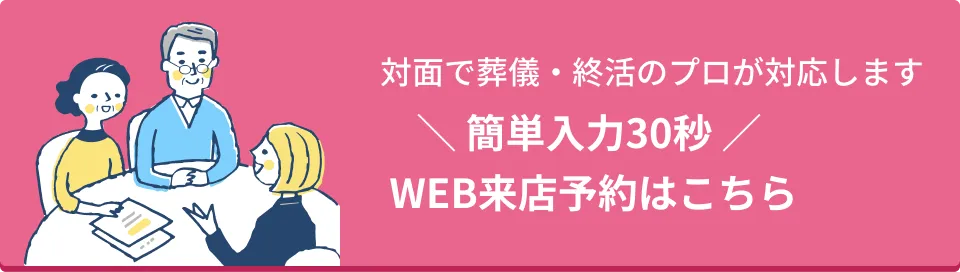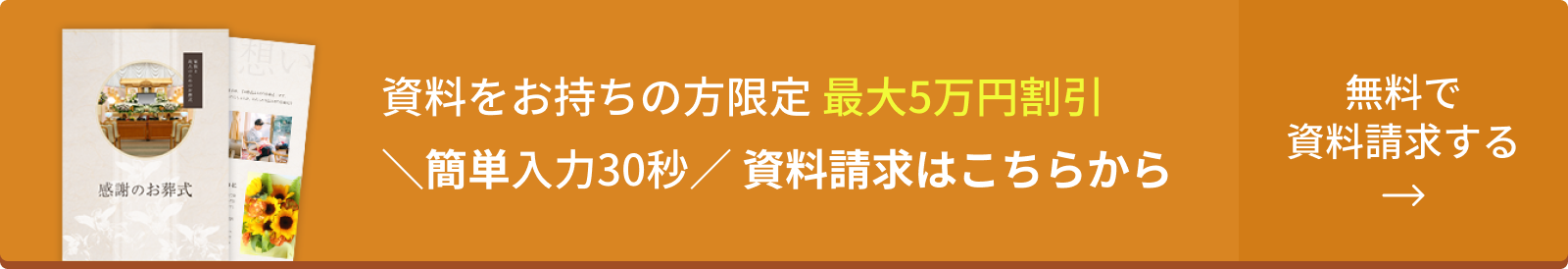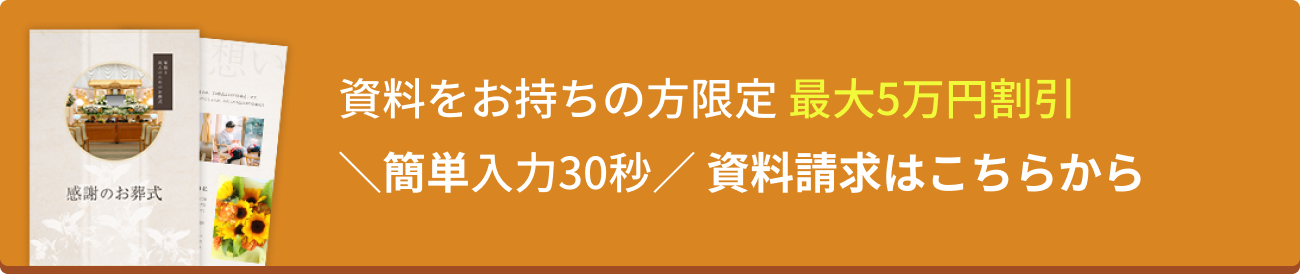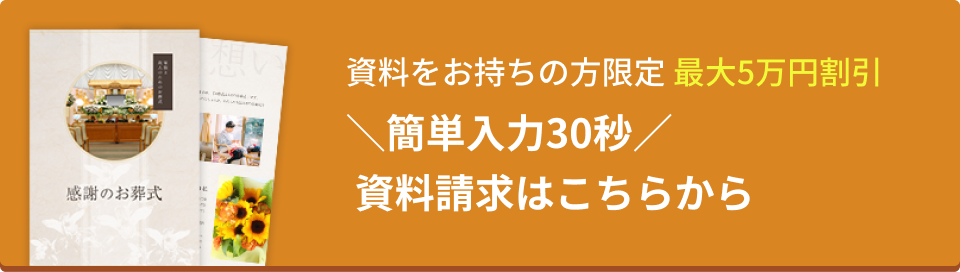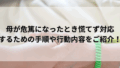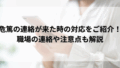危篤と聞いて心の準備をしたのに、なかなか亡くならず、戸惑いが続いていませんか?
「いつまで続くのか」「何をしてあげればいいのか」不安は尽きません。
この記事では、そうした状況で落ち着いて過ごすための考え方や、家族としてできることを丁寧に紹介します。
具体的な過ごし方や、気持ちの整理のヒント、よくある疑問にも答えます。
つらい時間を少しでも穏やかに過ごすために、知っておいてよかったと思える内容をお届けします。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。
危篤でなかなか死なない時にまず知っておくべきこと
危篤と医師から告げられてからなかなか死なない時にまず理解しておくべきことは、すぐに亡くならないこともある、ということです。
他にも理解しておくべき内容をご紹介。
- 危篤と言われてもすぐには亡くならないこともある
- 日数には個人差があり、正確な予測はできない
- 近くにいることが大切な時間になる理由
危篤と言われてもすぐには亡くならないこともある
「危篤」とは、病気や怪我の状態が非常に重く、生命が危険に瀕しており、回復の見込みが極めて低いと医師が判断した状況を指します。
しかし、この宣告があったからといって、すぐに命が尽きるわけではないことを知っておく必要があります。
患者さんの強い生命力や、人工呼吸器などの延命措置によって、危篤状態が予想よりも長く続くケースも少なくありません。
一時的に病状が落ち着き、「小康状態」や「中治り現象」と呼ばれる回復を見せることもあります。
日数には個人差があり、正確な予測はできない
危篤状態から最終的な臨終を迎えるまでの期間は、人によって大きく異なります。
数分から数時間で亡くなる方もいれば、数日、数週間、あるいは数ヶ月にわたって危篤状態が続くこともあります。
そのため、医師でも正確な時間を予測することは非常に難しいのが現状です。
近くにいることが大切な時間になる理由
危篤状態は、その人の命の終わりが差し迫っていることを意味し、ほとんどの場合で「死」と密接に関わってきます。
そのため、家族としてはいつでも駆けつけられるように準備しておくことが大切です。
可能な限り本人に寄り添い、最期の瞬間に立ち会うことは、後悔のないお別れのために非常に重要です。
患者さんの意識がなくても、聴覚は最後まで残ると言われているため、感謝の気持ちや励ましの言葉、楽しい思い出を語りかけることが、本人にとって大きな支えとなる可能性があります。
危篤からなかなか死なないときの家族の過ごし方
危篤からなかなか死なない場合は精神的な負担が増えるため、無理に1人で抱え込まず家族に相談をして交代してもらうことやご自身の体調にも気を付けながら生活をすることが重要です。
- ずっとそばにいられない時はどうする?
- 交代や休憩を取りながら見守る方法
- 声かけや手を握るなどできることを大切に
ずっとそばにいられない時はどうする?
危篤状態が長期化すると、家族の肉体的、精神的な負担が大きくなることがあります。
家族が複数いる場合は、全員が24時間付き添い続けるのが難しいこともあります。
そのような時には、無理に一人で抱え込まず、家族間で付き添いを交代するなどして、負担を分担することを検討しましょう。
交代や休憩を取りながら見守る方法
付き添い中は、自身の体調管理にも十分に注意を払う必要があります。
十分な睡眠を取り、バランスの取れた食事を心がけ、適度な休憩を挟むことで、心身の健康を保つことが大切です。
無理を続けると、看病する側が体調を崩し、かえって患者さんや他の家族に心配をかけることになりかねません。
不安な気持ちは一人で抱え込まず、親しい家族や友人、あるいは専門機関に相談することも有効な心のケアになります。
また、医療スタッフと密に連携し、患者さんの状況について情報を共有することも重要です。
声かけや手を握るなどできることを大切に
危篤状態の患者さんは、たとえ反応がなくても、家族の声が聞こえている可能性があると言われています。
そのため、積極的に話しかけ続けることが推奨されます。
感謝の気持ちや励ましの言葉を伝えたり、楽しかった思い出話をしたり、手を握ったり、患者さんが好きだった音楽をかけたり、思い出の写真を見せたりすることも、心を通わせる大切な時間となります。
患者さんが穏やかに最期を迎えられるように、家族として寄り添い、できる限りのことをしてあげましょう。
臨終を告げられた後には、「末期の水」を口元に含ませるなどの最後の別れの儀式を行うこともできます。
危篤からなかなか死なない時にできる準備
心の整理や親族への連絡、もしもの時に為に慌てないように必要な書類や情報の確認などが事前準備としてできます。
- 心の整理の時間として過ごす
- 家族や親戚に連絡をしておく
- もしもの時に慌てないための事前確認
心の整理の時間として過ごす
危篤の知らせを受けたら、まずは落ち着いて深呼吸をすることが肝要です。
希望を持つことは大切ですが、一方で「亡くなること」を想定し、心構えをしておく必要があります。
この心の準備をしておくことで、いざという時に冷静な判断を下し、後悔のないように最善を尽くすことができるでしょう。
家族や親戚に連絡をしておく
心の準備が整ったら、迅速に家族や親戚に連絡を入れます。
連絡の優先順位は、患者さんとの関係性が深い人からが基本ですが、遠方に住んでいる人には特に早く連絡することで、最期に間に合う可能性が高まります。
一般的には3親等以内の親族に連絡することが推奨されますが、血縁に関わらず、患者さんと特に親しかった友人や知人にも連絡すると良いでしょう。
事前に連絡先のリストを作成しておくと、いざという時に慌てずに済みます。
また、自身の勤務先にも早めに状況を報告し、菩提寺がある場合は僧侶にも連絡をしておくと、その後の葬儀の準備がスムーズに進みます。
連絡方法は、緊急性が高いため電話が基本です。深夜や早朝であっても、一言お詫びを添えて連絡することが望ましいとされています。
電話が繋がらない場合は、メールやSNSを補助的に活用することもできます。
連絡時には、自身の名前、患者さんとの関係、患者さんの状態、病院名、住所、病室、自身の連絡先など、必要な情報を漏れなく伝えるようにしましょう。
もしもの時に慌てないための事前確認
万が一の事態に備えて、葬儀社を事前に選定しておくことを強くお勧めします。
病院の霊安室に遺体を安置できる時間は限られているため、事前に信頼できる葬儀社を決めておくことで、臨終後もスムーズに搬送や葬儀の準備を進めることができます。
複数の葬儀社から見積もりを取り、故人や家族の希望に合ったプランを選ぶと良いでしょう。
患者さんが生前に葬儀に関する希望をエンディングノートなどに残している場合は、それを尊重することも大切です。
また、病院での治療費や今後の葬儀費用、僧侶へのお布施など、まとまった費用が発生する可能性があります。
故人の銀行口座は亡くなると凍結され、すぐに引き出せなくなるため、事前に必要な現金を確保しておくと安心です。
さらに、病院に泊まり込む可能性も考慮し、数日分の宿泊準備(携帯電話と充電器、財布、着替え、洗面用具、常備薬など)をしておくと良いでしょう。
患者さんの臓器提供や献体の意思を確認しておくことも、本人の希望を尊重するために重要です。
死亡後の手続きに必要な戸籍情報を事前に確認したり、遺言書の作成、重要な書類の整理、生前整理など、終活に関する準備を進めておくことも、残された家族の負担を軽減する上で非常に役立ちます。
危篤からなかなか死なないときの注意点
危篤からなかなか死なないと思っている時に気を付けるべき注意点として、体力や気力の消耗や勤務先や周囲への連絡や調整を怠らないようにしましょう。
体力や気力の消耗に気をつける
危篤状態の家族に寄り添うことは、心身ともに大きな負担となります。
長期間の付き添いや看病は、看病する側の体力や気力を著しく消耗させる可能性があります。
家族を支え続けるためにも、自分自身の体調管理を怠らないようにすることが重要です。
十分な休息を取り、無理をせず、必要であれば他の家族や医療スタッフに助けを求めるようにしましょう.
勤務先や周囲への連絡や調整を怠らない
危篤状態の段階では、一般的に忌引休暇は適用されません。多くの場合、有給休暇や欠勤扱いとなります。
危篤状態が長期化する可能性があるため、自身の上司や人事部に状況を相談し、休暇の調整や業務の引き継ぎについて話し合うことが大切です。
日中の連絡が可能な時間帯に、職場に定期的に状況を報告することで、周囲の理解を得やすくなります。
焦りや苛立ちを抱えないために気持ちの余裕を持つ
危篤状態が長引くことは、家族にとって精神的な負担となり、時には焦りや苛立ちを感じてしまうこともあるかもしれません。
しかし、「危篤なのに、なかなか死なない」といった不適切な言葉を口にすることは避けるべきです。
このような発言は、故人の死を望んでいるように聞こえかねず、周囲に誤解や不快感を与える可能性があります。
また、患者さんが危篤状態にある間は、不要な外出や娯楽は控えることが望ましいです。
特に、飲み会や旅行など人目につく場所での行動は、他者から「身内が苦しんでいる時に何をしているのか」と誤解される可能性があるため注意が必要です。
疲れた時は、自宅など人目を気にせずリラックスできる場所で過ごし、ストレスを発散するようにしましょう。
病院内では、他の患者さんやその家族への配慮を忘れず、大声で騒いだり、取り乱したりする行動は慎むべきです。
家族にかける言葉も、相手の状況を思いやり、安易な励ましではなく、気遣う言葉を選ぶことが大切です。
危篤からなかなか死なない時によくある質問
「何日ぐらい続くことが多いのか」「途中で帰宅しても大丈夫?」などのよくある質問をご紹介。
何日くらい続くことが多いの?
危篤状態が続く期間は個人差が大きく、明確な日数はありません。
医師でも正確に予測することは難しいとされています。
短ければ数時間で亡くなることもありますが、多くの場合は数時間から2〜3日程度で臨終を迎えることが多いとされています。
しかし、患者さんの強い生命力や医学的な延命治療によって、数週間から数ヶ月間続くケースも存在します。
途中で帰宅しても大丈夫?
危篤状態は「いつ亡くなってもおかしくない」状況であるため、できる限り付き添うことが推奨されます。
しかし、危篤状態が長期化し、家族が24時間付き添い続けることが難しい場合もあります。
そのような時は、無理をせず、家族で交代しながら付き添うことを検討しましょう。
一時的な帰宅が必要な場合は、他の家族と協力し、病院との連絡体制を確保するなど、いつでも迅速に動ける準備を怠らないことが大切です。
自身の体調管理も重要なので、無理のない範囲で付き添うようにしましょう。
最後にしてあげられることって何?
患者さんにしてあげられることは、本人の気持ちを尊重し、穏やかに寄り添うことです。
意識がなくても聴覚が残っている可能性があるため、感謝や励ましの言葉を伝えたり、楽しかった思い出話を語りかけたりすると良いでしょう。
手を握る、患者さんが好きだった音楽をかける、思い出の写真を見せるなども有効です。
また、身の回りの世話をすることも重要なサポートとなります。
臨終を告げられた後であれば、医療従事者の指示に従い、「末期の水」を口元に含ませたり、「エンゼルケア」を行ったりすることで、安らかな旅立ちをサポートすることができます。
さらに、本人の希望を尊重したお見送りの準備を進めておくことも、家族ができる大切なことです。
これには、生前の臓器提供や献体の意思確認、そして希望に沿った葬儀社の選定などが含まれます。
記事全体のまとめ
長期化する危篤状態においては、看病する側の心身の消耗に注意し、家族間で交代しながら無理のないように付き添いましょう。職場への適切な連絡と調整も欠かせません。
最も大切なことは、後悔のない時間を過ごすことです。
ネガティブな発言を避け、周囲への配慮を忘れず、患者さんに感謝の気持ちを伝えたり、思い出話をしたりして、穏やかに寄り添うことが、家族にできる最善のことと言えるでしょう
また、長引く場合は事前に葬儀社に相談をしておくことで、精神的な負担を軽減することができます。


〒157-0066
東京都世田谷区成城2-15-6 イル・レガーロ成城1F
(成城学園前駅 徒歩4分)
営業時間
10:00~17:00 土日祝も営業
(事前予約いただければ上記時間外も対応いたします。)
※来店予約は必須ではありません。お気軽にお立ち寄りください。
お電話・ご希望の場所(施設・ご自宅など)への訪問でのご相談もお受けしております。