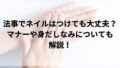葬儀の場で供花を贈るとき、どんな花がふさわしいか悩む方は少なくありません。
間違った花やタイミングで贈ると、かえって失礼になってしまうこともあります。
本記事では、葬儀に適した花の種類や相場、宗教別のマナー、避けるべきNG例まで詳しく解説します。
さらに、実際の注文方法や贈り方のポイントも紹介。
この記事を読むことで安心して花を贈れるようになります。
葬儀の花に関する基本的な考え方
葬儀の花とお祝いの花の違いや供花の意味など、基本的な考え方の違いについてご紹介。
- 遺族の意向を確認する
- 葬儀社に連絡する
- 予算と内容を決める
- 発注者情報を伝える
葬儀の花とお祝いの花は違う
葬儀に供える花は、お祝いの場面で贈られる花とは異なる特別な意味合いを持ちます。
供花は派手な色使いを避け、白を基調とした落ち着いた色合いが特徴で、籠花やスタンド花といった特定の形式が用いられます。
これは、故人を悼み、遺族に弔意を示すためのものであり、祝意を表すものではありません。強い香りの花やトゲのある花は、一般的に不適切とされています。
供花の意味と役割
供花(きょうか、またはくげ)は、故人の冥福を祈り、お悔やみの気持ちを遺族に伝えるために花のことで、基本的に祭壇に供えられます。
その由来は、釈迦が亡くなった際に天から宝花が降って供養されたという説に基づいています。
供花は故人の霊を慰めるだけでなく、葬儀の祭壇や会場を美しく飾り、厳粛な雰囲気を作り出す重要な役割も担っています。
また、悲しみに包まれた遺族にとっては、多くの供花が故人への想いや慰めとなり、故人との別れを惜しむ気持ちの象徴ともなります。
供花には通常、贈り主の名前が記された名札が添えられ、故人との関係性の深さに応じて祭壇に配置されます。
地域や宗教による違いを理解する
供花の種類、形式、およびマナーは、故人の宗教や宗派、さらには地域の慣習によって大きく異なります。
そのため、供花を贈る前には、必ず遺族に葬儀の形式や供花に関する意向を確認することが不可欠です。
この確認を怠ると、意図せず失礼にあたる可能性や、会場の都合で飾ってもらえないといった事態に繋がりかねません。
葬儀の花は葬儀社経由でも依頼できる
葬儀に関連する花は葬儀社経由でも依頼することができます。
葬儀社を通すメリットと注意点
供花の手配は、原則として葬儀を執り行う葬儀社を介して行うのが最も一般的で確実な方法です。
葬儀社を通す最大のメリットは、葬儀会場全体の装飾の統一感を保てる点にあります。
供花の配置は喪家と葬儀社が相談して決定するため、葬儀社が贈り主を把握している必要があります。
また、故人の宗教や葬儀の規模に合わせた適切な花を選んでもらえるため、マナーに沿った供花を用意しやすいでしょう。
ただし、一部の葬儀社では、提携している生花店以外の供花の持ち込みを許可していない場合があります。
そのため、葬儀社を介さずに供花を手配する際は、事前に葬儀社に持ち込みが可能かどうかを確認することが非常に重要です。
依頼の流れと準備しておく情報
供花を依頼する際の一般的な流れは、遺族の意向を確認した後に葬儀社に連絡を行い、予算と内容を決めてから発注者情報を伝えましょう。
- 遺族の意向を確認する
- 葬儀社に連絡する
- 予算と内容を決める
- 発注者情報を伝える
遺族の意向を確認する
まず、遺族が供花を受け入れる意向があるかを確認します。遺族は多忙なため、直接連絡するのではなく、葬儀社を通じて問い合わせるのが一般的です。
葬儀社に連絡する
葬儀社に、喪主の名前、葬儀の日程、会場名を伝え、供花の依頼を行います。
予算と内容を決める
予算や希望する供花の内容を葬儀社に伝えます。どのような種類があるか不明な場合は、葬儀社のラインアップから選んだり、相談して決めたりできます。
発注者情報を伝える
贈り主の住所、氏名、電話番号、故人との関係性を伝えます。
また、供花に添える木札に記載する名前についても明確に伝えてください。
多くの葬儀社は、電話のほか、オンラインやFAXでの注文にも対応していますが、疑問点がある場合は電話で直接相談する方が確実です。
葬儀の花の種類と選び方
葬儀の花は白い花が定番としてよく選ばれますが、何故白い花であるのかや適切な花の種類や避けるべき種類についてご紹介。
- 定番の白い花とその理由
- 洋花・和花の使い分け方
- 避けるべき花の色や品種
定番の白い花とその理由
供花は、白を基調とした落ち着いた色合いが一般的です。
この白い色は、純粋さや清潔さ、そして故人への深い敬意を表す象徴とされています。
よく選ばれる花の種類としては、菊、百合、胡蝶蘭、カーネーション、トルコキキョウなどが挙げられます。
特に菊は、日持ちが良く、清らかで優雅なイメージを持つため、仏事において重用されてきました。
洋花・和花の使い分け方
伝統的な葬儀では菊が中心でしたが、近年では故人の生前の好みや遺志を尊重し、淡いピンク、紫、青などの洋花も供花として用いられることが増えています。
これにより、祭壇がより華やかになる場合もあります。ただし、キリスト教式では菊はほとんど使われず、カーネーションやユリといった洋花が主に選ばれます。
避けるべき花の色や品種
供花を選ぶ際には、トゲのある花、香りの強い花、毒性のある花、ツルのある花、すぐに枯れる花や落ちやすい花、派手な色や黒っぽい花など故人への敬意と配慮から避けるべき花がいくつかあります。
- トゲのある花
- 香りの強い花
- 毒性のある花
- ツルのある花
- すぐに枯れる花や落ちやすい花
- 派手な色や黒っぽい花
トゲのある花
バラやアザミなど、トゲのある花は、痛みや殺生を連想させるため不適切とされています。ただし、近年ではバラも使われることがありますが、その場合はトゲを取り除いて飾られます。
香りの強い花
カサブランカやクチナシなど香りの強い花は、他の参列者に不快感を与えたり、線香の香りを妨げたりする可能性があるため、避けるのがマナーです。
毒性のある花
彼岸花、チューリップ、スズランなど、毒性を持つ花は供花として不適切です。
ツルのある花
クレマチスやジャスミン、朝顔などツル性の植物は、「ツルに絡まって成仏できない」という考え方から避けることが望ましいとされています。
すぐに枯れる花や落ちやすい花
山茶花や椿のように花が落ちやすい種類や、すぐに枯れてしまう花も、清掃の手間を増やしたり、見た目を損なったりするため適切ではありません。
派手な色や黒っぽい花
四十九日を迎えるまでは、白系の花を基本とし、カラフルな花や特に黒っぽい色の花は避けるべきとされています。
葬儀の花の費用相場と贈るタイミング
供花などの葬儀に関連する花の費用相場についてですが、基本的に1基あたり15,000円から30,000円程度です。
また、贈るタイミングとしては余裕を持って手配するには、通夜の1〜2日前までに注文を済ませましょう。
- 供花の価格帯はどれくらい?
- 贈るタイミングと連絡の方法
供花の価格帯はどれくらい?
供花の一般的な価格帯は、1基あたり10,000円から30,000円程度が目安とされています。
このうち、15,000円から20,000円の範囲が主流です。
供花は1つを「一基(いっき)」と数え、2つの場合は「一対(いっつい)」と数えます。
一対で贈る場合は、費用も概ね2倍になります。
故人との関係性によって適切な金額は異なり、親族からの供花は比較的高額になる傾向があります。
しかし、あまりに高額すぎる供花は、かえって遺族に気を遣わせてしまう可能性があるため、適切な範囲で選ぶことが大切です。
贈るタイミングと連絡の方法
供花は、葬儀会場の祭壇に飾られるため、通夜が始まる前、遅くとも通夜当日の午前中、または通夜開始の数時間前までに会場に届くように手配するのが一般的です。
余裕を持って手配するには、通夜の1〜2日前までに注文を済ませると良いでしょう。
訃報を受けてから準備を始めるのがマナーとされており、「事前に準備していた」という印象を避けるためです。
もし葬儀に間に合わない場合でも、通夜の翌日の葬儀・告別式までに手配するか、後日故人の自宅へ届けて後飾り祭壇に供えるという選択肢があります。
自宅へ贈る場合は、初七日法要から四十九日法要までの間に届けるのが適切なマナーとされています。
その際は、遺族に受け取り可能な日時を事前に確認し、時間指定で配送するようにしましょう。
葬儀の花は宗教によって異なる
葬儀の花は宗教によって異なりますので、事前に確認する必要があります。
- 仏式の供花と宗派の違い
- 神式・キリスト教式の特徴
- 無宗教の場合の配慮点
仏式の供花と宗派の違い
日本の葬儀の大部分を占める仏式では、供花に主に百合や白い菊・蘭などの生花が使われます。
これらの白い花は、故人の魂の清らかさを表します。
また、淡いピンク、紫、黄などの差し色を加えることもあります。
供花としては、香りが強かったり毒性があるような種類、トゲのある花は避けるのがマナーとされていますが、近年ではバラなども使用されるケースが増えており、その際にはトゲは取り除かれます。
地域や宗派によっては特定の慣習があり、例えば関西地方の一部や日蓮宗などでは、強い香りと毒性から邪気払いの意味を持つ樒(しきみ)が供花として用いられることがあります。
神式・キリスト教式の特徴
神式とキリスト教式の特徴をご紹介。
神式(神道)
神道の葬儀における供花は、基本的に仏式と共通しており、白色の百合や菊やカスミソウが主に選ばれることが多いです。
キリスト教式
キリスト教の葬儀における供花は、故人の霊を慰めるためではなく、遺族を慰める目的が強いとされています。
使用される花はユリ、カーネーション、胡蝶蘭などの洋花が中心で、菊はほとんど用いられません。
供花には名札を付けず、葬儀会場ではなく故人の自宅宛に、持ち運びやすいコンパクトなバスケット形式で贈るのが一般的です。
また、生花のみが使われ、造花やプリザーブドフラワーは避けるべきとされています。
無宗教の場合の配慮点
無宗教形式の葬儀における供花に関する具体的な記述は少ないものの、献花はキリスト教式のほか、無宗教形式の葬儀でも用いられることがあります。
無宗教の葬儀では、特定の宗教的制約がないため、遺族の希望や故人の生前の好みを最大限に尊重することが重要となります。
一般的には、派手すぎない、落ち着いた色合いの生花を選ぶのが無難でしょう。
葬儀の花に関するよくある質問
葬儀の花に関するよくある質問をご紹介。
遠方からでも花を贈れる?
はい、遠方からでも供花を贈ることは可能です。
インターネットのオンラインストアや葬儀社に事前に連絡をして置けば、自宅から手軽に供花を手配し、指定の場所へ配送してもらうことができます。
一部のサービスでは当日配達にも対応している場合があります。
ただし、供花を依頼する前に、必ず葬儀社に会場への持ち込みが可能かどうかを確認してください。
葬儀社によっては、提携外からの供花を受け付けない場合があるため、事前の確認がトラブルを避けるために重要です。
花の注文は何日前がベスト?
供花は、葬儀会場の祭壇に飾られるため、通夜が始まる前、遅くとも通夜当日の午前中、または通夜開始の数時間前までに届くように手配するのが理想的です。
余裕を持って手配するには、通夜の前日、または2日前までに注文を済ませておくと安心です。
訃報を受けてから準備を始めるのがマナーであり、あまりに早く届けることは「事前に準備していた」という印象を与えかねないので注意が必要です。
もし通夜に間に合わない場合は、葬儀・告別式までに手配するか、故人の自宅へ届けて後飾り祭壇に供えることも可能です。
家族葬でも供花は必要?
家族葬のような小規模な葬儀では、供花を辞退する遺族が増えています。
これは、会場のスペースが限られていることや、遺族が「関係者に負担をかけたくない」と考えているためです。
そのため、家族葬で供花を贈る際は、必ず事前に遺族の了承を得ることが最も重要です。
もし辞退された場合は、無理に贈ろうとせず、別の形で弔意を示すべきです。
故人との関係が非常に深い場合は、香典と供花の両方を贈ることもあります。
また、葬儀に参列できない場合や、香典を辞退された際に、供花を手配して弔意を表すことも有効な手段です。
記事全体のまとめ
供花とは、故人の冥福を祈り、遺族の悲しみを慰め、葬儀会場を荘厳に彩る大切な役割を果たす生花です。
故人や遺族の宗教、宗派、地域の慣習を理解し、特に遺族の意向を事前に確認することが何よりも重要です。
手配は葬儀社を介するのが一般的で、会場全体の統一感やスムーズな配置を考えると最も確実な方法です。
供花の種類は、清らかさを象徴する白を基調とし、菊、百合、カーネーションなどが定番です。
適切なマナーを踏まえ、故人への感謝と哀悼の意を込めて供花を贈ることが、最後のお別れの場にふさわしい心遣いとなります。
他にも葬儀の花に関するマナーや対応だけでなく依頼も感謝のお葬式にお任せください。