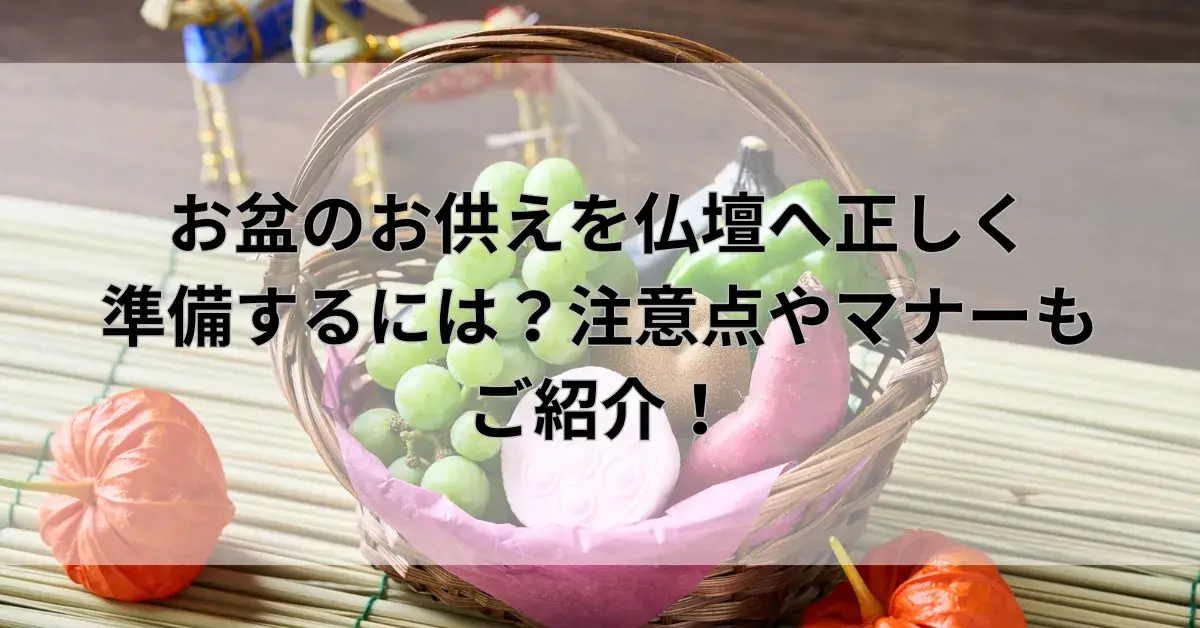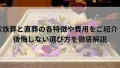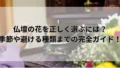お盆のお供えを仏壇へ準備する際、「何を選び、どのように並べるべきか」迷う方は多くいます。
地域差や宗派差があるため、正しい作法が分からず不安を抱く場面も少なくありません。
そこで本記事では、お盆のお供えを仏壇へ用意する際に押さえておきたい基本と実践方法をわかりやすく解説します。
意味やルールを知ることで、迷わず適切なお供えを整えられるようになります。
お盆の習わしに沿って仏壇を整えたい方が、安心して準備できる知識をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
お盆にお供えを仏壇へ準備する品の種類一覧
お盆にお供えを仏壇へ準備する際の果物・お菓子・飲み物の種類について解説していきます。
仏壇に供える際の定番の果物
お盆の仏前を華やかに彩る果物は、豊かさや恵みを象徴するお供え物として人気があり、決まりはありませんがりんごや梨、みかんなどが選ばれることが多いです。
お供え物として果物を選ぶ際は、丸い形状のものが縁起が良いとされています。
これは、「円」が「縁」に通じ、故人やご先祖様との良好な関係が長く続くようにという願いが込められているためです。
数を揃える場合には、故人との縁が切れることを連想させる割り切れる数(偶数)を避け、奇数で用意することが一般的です。
また、夏場は果物が傷みやすいため、なるべく日持ちし、常温で保存が可能なものを選ぶと良いでしょう。
お盆お供え仏壇に供えるお菓子・飲み物
お菓子は、故人が生前に楽しんだ喜びを共有する意味合いを込めて供えられる定番の品です。
お盆の期間中、仏壇に飾っておくことが多いので、日持ちがする焼き菓子、せんべい、羊羹、ゼリーなどが推奨されます。
生クリームを使った生菓子(ケーキやシュークリームなど)は日持ちしないため、避けるのが基本マナーです。
お参りに来た方々へお下がりとして配ることを考えて、個包装になっている品物を選ぶと喜ばれます。
伝統的なお供え物としては、落雁(らくがん)が定番です。
これは水分が少なく保存性に優れ、仏教の象徴である蓮の花をかたどっていることが多い砂糖菓子です。
飲み物に関しては、故人の好物であったものが選ばれることが多いですが、アルコール類は供養の場にはふさわしくないため、供えるのは避けるべきとされています。
お盆でお供えを仏壇へ並べる際の配置と注意点
仏壇の向き・位置やお供え物で避けるべき種類などの注意点について解説していきます。
仏壇の向き・位置の注意点
仏壇の向きについては浄土真宗・天台宗・浄土宗は東向き、曹洞宗・臨済宗は南向きです。
また、日蓮宗は決まりはなく真言宗は本山の位置によって変わるため事前に確認しておきましょう。
お盆お供え仏壇で避けたい置き方
お供え物を仏前に置く際、避けるべき品物があります。
仏教では殺生(不殺生戒)を禁じる教えがあるため、肉、魚、卵といった動物性の食品はお供え物としてふさわしくありません。
また、これらの食品は夏場に傷みやすく、衛生面でも問題があるため避けるべきです。
さらに、匂いや刺激の強い食材(五辛/五葷)も、煩悩を刺激するとされ(例:ニンニク、ネギ、ニラなど)、供物には不適切です。
食べ物以外では、トゲのある花(バラなど)や毒性のある花、香りの強すぎる花、そして仏壇を汚す可能性がある鉢植えも避けて飾ります。
ロウソクの火を消す際には、人の息は不浄であるという考えから、息を吹きかけて消すことはマナー違反とされています。
必ず手で仰ぐか、火消し用の道具を使って消しましょう。
お盆でお供えを仏壇に準備する際に気を付けたいポイント
気を付けたいポイントとして適した量とバランスや宗派によって供養方法が異なりますのでご紹介。
適した量とバランス
お盆のお供え物は、弔問客から頂く品物も含め、最終的に家族や参列者で分け合って消費することを前提に量や品目を選ぶことが重要です。
特に、お盆の期間中(4日間)は供物を仏壇に飾ったままにすることが多いため、夏場の暑さでも腐敗しにくいよう、日持ちがして常温保存が可能な品物を選ぶよう心がけましょう。
生のお供え物(精進料理など)を用意する場合は、お盆の期間中の3食分として食べられる量にするのが望ましいとされます。
他家へお供え物を持参する場合の金額の目安は、一般的に3,000円~5,000円程度とされています。
遺族に余計な負担をかけないよう、この範囲内で品物を選ぶのがマナーです。
ただし、故人が初めて迎える新盆(初盆)については少し高く5,000円~1万円と設定することもあります。
宗派によって供養の仕方が異なる
お盆の供養の仕方は、宗派によって大きく異なる点があるため、事前に確認が必要です。
特に浄土真宗では、故人の魂が現世に戻るという考え方がないため、ご先祖様を迎えるための精霊棚や御霊供膳といった特別な飾り付けや供養は原則行いません。
浄土真宗におけるお供えは、故人への供養というよりも、阿弥陀如来への感謝を表すことが目的とされています。
ただし、一部地域では浄土真宗でも切子灯籠を飾る慣習が見られます。
浄土宗や真言宗など、他の在来仏教の宗派では、お供え物の基本は共通していますが、地域や寺院特有の慣習がある場合もあるため、迷った場合は菩提寺の住職に尋ねるのが確実です。
農作物の選定に関するマナー
お盆の飾り付けには、夏の農作物であるキュウリとナスが欠かせません。
これらは、割り箸や麻がらなどで手足を付け、キュウリを精霊馬、ナスを精霊牛に見立てて、ご先祖様があの世とこの世を移動するための乗り物として供えます。
馬(キュウリ)には「一刻も早く帰ってきてほしい」という願いが、牛(ナス)には「帰りは景色を楽しみながらゆっくり戻ってほしい」という願いが込められています。
また、お供えする農作物には、旬の果物や野菜(百味五果)が選ばれますが、仏教の教えに基づき、煩悩を刺激するとされる五葷(ネギ、ニラ、ニンニクなど)は選ばないのがマナーです。
お盆でお供えを仏壇に準備した後の片付け方とタイミング
お供えをした後の片づける時期や処分方法についてご紹介。
片付ける最適な時期
お盆の飾りやお供え物の片付けは、ご先祖様の霊をお見送りする送り火が終わった後に行います。
具体的には、お盆の最終日である8月16日の夜、または翌日の17日中に全て片付けを済ませるのが一般的です。
精進料理など傷みやすい飲食物は、お盆の期間中でも、長時間供えたままにせず、冷めたりぬるくなったりした時点で仏壇から下げましょう。
湯気が出なくなったら下げるのが目安です。
処分方法と扱い方
お供え物の中で食べられるものは、粗末にせず、家族や親戚で分け合っていただくのが正しい作法です。
仏教では、これはご先祖様から分け与えられた「お下がり」として、感謝の気持ちと共にいただくことが供養になるとされています。
食べきれずに残ってしまったものや、精霊馬、蓮の葉などの生物の飾り物については、そのまま一般ゴミとして捨てるのではなく、他のゴミと区別して処分する配慮が必要です。
処分する際は、半紙などの白い紙に包み、塩で清めてから可燃ごみとして出すのが一般的な方法です。
寺院にお焚き上げをお願いするか、庭に埋めることができる場合もあります。
新盆で飾った白提灯は、一年限りで使い回しをしないのが原則であり、お盆が終わった後、供養の上でお焚き上げなどで処分します。
通常の絵柄入り盆提灯は、来年以降も使用できますので、手入れをして保管しましょう。
残った供物の食べ方・保存方法
仏壇から下げたお供え物は、ご先祖様から授かった「お下がり」として、集まった家族や親戚一同で分け合って食べるのがマナーであり、供養の一環です。
食べることで、ご先祖様との繋がりを感じ、日々の恵みに感謝します。
お供えした食べ物が大量で食べきれない場合は、お参りに来た弔問客や親族に、お土産として持ち帰ってもらうことも問題ありません。
保存に関しては、傷みやすい食品は仏前に供えた後、すぐに冷蔵庫に入れるなどして、新鮮なうちに消費することが大切です。
お供え物は、傷んで腐ってしまう前に下げるということが、ご先祖様や仏様への敬意を示す上で最も重要な点です。
お盆でお供えを仏壇に選ぶ際のよくある質問
お盆でお供え物を仏壇に選ぶ際のよくある質問をいくつかご紹介していきます。
お供え物で必要なものは?
お盆の仏壇のお供え物の基本は、仏教の「五供(ごく)」と呼ばれる5つの要素です。
これらは日々の供養の基本でもあります。
五供とは、香(線香)、花(仏花)、灯燭(とうしょく)(ロウソク)、浄水(水やお茶)、飲食(おんじき)(ご飯、果物、お菓子など)の5つを指します。
お盆の時期には、この五供に加えて、盆提灯や精霊棚、精霊馬・精霊牛、水の子といったお盆特有の飾りや供物を準備して盛大にご先祖様を迎えることが望ましいとされています。
NGな食べ物はある?
お盆のお供え物として避けるべき食べ物は、仏教の教えと衛生面から、主に以下の品物が挙げられます。
動物性の食品
仏教では殺生を避ける(不殺生戒)ため、肉、魚、卵、乳製品などの動物性の品は供物として不適切です。
刺激の強い食材
煩悩を刺激するとされる、辛味や香りが強い野菜(五葷/五辛、例:ニンニク、ネギ、ニラ、タマネギ、ラッキョウ)も避けるべきです。
また、夏の暑い時期であるため、日持ちしない生菓子や、溶けて仏壇を汚す可能性がある飴なども避けるのが賢明です。
故人の好物でこれらの品を供える場合は、調理して傷まないよう配慮し、すぐに下げることが大切です。
アルコール類も供養の場にはふさわしくないため避けるのが基本です。
いつお供えを並べればいい?
お盆のお供え物は、ご先祖様をお迎えする迎え盆までに飾り付けを完了させます。
一般的に、8月盆の地域では8月13日、7月盆の地域では7月13日が迎え盆とされているため、遅くともこの日の朝までには精霊棚を整え、お供え物を並べ終えるのが望ましいでしょう。
盆提灯などお盆の飾りについては、お盆の月に入った頃から準備を始めることができます。
飲食の供物については、以前は朝と昼の2回とされていましたが、現代ではご家庭の都合に合わせて、毎回の食事の前や朝のみなど、無理のないタイミングで供えることが推奨されています。
記事全体のまとめ
お盆は、ご先祖様や故人の霊が現世の自宅へ戻り、家族と一時を過ごす日本の伝統的な仏教行事です。
この期間に、ご先祖様への感謝の気持ちを込めて、心を尽くしてもてなすことがお供えの基本的な意味となります。
お供え物は「香・花・灯燭・浄水・飲食」の五供に基づき用意され、仏壇の前には精霊棚(盆棚)盆提灯は、ご先祖様を導く目印として欠かせない存在です。
そのため、どの種類を選べばいいのか、片付けについて理解をしておきましょう。